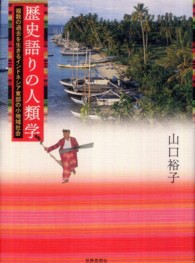『歴史語りの人類学-複数の過去を生きるインドネシア東部の小地域社会』山口裕子(世界思想社)
実証的文献史学を中心とする近代歴史学は、国民国家の制度や文化の形成・発展に寄与し、国民意識を高めるのに貢献した。つまり、近代の歴史叙述は、おもに国民を読者対象とした。したがって、世界史は各国史の寄せ集めで、たとえば山川出版社の「世界各国史」(32巻、1954-92年;新版28巻、1998-2009年)は、「政治史を軸に、社会・経済・文化にも着目した」。しかし、このような時代遅れのシリーズの考えでは、「世界を知ろう 21世紀へ」という謳い文句とは真逆に、21世紀の世界に対応できなくなっている(ただし、各巻においては、21世紀に立派に通用する優れたものが多々ある)。
このような近代の歴史観から解放されるためには、文献ではわからない歴史観を知る必要がある。それを教えてくれるのは、歴史学だけでなく人類学や社会学、表現文化学、地域研究など、人びとの営みを主体に研究している人たちである。本書もそのひとつで、実証的文献史学ではけっしてわからない歴史と人びとのつながりを教えてくれる。そして、そのことは国民国家形成の邪魔をするような歴史を語ることが憚られた時代から解放されて、人びとが国民以外のさまざまな読者を対象として歴史を語り出したことを示している。
本書の研究対象の中心であるブトン島は、インドネシア東部スラウェシ島南東沖にある。著者、山口裕子は、インドネシア国史のなかでもほとんど語られることのない、この島や王国に関心をもった理由を、つぎのように語っている。「今日のブトン社会に赴き、一歩踏み込んで人々の暮らしを見れば、そこには人々の生活に「歴史」が実に多様な形で織り込まれている。その意味でブトンは「歴史の豊かな」島である。人々は「歴史」を語り、さまざまに表象するのみではない。その「歴史」は人々の社会生活に浸透しており、人々はむしろ「歴史を日常的に生きている」」。
「本書は、人々が語る「歴史」と、それを語る人々の「現在」の双方に着目し、そのいずれもが対照的なブトン島の二つの村落社会を対象に、日常、非日常の社会生活と不可分な「歴史語り」を社会人類学的に記述、分析する民族誌である。そのうえで、「歴史語り」と、外部の一次資料にもとづくブトン王国史を比較考察するとともに、語り手の現在のアイデンティティの政治をブトン地域の近現代の政治史と関連させて探求する。それにより、実証主義対相対主義という、歴史をめぐる近年の理論的な対立を昇華する方法を提示し、さらに実証主義でも相対主義でも十分に説明できない、人々が現に生きる社会生活において、「歴史」を語り表現することの多元的な意味を明らかにしようとするものである」。
本書は、「歴史語りの人類学」を目指す民族誌であり、そのためにつぎのような考察と分析をおこなっている。「ブトン社会における歴史語りを、語られた出来事が属する「過去」と、それを語る人々の「現在」のいずれか一方に還元することなく、時間的にも空間的にも決して一元的ではないコンテクストにできる限り適切に位置づけながら考察していく。その結果として、本書で援用する方法は、よく整理された方法論の観点からは、折衷的で不十分に見えるかもしれない。だがそれは、理論的思考を優先させるのではなく、歴史語りの資料がしめす多元的で複合的な、なおかつ微細なほころびにできる限り忠実に、それぞれにふさわしいと思われる方法を模索した結果である。これらの考察によって全体として、今日の[ブトンの]ウォリオ人とワブラ人の生そのもの、多元的で豊かな歴史語りの実践をその一部とする人々の生そのものを記述し分析する」。
著者は、「もっとも重要なことと、真実は書かれる必要がない」という歴史語りと、欧文の一次史料を中心とする外部資料との間のほころびに注目し、「西洋近代的な「歴史学」が想定するのとは完全に一致しない別の「真実」の在り方が存在すること」を示した。そして、つぎのように結論づけた。「ウォリオ社会においてもワブラ社会においても、歴史語りは、不変の過去の歴史の単なる再現(表象)ではない。また語り手による完全にフリーハンドの創造物や単なるメッセージの乗り物であるだけでもない。本書では、その出発点においては人類学的歴史研究を援用してきた。だがそれによって到達したのは、「洗練された実証主義」でも「より相対主義的な分析」でも十分には説明できない、「歴史」が単に生活のなかで語られるというよりは、「歴史語り」が人々の生活の時空間のなかで生きられているともいえる、彼らの生の在り方そのものであった。本書で試みてきたのは、そのような「歴史」と「歴史語り」を一部とする、ウォリオとワブラという小規模社会の社会生活の記述と分析の民族誌、つまり「歴史語りの人類学」の実践である」。
日本でも、地方の伝承に基づく「歴史語り」による町おこしや歴史大河ドラマなどの時代劇に、実証主義的な史実を求めたりはしない。山に入ると、前近代の立派な石垣や古墳群の出現に驚かされることがある。それらは、現代の生の在り方と、どう結びついているのだろうか。著者は、日本ではあまりみられない、「歴史語り」と地方社会との関係、さらに国家、時代との関係を探ろうとしている。歴史学が注目してこなかった視点に立って、歴史が人びとの日常生活のなかに、どのように潜り込んでいるかを考察・分析している。本書のような新たな見方から学ぶことによって、歴史学は近代から解放され、人びとの生活にとっての歴史の存在意味がわかってくるのだが、・・・。