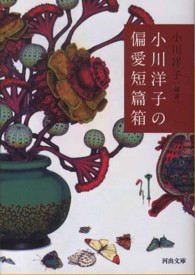『小川洋子の偏愛短篇箱』小川洋子・編著(河出文庫)
ふだんはあまり読まないミステリやSF、長編の翻訳物などを、汗だくになりながら一気読みする。今の私には夏休みなどないけれど、そんな、ただ読むことを楽しむための読書で、夏休みらしい気分を味わうというのが、いつの頃からかのならわしとなっている。で、この夏はこれに、と手にしたのが本書。
……つまりこの本は、私にとって大事な作品な作品を十六集め、十六の仕切りに納めた収集箱なのである。誰に見せる必要もない、私以外に誰一人在りかを知らない箱であったのだが、本人も予想しなかったちょっとした偶然により、ふと蓋が開いた、そんな感じだろうか。
小川洋子がセレクトした短編のアンソロジー。収録作品は以下の十六編である。
内田百閒「件」
尾崎翠「こおろぎ嬢」
金井美惠子「兎」
牧野信一「風媒結婚」
川端康成「花ある写真」
横光利一「春は馬車に乗って」
森茉莉「二人の天使」
武田百合子「薮塚ヘビセンター」
島尾伸三「彼の父は私の父の父」
向田邦子「耳」
三浦哲郎「みのむし」
田辺聖子「雪の降るまで」
吉田知子「お供え」
まえがきにあるとおり、読み手は、十六に仕切られた収集箱のなかで、それぞれが不思議な存在感を放つ物体を、ひとつひとつ眺めていくかのような気分にさせられる。
それで思い出したのが、先日行った小石川植物園の一角にある、東大の総合研究博物館の分館で常設展示されている「驚異の部屋」だった。
大航海時代の西欧では、王侯貴族や学者たちによって、世界じゅうから集められた珍品を陳列することが流行したという。展覧会の概要によれば、そうした「『もの』をめぐる原初的な『驚異』の感覚は、体系的な知の体得へ先立つものであるとともに、新たな知の獲得へと人々を駆り立てる潜在的な原動力」なのだという。
この「驚異の部屋」にならい、大学に遺された由緒ある学術標本によって構成された展示空間には、鉱物や植物の標本やホルマリン漬け、動物の剥製や骨、年代物の映写機や天秤といったさまざまな器具や模型が、古い什器に収まってならんでいる。
そして、ふつうの博物館ならば、展示物のひとつひとつについているはずのプレートがここにはない。展示物についての情報が与えられないという状況で、観衆はただ視覚的な驚きに徹し、そのもののかたちに見入り、味わい、想像力を働かせることになる。
旧東京医学館本館、明治はじめに建てられた木造擬洋風建築であるその館内に繰り広げられた「驚異の部屋」。インスタレーションを見ているような、もしくは贅沢な骨董品店に入りこんだような、あるいは富豪の好事家がつくった秘密の部屋に案内されたような気分で展示物を眺めつつ、こうも思った、「小川洋子の世界みたい」と。
その時は、『薬指の標本』を思いだしていたのだけれど、小川のいう十六に仕切られた標本箱も、あの空間にふさわしいではないか。
仕切りにおさめられたものたちは、一見正体不明の何ものかである。鉱物のようにも、植物の種のようにも、動物の体の一部のようにもみえて、そのどれでもないようなもの。あるものはダイヤモンドのように硬そうだったり、あるものはゼラチンのようにグニャグニャとしていたり、またあるものは、そう、小川が子どものころにひそかに集めていたという爪やかさぶたのように、味わい深くも不格好なかたちをしている。
もちろんこの標本箱にも、内容物の名を示すプレートはない。作品にはタイトルというものがあるけれど、ここに並んでいる物体は物語のエッセンスのカタマリであるから、それが何かは見る者、つまり読み手の想像力に委ねられているのである。
本書には、それぞれの作品のあとに、編者による「解説エッセイ」が付けられているけれど、それも結局、プレートの代わりにはならない。編者・小川は、標本の側らで学芸員のようにしてそれを指し示しているのではなく、読み手と肩をならべて標本箱を眺め、そっと耳打ちするようにして語っているのであるから。
小川洋子のファンならば、ここに差し出された物語のそこここに、彼女の作品にひそむキーワードを発見することだろう。私はひとつひとつの作品と、そしてそのならびから、彼女の書くものから感じるのと似た独特のおかしみ、いびつさ、閉塞と浮遊、などなどを受け取りつつ、いろいろな時代と場所をめまぐるしく周遊したかのような気分になれた。標本箱をじっとのぞき込んでいたと思いきや、さっきとは別のところにいる自分に気がつく。そんな、「おはなしのちから」を味わえた夏の読書であった。