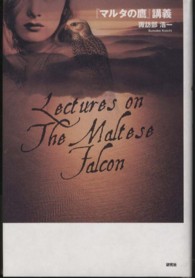『「マルタの鷹」講義』諏訪部浩一(研究社)
「文学研究の硬派と軟派」
諏訪部浩一さんは研究者としては「硬派」である。たとえば、諏訪部さんの授業では一冊の小説を何年もかけて読むらしい。一回の授業で読むのは数頁、一年でも数十頁という勘定である。実に禁欲的なやり方だ。十年後にやっと全部を読み終わる頃には、始まりの方で起きた殺人事件のことなど忘れてしまうのではないか?と心配する人もいるかもしれない。言ってみれば(あえてアメリカ風の比喩を使うと)ひとつのハンバーガーを切り分けて、朝・昼・晩と、いや、明日も明後日も明明後日も食べるようなものではないか。
しかし、実はこれは文学研究にかぎらず、大学の授業としては王道なのである。筆者が学生の頃にも、毎年シラバスに「Sein und Zeitを読む」としか書かない哲学の先生がおられて、ドイツ語にもう少し自信があれば是非のぞいてみたかった。そんなにゆっくり読むなんて、いったいどんな秘儀が行われているのか、確認したいと思ったものだ。
本書はその「秘儀」を、かなり親切に開陳した本である。全部で23の章に「イントロダクション」と「あとがき」と「語注」がついて、ふつうの大学の授業の1年分弱。硬派で知られる諏訪部さんとしてはやや軟派な部類だろうが、それにしても対象はあの『マルタの鷹』だ(2時間足らずのB級アクション映画!)。Sein und Zeitをじっくり読むというのとはわけが違う。より奥の深い「秘儀」が必要となるにちがいない。
だからこそ、「講義」という設定にこだわったのだろう。もちろん講義というのはフィクションで、おそらく本書の原稿は――まあ、ひょっとすると集中講義などで使った可能性もないではないが――基本的には印刷物として読まれるために準備されたものである。しかし、それをあえて「講義」と呼ぶところに著者の意図がありそうだ。
それはいったいどんな「意図」か。ダシール・ハメットの『マルタの鷹』はかつては有名だったかもしれないが、今や〝ハードボイルドおっさん〟のノスタルジアくらいにしか見られない、つまり、「かつての名作」にありがちな黄昏れた気配を漂わせた作品である。しかし、諏訪部さんはこの作品がまだ生きていることを示そうとする。そのためには「『マルタの鷹』はまだ生きてるぞ!」などと声をあげてもまったく意味がない。そこで彼は、ちょっと別の作戦を使った。物語に「直接的関与」をするのである。しかも、それは巧妙なからくりとともに行われる。諏訪部さんは自身の「直接的関与」については――いかにも硬派な先生らしく――素知らぬ風を決め込んだ上で、そのかわりに、作品の主人公である私立探偵スペードが、探偵のくせに事件に「直接的関与」をしているという事実に焦点をあてる。
探偵による事件へのこうした直接的関与という特徴は、ハードボイルド探偵小説が志向する「リアリティ」に関連している。というのは、探偵が事件解決のための捜査をすることは、彼(もしくは彼女)の関わりによって(探偵自身のみならず)事件が変容してしまうという、「現実」的な可能性を内包するはずだからだ。むろん伝統的探偵小説では、こうした「変容の可能性」という「現実」を排除するべく事件はしばしば「密室」で既に「起こってしまったこと」として提示されるのだが(ただし、この「取り返しのつかなさ」も、紛れもなくまた一つの「現実」であるのだが)、そのように考えてみればなおさら、ハードボイルド小説においては事件とは常に「進行中のもの」であることが、その意義とともに理解されることになるはずだ。(49)
後半のところの「探偵」を「批評家」と、「事件」を「作品」と読み替えてみるとおもしろい。
批評家による作品へのこうした直接的関与という特徴は、ハードボイルド批評家が志向する「リアリティ」に関連している。というのは、批評家が作品読解のための捜査をすることは、彼(もしくは彼女)の関わりによって(批評家自身のみならず)作品が変容してしまうという、「現実」的な可能性を内包するはずだからだ。むろん伝統的批評では、こうした「変容の可能性」という「現実」を排除するべく作品はしばしば「密室」で既に「起こってしまったこと」として提示されるのだが(ただし、この「取り返しのつかなさ」も、紛れもなくまた一つの「現実」であるのだが)、そのように考えてみればなおさら、ハードボイルド批評においては作品とは常に「進行中のもの」であることが、その意義とともに理解されることになるはずだ。
驚くほど意味が通ってしまうことがおわかりだろう。どうやら諏訪部さんは、講義形式というフィクションを採用することによって、『マルタの鷹』がいかに「進行中のもの」であるかを示したかったのだ。そこではもちろん、講義という〝進行的〟な形式が効力を発揮するわけだが、文章となると(つまり仮の講義では)そうした進みゆく感じを出すのは意外と難しい。そこで「秘儀」が必要になってくる。諏訪部さんの文章には独特の持続性と緊張感があって、そのおかげで「進みゆく感じ」が作られている。ごく簡単な例を「イントロダクション」からあげると、
それほどまでの「精読」に『マルタの鷹』が値するのかという疑問を抱く人がまだいるかもしれないが、右に述べたこととの関連であえていっておけば、ハメットは自分を「単なる探偵小説家」とは考えていなかったし、方法論に関しても、モダニスト的な意識が極めて強い作家であった。(6)
…というような箇所の、「まだいるかもしれないが」(とくに「まだ」)や、「あえていっておけば」(とくに「あえて」)や、「考えていなかったし」(とくに「し」)などにこめられた微妙な苛立ちやお叱りの口調は、ハードボイルド批評家たる諏訪部さんの「講義」の進行感を増し、それが「直接的関与」の気配を作るとともに、最終的には「直接的関与」をされている『マルタの鷹』の側の「依然として生きている」というフィクションを工作するのである。
もちろん上述のものはほんの序の口。ハードボイルド批評家たる諏訪部さんの、「事件」へのより深い「直接的関与」は本文を読み進めれば随所で出遭うことができる。筆者がとりわけ印象に残ったのは、ハメット作品としては「殺人」がきわめて少ないという『マルタの鷹』の、その数少ない殺人のひとつ「ジャコビ船長の死」についての「講義」である(第十六講)。この場面では主人公スペードがマルタの鷹の彫像を手に入れて、その興奮のあまり、珍しく我を忘れて死体の手を踏んでしまうのだが、諏訪部さんはこのことについて次のように言う。
だが、スペードの足がジャコビの手の上にあるという描写は、こうした「非情」な振る舞いが、同時に陥穽でもあるという可能性を前景化する。つまり、スペードが死者を足蹴にするこの場面は、彼が死者に足を引っ張られているようにも見えるのだ。そしてそのように理解されてみれば、この「死者」は単なる「死体」であることをやめるだろう。ジャコビは「黒い鳥」を虚しく追い求めてきた人間達の象徴となり、ブリジッドというファム・ファタールを虚しく助けようとした男達の列に連なるのだ。かくしてジャコビの虚しい死は、それを「非情」に扱おうとするときに、スペードにとって「他人事」ではなくなってしまうのである。彼が慌てて足を引っこめるのは、まったくもって無理もないことだといわねばならないだろう。(218)
「踏みつけ」についての解釈そのものももちろんおもしろいのだが、何より興味深いのは、諏訪部さんが「つまり、スペードが死者を足蹴にするこの場面は、彼が死者に足を引っ張られているようにも見えるのだ」といった活動写真の弁士めいた語り口を通し、そうした解釈そのものを、いわば煽っているということである。こうして、ふつうの人ならまず気がつかないような『マルタの鷹』の別の表情を明るみに出し、しかもそれを読者にぐいぐいと読ませることで、諏訪部さんは『マルタの鷹』にあらためてその新しい命を生きさせるのである。
本書が「講義」であることの今ひとつの意味は、その「おみやげ」の多さにもある。諏訪部さんの語りには敏感なジャンル意識があって、『マルタの鷹』を論じつつも、文学における「枠」とは何か?という問いがつねに頭をもたげている。そのせいもあって、たとえば「恋愛」ひとつにしても、「我を忘れて本気になった方が負け」(123)といったマクロな視点からのコメント(もしくは忠告?)がなされるので、読者は最終的には「恋愛」「ファム・ファタール」「探偵小説」「警察もの」「殺人」といった大衆小説の鍵概念について、多くの〝常識〟を獲得したうえで帰途につくことができるという案配なのである。やはり、正真正銘の講義だと言えるだろう。
本書ではところどころで「探偵でありつづけることのたいへんさ」への言及がなされる。それは裏返せばハードボイルド批評家としての諏訪部さん自身の「たいへんさ」ともからんでくる。しかし、同時に、それだけ「たいへん」で忙しいのに語り続けてしまう、その明るい負担感のようなものが仄見えるところに、この「講義」のほんとうの楽しさがあるようにも思った。