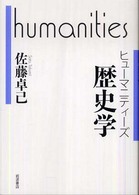『ヒューマニティーズ-歴史学』佐藤卓己(岩波書店)
本書を読んで悲しくなった。この手の入門書は、著者が自分の読書歴にもとづいて書かれている。著者と同じ本や同種の本を読んだことのある者は、頷きながら、あるいは自分と違う読み方をしていると反発しながら、読み進める。しかし、本を読んでいない者は、この本に書かれていることの意味がわからない。本書で書かれている「パソコンを使う前にマニュアルを読むようなものだからである」。大学に入学してから読んだ本を訊ねると、授業で使った本しかあげない学生が読んでも、本書はわからない。だから、授業で使えない! 悲しい!
本シリーズ、ヒューマニティーズ全11冊は、哲学、歴史学、文学、教育学、法学、政治学、経済学、社会学、外国語学、女性学/男性学、古典を読む、からなる。明らかに社会科学に属するものが半数ある。「歴史学は科学か?」と問われた近代と違い、近代科学だけでは明らかにできない現代の諸問題に対処するためには、近代科学を超える意味での人文学humanities的知識が必要である。それは、本シリーズの各章の統一された副題からわかる。歴史学なら、「歴史学はどのように生れたのか」「歴史学を学ぶ意味とは何か」「歴史学は社会の役に立つのか」「歴史学の未来はどうなるのか」。
本書は、著者佐藤卓己の研究(読書)遍歴をたどりながら、「如何にしてメディア史研究者になったか」を語っている。著者の著書を読んでいれば、著者がどのような背景と意図をもって、それぞれの著書を書くにいたったかがわかっておもしろい。
著者は、「はじめに」で、まず「「歴史学」を書く資格が、私にあるだろうか」と問う。そして、大学の学部・大学院と史学科・西洋史学専攻に属しながら、専任教員として歴史学科に属したことがないからこそ、「本書の執筆を引き受けた」と答える。歴史学を主観的にしかとらえられない「歴史学者」に、本書は書けないのか。「書けない」とわたしも思う。
「「公共性の歴史学」に辿り着いた」著者は、つぎのように批判する。「歴史を学ぶ意味への問いを切実に感じるのは、歴史学科に所属する教員より、私のように社会学科や教育学部で歴史学を教えている教員だろう。歴史が好きで、それを学ぼうと志した学生が「何のための歴史的アプローチか」と問うことは少ないからである」。さらに、「日本では一九八〇年代以降ポストモダン思潮と並行した社会史ブームは、その唱道者の意図に反して、歴史学の印象を非政治的な雑学趣味にしてしまった感もある」、「「歴史は過去と現在との対話 」(E・H・カー)というフレーズは歴史家によって頻繁に引用されるが、その割にはあまり応用されていない」と手厳しい。
「歴史家とは通史を書くことだと思っている学生」や「歴史」を「歴史学より歴史物語、あるいは歴史教育の略語である」と思っている世間一般の人びとに、「歴史学」とはなにかを説明することは、それほど難しいことではない。著者のいうように「史料に基づき「ここまではわかった」「そこから先はわからない」と明言」すればいいからである。しかし、その具体例である専門論文や研究書を読んだことのない者に、説明してわかってもらうことは不可能である。せめて大学で歴史学を専門にしようとする者は、どの本が通史で、どの本が歴史小説で、どの本が歴史学の研究成果に基づいた一般教養書であるのかを区別できるだけの読書を、すくなくとも大学に入った日からしてほしい。
人文学は幅広い知識が必要で、本を読まない者が学ぶことができる学問ではない。ということは、本を読まない学生相手に人文学を教えること自体が、もはや無駄なことなのか。本書のような入門書の前に、学生に本を読む習慣をつける方法、あるいは本を読まない学生のための人文学の本が必要だ。情けない!