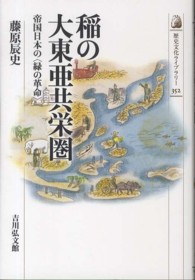『稲の大東亜共栄圏-帝国日本の<緑の革命>』藤原辰史(吉川弘文館)
いままでいちばんおいしかったコメは、フィリピン南部ミンダナオ島ダバオ市街地から少し内陸に入ったカリナンで食べた陸稲の赤米ジャバニカだ。日本人が普通に食べる白米ジャパニカより粒が大きく、香りとともにじっくり味わうことができた。1985年に調査のために下宿していた家の奥さんは、市場でちょっと変わったものがあると、買ってきて食べさせてくれた。たくさんの種類の地場もののコメやイモ、野菜があることがわかった。タイのバンコクのスーパーマーケットに行っても、いろいろなコメがあることに驚かされる。ジャスミンライス(香り米)として世界的に有名になった輸出用とは違い、人びとが食生活を楽しむためのコメがあるのだ。
本書では、ただたんに人びとから豊かな食生活を奪っただけではなく、「コメの品種改良の歴史にひそむ、「科学的征服」の野望」が語られている。裏表紙には、つぎのような本書の概略がある。「稲の品種改良を行ない、植民地での増産を推進した「帝国」日本。台湾・朝鮮などでの農学者の軌跡から、コメの新品種による植民地支配の実態の解明。現代の多国籍バイオ企業にも根づく生態学的帝国主義(エコロジカル・インペリアリズム)の歴史を、いま繙(ひもと)く。」
この概略を読まないで、帯に大書された「稲も亦(また) 大和民族なり」だけ見て読みはじめると、日本の稲作文化とそれを支えた農学者たちの礼賛の本ではないかと思ってしまう。著者、藤原辰史は、農学者たちの功績を認めつつ、それでも罪悪のほうがはるかに深刻で後世まで引きつづく問題を遺したことに鋭く切りこんでいく。そして、その功績は市場原理と結びついていったものであり、とくに自家消費用の在来米を栽培する人びとの生活を豊かにするものではなかったことを明らかにする。著者は、植民地産米の増産について、つぎのように述べている。「移出する側の植民地の農民は、良質(と内地の市場で評価される)品種を食べることはまれであり、在来の食味の悪い(と内地の市場で評価される)米や、粟(あわ)や黍(きび)を食べる。内地米は基本的に自給米ではなく商品であった」。
植民地台湾で導入された蓬莱米は、肥料を購入できる農家には歓迎されたが、「妻君」は「夫婦喧嘩をしてまで導入を拒んだ」。その理由を、著者は「三重の違和感があったのではないか」と述べ、「肥料依存型の農業構造のみならず、台湾の社会構造と心理構造をその両面からダイナミックに改変した」と指摘している。いったん導入され、肥料、農薬、水への依存度が高まると、収穫量が減る恐怖から抜け出すことができなくなる「薬物依存」と同じ状況に陥る。それを日本は朝鮮、台湾につづいて「大東亜戦争」で占領した東南アジアにも導入し、さらに戦後の「緑の革命」にも影響を与えることになった。
著者は、本書の基本的立場をつぎのように述べて、結論へと誘っている。「品種改良の政治的および社会的影響を、高橋[昇]や菅[洋]のように無害化することでもなく、山元[皓二]や高木[俊江]のように政治による科学技術の独占としてとらえることでもない。あるいは、盛永[俊太郎]のように発展史のなかに埋め込むのでもない。そうではなく、品種改良が編み出す技術的連関の網のなかで人びとが生き、生かされるという状況を記述することであった」。
そして、著者は「育種技術は「人を殺すこととまったく関係がない」」というきれい事は、「事実ではない」ときっぱり言い、最後の節「日本植民地育種の遺産」でつぎのように結論している。「育種技術が社会の矛盾を温存して人間と空間を人間の生活実感を通して支配するこのシステムは、警察権力や軍事力で人間を支配するよりもいっそう持続的で摩擦が少なく、それだけに、かえってとてつもなく厄介な統治システムでもある」。
そして、エピローグ「日本のエコロジカル・インペリアリズム」で、つぎのように警告する。「二一世紀の帝国主義が、国家の枠を超えて、遺伝子操作技術をはじめとするバイオ・テクノロジーによって人間と人間以外の生物を同時に支配するという、新しい段階に突入することは間近に迫っているように思われる。医薬品産業と種子産業はしばしば同一の企業に担われている。古い時代の偶然が新しい時代に必然になることで、歴史は進展してきたからである」。
わたしたちは、なんのためらいもなく日本のコメはおいしいと思い、その日本のコメを守り、広めていくことになんの疑問も思っていない。だから、それに真摯に取り組む農学者たちを立派な科学者として尊敬してきた。しかし、本書を読むと、日本のコメは戦前・戦中の帝国主義・植民地主義と深く結びつき、それが戦後のアメリカの食糧戦略にも結びついていったことがわかる。そして、「稲も亦 大和民族なり」というように民族文化と絡み、世界に誇ることができると思っているために、さらにやっかいである。すくなくとも、日本人の稲のもつ特殊性を理解したうえで、その神聖性は国内にとどめ、外国に押しつけることだけはやめた方がよさそうだ。