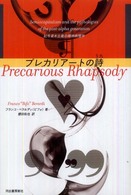『プレカリアートの詩---記号資本主義の精神病理学』フランコ・ベラルディ(ビフォ)、櫻田和也訳(河出書房新社)
ここ数年、ポスト・ネグリともいうべきイタリアの思想家たちの紹介が開始されている。パオロ・ヴィルノ、マウリツィオ・ラッツァラート、そして今回紹介するビフォは、ともにアウトノミア運動でネグリと戦列をともにし、いまもそれぞれのかたちで現場での実践と理論を切断させることなく活動してきた。しかし、その思考はまったくネグリ的とは言えないばかりか、ネグリに対して容赦のない批判が行われている。日本国内では、学術的にも運動的にもねじれた形で受容されているため、より状況は複雑なのだが、ネグリの「偉大さ」もかれらの営為との対照の中でこそ語られなければならないだろう。ビフォことフランコ・ベラルディはイタリアで活動後、フランスにわたりガタリとともに行動した。その軌跡はおりしも本書のすこし前に刊行されたフランソワ・ドスの『ドゥルーズとガタリ 交錯的評伝』からうかがうことができる。日本での最も初期のアウトノミア運動とその弾圧の紹介である粉川哲夫の「イタリアの熱い日々」(1979)にもその名前があるが、それから30年がたってようやく初の日本語の訳書が刊行されたという形になっている。訳者の櫻田は、社会学者であると共にメディア・アクティビストとして知られており、まさにビフォの導入にふさわしい。本書はビフォがアウトノミア運動を総括しつつ、そこから現代資本主義がもたらす病理をガタリ的に分裂分析したものと言えよう。論旨は多岐にわたるが、その要旨は次のようなものだ。アウトノミア運動は資本主義を先取りすることによってユートピア的な叛乱となったが、資本主義はユートピアを反転させたディストピアとして、その末期をあらわにしている。抑鬱はその結果であり、したがって鬱、ひきこもりなどで苦しむ人々はいわば「前衛」たちなのである。実際、存在論の究極がある無意味性だとして、それはまさにかれらによってこそ生きられているではないか。現在のすぐれたアートがすべてディストピアを表現するのはこれと同期しているのであり、コミュニズムもまたこの先にこそ展望されるだろう。
したがってビフォの基調はいたるところにコミュニズムを見いだすネグリ(ハート)のような明るさとは無縁であるが、だからこそ私たちはこれを信頼し得ると言えよう。この信こそドゥルーズのいう断片でしかなくなった「世界への信」であるのだ。こうしてビフォの思考と実践は、現代と格闘するアーティスト、他方で鬱、ひきこもりたちにも開かれたものとなる。そして、なにより新たなアナキズムを模索するアクティビストたちに限りない示唆を与えることとなるだろう。