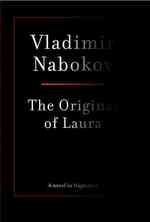『The Original of Laura』 Nobokov (Knopf)
没後32年目に出版されたナボコフの遺作で、「死は悦び」という副題がついている。ナボコフは未完の作品はすべて焼却するように遺言していたが、その遺言に逆らって出版したというので世界的なニュースになった。
ナボコフの未完の「長編」が出たのは文学的事件なので注文してみたが、届いたのは3cmくらいある分厚いハードカバーだった。こんな長い作品が眠っていたのかとわくわくしながらページを開いたところ、愕然とした。
"The Original of Laura"はインデックスカードという厚紙のカードに鉛筆書きされていたと伝えられているが、奇数ページの上半分にはカードの表側が写真版で、下半分には活字化されたテキストが印刷されている。偶数ページはカードの裏が同じ体裁でレイアウトされているが、裏面にまで文字が書かれているカードは数枚だけである。本の用紙自体もインデックスカードの厚さなので(カードの縁に沿ってミシン目がはいっていて、切りとれば元のカードが再現できるようになっている)、ぶ厚いといっても280ページほどしかない。インデックスカードは12行書けるようになっているが、それを活字化したテキストは8行で組まれている。普通の組み方をしたら50ページ足らずでおさまるだろう。
書き直しや綴りの間違いまでふくめてナボコフの肉筆を見ることができたし、凝った造本の割りには3000円そこそこだったので腹は立たなかったが、厚さが厚さだっただけにがっかりしたことは否めない。
50ページの分量しかないなら「長編」という報道は間違いだったのだろうか。
本書の刊行にあわせて『群像』11月号は「知られざるウラジミール・ナボコフ」という特集を組んだが、若島正氏は「私の消し方――『ローラのオリジナル』を読む」を寄稿し、本書が『透明な対象』と同じくアルファベットになぞらえた26章構成であること、『透明な対象』と共通する人物が複数登場すること、死にゆく意識をテーマとしていることから、両者をペアになる作品と推定している。この仮説が正しいなら、刊行された『ローラのオリジナル』はありうべき作品の1/4ほどの断片ということになる。わたしは若島説は説得力があると思う。この書き出しは『透明な対象』に匹敵する長編の冒頭にふさわしい。
さて、中味である。
物語は闇の中の声からはじまり、目が闇になれるようにしだいに状況があきらかになってくる。声の主の女はフローラといい、作家の妻。もう一人男がいて、彼も作家らしい。二人はパーティを抜けだして、束の間の情事を楽しんでいる。かなりあけすけな描写である。
第二章以降はフローラの生い立ちに飛ぶ。フローラの祖父は1920年にモスクワからニューヨークに亡命したロシア人画家で、その息子でファッション・カメラマンのアダムと、バレリーナのランスカヤの間にできたのがフローラだ。父アダムには少年愛の癖があったが、愛した少年たちが殺しあいをしたのを気に病んだのか、ピストル自殺してしまう。彼は自殺の瞬間を自動シャッターで撮影したが、未亡人となった母はその写真を雑誌に売ってしまい、その金でパリに住居を確保する。
フローラの母はバレエ教師として成功するが、フローラが12歳の時、ヒューバート・ヒューバート(!)という男があらわれる。彼は母とねんごろになるが、本当の狙いはフローラにあり、ある夜、フローラが38度の熱を出し、母が薬屋にアスピリンを買いに行っている隙にイタズラしてくるが、彼女はすんでのところで股間を蹴りあげ身を守る。
フローラは14歳の時、滞在先のホテルでテニスの球拾いをやっている少年と初体験をすませる。彼女は彼の性器を冷静に観察する一方、唇へのキスは許さない。セックスへの好奇心から身をまかせたにすぎず、ロリータとそっくりの経歴である。
この後、大学時代に話が飛び、フランス語とロシア語の授業で一緒になった日本人の娘から左手に文字を書きつけるというカンニングの技を伝授される(肌に文字を書くことと日本人が教えるというのは「耳なし芳一」からの連想だろうか)。
小説の態をなしているのはこのあたりまでで、残りは断片や創作ノートの類だ。冒頭でフローラと交わっていた作家は彼女をモデルに『ローラ』という小説を書き、ベストセラーになるという展開らしい。『ローラのオリジナル』という題名はここから来ているが、フローラの生い立ちを描いた部分とどうつながるかはわからない。
フローラを描いた条はナボコフの香りがたしかにするけれども、それだけだったら遺言に逆らってまで出版するほどの価値はなかっただろう。本書で一番興味深いのは創作ノートの部分だった。仏教のニルヴァーナの思想についてのメモや自我の消滅といった文言が書かれており、われわれが知っていると思っていたのとは別のナボコフが顔をのぞかせている。瞑想修行を思わせる記述もある。本書の副題になっている「死は悦び」も死後の世界や仏教への関心が背景にあるらしい。
死後の世界への言及は『青白い炎』などにも出てきたが、狂人の戯言のような形で相対化されていた。ナボコフと仏教などというと大方の読者は眉に唾をつけることだろう。ところが現在のナボコフ研究はどうもそちらの方向に向かっているらしいのだ。
ナボコフの伝記の決定版の著者であり、ナボコフ研究の第一人者であるブライアン・ボイド氏が『群像』の特集に「ナボコフの遺産」という文章を寄せているが、そこにはこう書かれている。
一九七八年にヴェラナボコフが書き記したナボコフの中心的なテーマは「異界」だというよく引用されるコメントとは別に、私はナボコフの形而上学への傾倒、とりわけ死後の世界があるとしたらどのようなものかという、思考実験と小説上の探求についての研究にも手を伸ばしていた。私はナボコフの中心的なテーマは、自伝『記憶よ、語れ』で述べられているように、心理的、認知論的、倫理的、形而上学的なものまでふくむ、宇宙における意識の位置だと一貫して考えてきた。死の先にある形而上学的存在の可能性への生き生きとしたナボコフの関心は一九七〇年代の終わりまでかろうじて認められ、十分に、たぶん十分すぎるほど、ここ三十年にわたるナボコフ研究の中で解明されてきた。
ボイド氏は1986年にヴェラ夫人から許可をもらい『ローラのオリジナル』を読んでいたということだが、なるほど、こういうわけだったのだ。