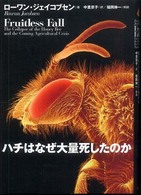『安部公房の“戦後”植民地経験と初期テクストをめぐって』 呉美姃 (クレイン)
韓国人の安部公房研究者が東大に提出した博士論文をもとにした本である。鳥羽耕史氏の『運動体・安部公房』の二年半後に出た本であるが、『終りし道の標に』から『砂の女』までとあつかっている時代が重なっているだけでなく、政治運動と安部公房という視点を共有しており、鳥羽の論の強い影響下に書かれたといって差し支えないだろう。
しかし重なっている部分が多いだけに、相違点も際立っている。鳥羽が1950年代の安部にポストモダンの大波に洗われ、脱政治が当たり前になっている現代日本の先駆を見ているのに対し、呉は植民地生まれの愚直なコミュニストとしての安部公房像にこだわっているのだ。
鳥羽は文化人類学的で人形劇を思わせる『飢餓同盟』をとりあげる一方、滿洲を舞台にした『けものたちは故郷をめざす』を等閑に付したが、呉は逆に『飢餓同盟』を無視し『けものたち』に一章をさいている。「引き揚げの過程で接する他民族への眼差しの変化
」が他の引き揚げものの小説とは一線を画していると考えるからである。
「壁」の読解も対照的だ。鳥羽は柄谷行人的な『資本論』読解を「壁」に読みこんだが、呉は名刺の「戦時中、反抗できぬ弱虫はただ発狂することをねがった。……中略……そのじめじめした願望を現実にして奴等にたたき返し、うんと言わしてやるのがおれたちの復讐なんだ
」という台詞に着目し、こう書いている。
名刺が「ぼく」に復讐を試みた理由は、人間「ぼく」の愚かさにあった。カルマ、すなわち<罪業>は、戦争に抵抗できなかった「ぼく」の無力さを指している。「ぼく」から名前が逃げた原因は「デンドロカカリヤ」の「コモン君」と同じく<戦争>の記憶にあったのである。したがって、名前と実体の分離という変形は、戦争のトラウマが露呈した形にほかならない。主体として行動できなかった「ぼく」の愚かさは自らを客体化してしまい、その結果、名刺との分裂に羞恥心と虚脱感を感じるほかなくなってしまうのである。
知識人の戦争に対する悔恨と自責が名前と実体を分離させたとというわけだ。こういう生真面目な読み方はそれなりに説得力がある。
とはいえ天皇制に対する諷刺とまで言ってしまうとどうだろうか。
語り手はカルマの名前を消して病院で「十五番」という名を与える。これも敗戦に対する寓意であるが、名前もない存在としてのカルマの羞恥、屈辱は敗戦が招いたことである。アメリカに占領され、<occupied in Japan>になった名前のない被占領状態の日本が否応もなく浮上するのである。さらに名前を失ったカルマをY子が三回も「人間あひる」として戯画化しているにも、極めて暗示的で、それは「人間宣言」によって戦後も存続しえた天皇制への諷刺としても読めるのである。
こういう読み方はさすがに無茶だろう。
『東欧を行く』に対する視点の違いも興味深い。鳥羽は安部公房が東欧の民族間の対立にこの時点で気づいており、国家の間の境界=対立ではなく民族集団の間の境界=対立を「国境病」と呼んでいること、社会主義国にも矛盾があるが、その矛盾を「プラスの矛盾」と言い換えて擁護していることを指摘する。一方、呉は植民地と本土の対立や滿洲の民族問題には鋭敏な反応を見せていたのに、安部が東欧で見てとった民族間の対立はなぜか無視し、チェコの共産党には「民主主義」があるという言葉にだけ反応している。安部がさまざまな社会主義的矛盾を指摘していると抽象的に書くだけで、その矛盾の重要なものが民族間の矛盾だということまでは触れていない。東欧旅行後の日本共産党批判にいたる過程となると鳥羽の論の方がはるかに説得力がある。なぜ急に読み方が浅くなってしまったのか、不可解である。
しかし一番違うのは『砂の女』の評価である。主人公が監視を解かれたにもかかわらず逃亡をあきらめる結末をコミュニズムからの離脱と解釈する点では両者ともに軌を一にしているが、鳥羽はそれを「自らを密室のなかへと幽閉していく志向」として現在のオタク文化の先駆のようにとらえているのに対し、呉は「個人的<主体>への源泉回帰」、「平常時における闘いのあり方」と社会に対する主体的な係わりとして評価している。まさに真逆である。
こういう論の構えだと『砂の女』の結末の評価は運動をやめた後の安部公房をどう評価するかという問題に直結するが、『砂の女』の読み方はそれだけだろうか。