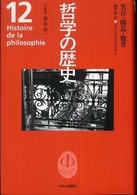『<small>哲学の歴史 12</small> 実存・構造・他者』 鷲田清一編 (中央公論新社)
中公版『哲学の歴史』の第12巻である。このシリーズは通史だが各巻とも単独の本として読むことができるし、ゆるい論集なので興味のある章だけ読むのでもかまわないだろう。
20世紀の三冊目でフランス語圏の哲学をあつかう。副題の「実存・構造・他者」のうち「実存」と「構造」があげられるのは当然だろう。第二次大戦後、フランスの哲学は世界中を席巻するが、1960年を境にそれ以前が実存主義、それ以降が構造主義とはっきりわかれるのである。
その意味で本巻がベルクソンからはじまっているのは意義深い。第二次大戦前のフランス哲学といえばベルクソニスムをさしたが、スピリッチュアリスムとは別の流れということになってはいても、時間がたってみるとやはり一つの伝統に棹さしていたからだ。
なお本題とは関係ないが、本巻を読んでいて第一次大戦前後に父親を亡くした哲学者がすくなくないことに驚いた。しかも戦死ということだけしかわかっていないリクールを除くと、あとはいずれも海軍士官なのである。サルトル、メルロ=ポンティ、アンリ、そして本書では無視されているが、ロラン・バルトもそうだ。第一次大戦の戦死者は陸軍の方がはるかに多かったと思うが、フランスの哲学者の多くはなぜか海軍士官の遺児だったのである。単なる偶然の一致だろうか。
「総論 モダンとポストモダン」 篠原資明
本シリーズの総論は編者自身が書いているが、本巻だけは鷲田清一氏ではなく篠原資明氏が担当している。篠原氏はベルクソンとドゥルーズに関する著作で知られているが、本章もベルクソンからメルロ=ポンティ、さらにドゥルーズへ向かう流れを縦軸として20世紀フランス哲学をまとめている。
ベルクソン、メルロ=ポンティ、ドゥルーズと並べればベルクソニスム、実存主義、構造主義(とポスト構造主義)という三つの時代区分がすべておさまり、伝統的なスピリッチュアリスムとの連結もはっきりするが、このようにまとめてしまうとドイツ哲学が現代フランス思想におよぼした圧倒的な影響が見えにくくなってしまう。
おそらくその点を考慮したのだろう、本書の真ん中あたりに「自由への横断――ライン川を越えて」という小林康夫氏のコラムがあり、総論とこのコラムをあわせ読むことで20世紀フランス哲学が立体的に見えてくるのである。
「Ⅰ ベルクソン」 檜垣立哉
第二次大戦前はベルクソン=フランス現代哲学だったが、実存主義の時代になるとすっかり忘れられてしまい、科学哲学としてのみかろうじて名前が残っていた。ベルクソンと科学哲学というと意外に思うだろうが、澤瀉久敬という人が生命科学の批判論として、今にして思えばかなり的外れな持ちあげ方をしてくれたおかげで関心がつづいていたのである(わたしが学生時代の頃だ)。
ところがポスト構造主義の時代になりドゥルーズが差異の哲学の原点としてベルクソンを評価していて、『ベルクソンの哲学』というすこぶる刺激的な本まで書いていることがわかって再び注目されるようになった。
本章はドゥルーズ的に強引に再編成されたベルクソンではなく、発展の順序を追ったオーソドックスな紹介であり、メルロ=ポンティやミンコフスキー、アンリに継承されたものまで視野におさめている。刺激は感じないが無難に読める章である。
「Ⅱ 反省哲学」 越門勝彦
フランス反省哲学といっても知っている人はすくないだろう(わたしは本書ではじめて知った)。本章を担当している越門氏もこれといった著作がないので「非常にマイナーな思潮」と認めている。しかしリクールに決定的な影響をあたえるなど、その影響は思いのほか広く深く、フランス哲学の重要な流れなのだそうである。
反省哲学というと内観主義のような印象を受けるが、代表者の一人であるナベールの定義によると「つねに精神をその作用ならびにその産出物において考察する」ことである。精神の「産出物」とは行動であり、行動を精神の記号と見なして両者の関係を意味作用と規定するというから、同時代のプラグマティズム、特にパースの思想と共通する部分が多いという印象を受ける。