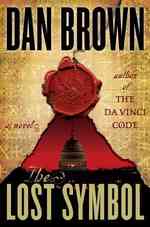『極北へ』ジョージーナ・ハーディング(新潮社)
北極海で越冬した男が到達した境地
知らない作家の小説を手にとるとき、作家のプロフィールが読み出すきっかけになることがある。若いときから創作一筋という人より、いろいろな道を経て書くことにたどりついた人のものに惹かれる場合が多い。
人の人生に寄り道はなくて、いろいろな道が交錯して、いまの自分を誘導している。それらが別の次元に引き上げられるとき、小説という器がリアリティーを持ってくる。生まれ落ちた作品は、従来の小説とは少しちがった視点に満ちているのだ。
『極北で』を手にしたきかっけも、同様だった。本のタイトルでも、「1616年、北極海。たったひとりの越冬」というキャッチフレーズでも、装丁でもなく、ジョージーナ・ハーディングという女性作家の略歴に興味をもった。
1955年、英国生まれ、ロンドンの出版界で働き、80年に来日、東京で編集の仕事に携わった後、アジア各地、ヨーロッパ大陸を旅してまわった、とある。これまで、チャウシェスク政権下のルーマニア紀行、子連れのインド生活体験記などを書いており、本書ではじめて小説作品に取り組んだ。予想は外れていなかった。洞察力のある緻密な筆致に魅了され、一気に読了した。
北極海に捕鯨にきたイギリス男たちが賭けを思いつく。グリーンランドの地図にも出てないような小さな島にひとりの男が残り、彼が翌年まで生きていられるかどうかに金を賭けたのだった。男はトマス・ケイヴといい、だれに説得されたわけでもなく、自らの意志で捕鯨基地に留まった。
外では動物を狩り、室内では靴の踵を作る(義父から靴作りの技術を伝授されていた)単調で規律ある暮らしを、彼は克明な日誌に付ける。強い自制心と計画性のもとに、厳しいながらも淡々と日常が進んでいく。
捕鯨船が残していった食糧があるので、充分ではないものの、一応食べ物はある。寝るところも倉庫兼作業場だったテントの内側に、仲間が作った木の小部屋があり、ストーブで暖まることもできる。無人島と言えども、完全に文明から切り離された環境ではない(そもそもそのような状況下での越冬は不可能だろう)。本書が描きだすのは、最低限のもので生き延びようとする男の精神面だ。それが想像力豊かに描かれる。
賭け事の発端は、ひとりの航海士がケイヴと言い争ったことだった。どんな男でも一冬ここに残されたら、寒さと光の乏しさで気が変になり、壊血病と飢えで死んでしまうと航海士は言い、ケイヴはそれに反発し、迷信に惑わされない分別と理性を備え、神の助けとちょっとした運があれば生き延びられると主張した。「ならおまえがやってみろ」と言われ、受けて立ったのだった。
ケイヴを苦しめたのは、寒さや孤独などの具体的な理由よりも、記憶の重みだった。彼は最愛の妻を出産で亡くしていた。出会い、一緒になり、子供の誕生を待つまでの甘美な記憶、それとは裏腹の出産時に妻を襲ったおぞましい苦しみとその果ての死。それらが激しくよみがえり、ついには彼女の幻影が目の前に立つようになる。
彼は神にこう祈る。
「もう、夢も、亡霊も、迷妄もたくさんです。目の前にあるのは、理性でわかるもの、物質界の確かな証拠だけでありますように。生き延びることだけに専念していられますように。灰は灰に、氷は氷に」
四月になっても陽が射さず、何ひとつ希望が感じられない日々がつづく。ついに太陽の位置が高くなり、雪解けがはじまると、雪の下から茶色い汚れた世界、捕鯨基地の残骸が現れる。水を含んで軟らかくなった雪には赤い染みが現れ、広がってゆく。
最後の章では国にもどったケイヴが描かれるが、彼は先に挙げた神への祈りどおりを生きている。自分の心に生じる妄想も、まわりからおしつけられる噂や迷信も退けて、物質界の確かな証拠だけを見つめる徹底した観察者になるのだ。
人は現実にはないものを心に描こうとする。夢や希望も、その反対の迷信や幻も、心の働きとしては同じものだ。ひるがえって動物は生き延びることに専心し、目の前の獲物だけを捕ろうとする。食べる分を得られれば充分で、それ以上の希望も恐怖も持たない。
希望にすがって生きることが人間の弱さであり、不完全さなのだろうか。希望とは、恐怖が形を変えて現れたものに過ぎないのだろうか。
人間の営みの歴史を振り返ってみると、たしかにそう感じられることがある。飢える恐怖が人に蓄えさせてきた。蓄えるうちに、それ自身が希望に転じてきた。瞬間を生きるだけならば、全身でそれに邁進するならば、「希望」という概念が入り込む予知はないだろう。
よく知られるように、西洋の捕鯨は鯨油の採取が目的で、肉には関心がなかった。油を採るためだけに船団が北極海に繰り出し、雪原を赤く染めていった。その油が原動力になって産業革命が達成されたのである。
思えばすごいことをしてきたものだが、それらの行為を支えるものとして、「希望」という概念があったことは否定しようがない。よりよい未来を夢みて励み、忍耐してきたのが、人類のこれまでの歩みなのだ。
書き初めや卒業アルバムに幾度となく書かれてきた「希望」の二文字。その本当の意味は何なのだろうと考え込んでいる。