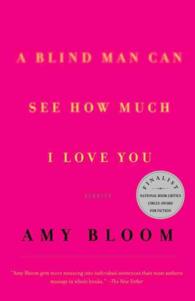『爪と目』藤野可織(新潮社)
「「あなた」とは何者か?」
小説の最初の一行は重要である。即座に二行目に目が移るような自然な書き出しにするか。それとも考え込ませるようなフックをつけるか。『爪と目』は後者の典型だろう。このようにはじまる。
「はじめてあなたと関係を持った日、帰り際になって父は「きみとは結婚できない」と言った。」
読み進めば「あなた」と「父」の関係がわかってくる。だが、この一行に遭遇したときの最初の奇妙さはいつまでも消えない。途中で何度も「あなた」ってだれだっけ?と問い返さずにいられなかった。私の頭の働きが鈍かったり、血縁関係を把握するのが苦手だったりするせいだろうか。
読み終えたいま、どうやらそうではないらしいと気づく。従来の人称とは意味するものがちがうのだ。それがボデイーブローのようにきいて三半規管をおかしくする。小説という形式への新しい挑戦である。
語り手はだれか。「あなた」と関係をもつことになった相手を「父」と呼ぶ立場にある人である。すなわち「わたし」である。「父」の前に「わたしの」が略されている。ほかの人の父なら、「一郎の父」というように父の前に名を冠するはずで、なにもなければ必然的に「わたし」の父となる。それならば、「わたし」と「あなた」はどのような関係にあるのか……。一行目から迷宮に引き込まれるような感覚になる。
説明すれば簡単なことだ。「父」は前妻が亡くなったあとに当時三歳だった「わたし」を連れて「あなた」と再婚した。つまり「あなた」と「わたし」は義母と娘という関係だ。小説は「父」と「あなた」の出会いや、一緒に暮らすことになった「あなた」と「わたし」の関係などを、人物の内面に立ち入らずに表面的な動きだけを写実していく。語り手は三歳から大人になった「わたし」だが、ふつうなら知るはずがないような「父」と「あなた」とのやりとりのディテールやひだを知り尽くしている。
たとえば冒頭の文章のあとはこのようにつづく。
「あなたは驚いて「はあ」と返した。父は心底すまなそうに、自分には妻子がいることを明かした。あなたはまた「はあ」と言った。そんなことはあなたにはどうでもいいことだった。ちょうど、睫毛から落ちたマスカラの粉が目に入り込み、コンタクトレンズに接触したところだった。あなたはぐっとまぶたに力を入れて目を見開いてから、うつむいて何度もまばたきをした」
語り手が第三者ならば通常の形式の範囲内である。だが、「あなた」にとって義理の娘である「わたし」が、これほど物事の詳細を明らかにすることは、これまでの小説ではあまり例がないのではないか。論理的におかしいと言う人もいるかもしれない。ところが、読んでいるとそうは感じないどころか、頭が辻褄あわせに興味を失い、ただ語りの力に引っ張られていく。
小説のなかに「父」がでてくれば、ふつうは「わたし」との関係がどのようなものであるかが明らかにされる。そのために「父」という言葉が使われると言ってもよい。少なくとも従来の小説ではそうだった(と思う)。「母」にしてもしかり。ところが、この作品の「父」や「母」は戸籍上の記号のように無機質で、「父」に父らしい振る舞いはなく、「母」には母らしい感情が欠け、夫婦同士にもその子供にも密接な結びつきがない。
語り手の「わたし」の「あなた」への呼びかけもまた形式的なものだ。「あなた」と「わたし」という人称は、英語のyou & Iのように、対峙する関係を強調するのに有効だが、この小説ではそのような使い方はされていない。
ここに描かれる「わたし」の実存には、「わたし」という一人称が本来もつべき自我が希薄なのだ。「父」や「母」も、そのように呼ばれる役割への認識が欠けている。相手と向きあい、関係を担うという意志や、相手を対象化し、自分を客体化するという視点が、だれからも欠落している。
それならば彼らは何よって行動しているのか。物事への反応、判断や思考を介さないリアクションである。「父」は後妻である「あなた」との性交がうまくいかず、自分の能力を確かめるためにほかの女性と寝る。「あなた」は押し入れの本を処分するのに呼んだ古本屋と関係する。または生前に前妻が書いていたブログを見つけて熱中する。
反応体と化した人間の姿を、「父」「母」「わたし」「あなた」という、本来なら関係をベースとした呼び名や人称を使って淡々と描いていく。このねじれこそがこの小説の新しさだ。読んでいると三半規管がおかしくなる原因もそこにある。
ここに登場する「あなた」と「わたし」は、自我を根拠とした一人称と二人称とは異なる、新種の「あなた」や「わたし」である。「わたし」が呼びかけている「あなた」は、「わたし」の相手としての「あなた」ではなく、だれでもなくて同時にだれでもあるような「あなた」だ。おなじように「わたし」は唯一無二の「わたし」ではなく、どこにでもいて、だれでもありうる「わたし」なのである。
特定の個人に光を当てたり、その心の内側を明らかするという意図で書かれてないためか、神話の語りにちかいような印象がある。とはいっても従来のように上空から見下ろす神の視線ではなく、反応体と化した人間のディテールをからだの反応に沿って語るという、新しいミッションをになった神=「わたし」の誕生である。
この小説でもうひとつ興味を引くのは視覚へのアプローチだ。見ること、見えることについての小説、とみなすことも可能で、『爪と目』という絶妙なタイトルもそのテーマと深く関わっている。それについては11月号の『新潮』に書く予定なので、そちらに場を譲ろう。