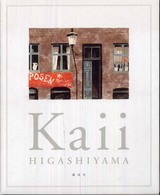『タイ 中進国の模索』末廣昭(岩波新書)
本書は、日本のタイ研究の高水準を示す誇るべき成果である。タイの現状を、これだけ詳細に深く、そしてわかりやすく書いたものは、タイ本国にもどこにもないだろう。本書のなかでは、ほかの日本人研究者によるいくつかの文献がしばしば参照されている。したがって、本書は著者個人の成果というより、これらの参照文献の著者たちとの共同研究の成果といってもいいだろう。そして、それらの共同研究をリードしたのが、著者の末廣昭であった。
2004-05年に、『戦争の記憶を歩く 東南アジアのいま』(岩波書店、2007年)を執筆するためにタイを広く歩いた。そのときは、2005年2月に実施された総選挙でタックシン首相率いる政党が全議席の75%を占める圧勝をしたように、素人目にはますます政権は安定するかにみえた。翌2006年9月にクーデタがおこり、あっけなく政権が崩壊するなどとは夢想だにしなかった。
著者は、本書執筆にあたって、いろいろ整理をしていることが、「はじめに」でわかる。まず、テレビ報道で映し出されるような「黄色のシャツ」と「赤色のシャツ」の対立というような単純なものではないことを、4つに分けて説明する(「第一に、国民の大多数は、「黄色のシャツ」であれ「赤色のシャツ」であれ、彼らのなりふりかまわない実力行使にうんざりしている」「第二に、「黄色のシャツ」を民主化の推進勢力と捉える議論には賛同できない」「第三に、「黄色のシャツ」(PAD)は王室擁護派、「赤色のシャツ」(UDD)は王室ないがしろ派と区分することもできない」「第四に、「黄色のシャツ」の活動を都市中間層、「赤色のシャツ」の活動を農村貧困層に代表させる見方にも疑問が残る」)。
つぎに、2つの切り口、2つの課題をあげる。2つの切り口とは「政治の民主化」と「タイの中進国化」で、キーワードとして「民主化、現代化、そして王制」を選んでいる。2つの課題とは、「ひとつは、民主主義をどのように発展させ、王制との調和をどのように図るのかという政治的な課題である。もうひとつは、グローバル化時代の世界にどのように対応するのか、いいかえれば、グローバル化の流れの中でどのように「タイらしさ」(Thainess)を維持するのかという経済社会的な課題である」。これら「二つの課題は将来のタイ社会をどのように構想するか、その違いによって、それぞれいくつかの選択肢に分けることができる」という。
本書は、前著『タイ 開発と民主主義』(岩波新書、1993年)の続編にあたるため、1992年から再開するのが筋であるが、著者はつぎの2つの理由から1988年を起点とした。「第一の理由は、一九八八年がタイにとって経済ブームの出発の年になったことにもとづく。その後の経済拡大や社会変化はすべてここから始まった。経済拡大はバブルを引き起こし、バブルの崩壊は通貨危機に発展する。そして、この通貨危機が、一方では「国の開発」より「国民の幸福」を重視する開発計画の転機となり、他方ではタックシン首相の「国の改造」の発想の源となった」。「第二の理由は、一九八八年が政党政治の本格的な開始年になったことによる。ただし、政党政治の開始は政治の腐敗のさらなる増殖でもあった。そのため、クーデタが勃発し、五月流血事件、憲法改正運動をへて、一九九七年憲法へと帰結する。ところが、「人民の憲法」と賞賛されたこの憲法は、タックシンという「強い首相」を創り出した。そして、二〇〇六年のクーデタ以後の政治は、タックシン体制の根絶か、それともその復活かを軸に、先行き不透明な政治抗争を繰り返している」。
この政治抗争の根源は、2009年3月末にタックシン元首相が支持者の集会で、ビデオを通じて述べた「今回のクーデタの首謀者はプレーム枢密院議長とスラユット枢密顧問官である」という爆弾声明につきるかもしれない。王室に絶大なる影響力をもつこれら2人を中心とする勢力が、反タックシン運動の黒幕だというのだ。しかし、著者は、そのような表面的な対立構造だけではなく、タイの基層社会・文化のなかで現在の状況を理解しようとし、タイの現状をつぎのように総括している。「「黄色のシャツ」と「赤色のシャツ」の衝突は、一面ではタックシン元首相の政界復帰をめぐる対立の側面をもっているものの、両者が過激な実力行使に走る背景には、間違いなくタイ経済の悪化、失業者の増加、将来への見通しへの不安が存在した。経済の不安定が政治の不安定を増幅させ、政治の不安定が経済の建て直しの足をひっぱるという悪循環に、タイは陥っている」。
著者は、今後の大きな課題として「王位の継承と今後の王制の在り方」をあげ、終章を「タイ社会と王制の未来」とした。日本の皇室とは違い、タイの王室は社会に影響を与えうるだけの内帑金(君主の所有に属する財貨)をもって経済開発や社会福祉事業などを行っている。日本の皇室やイギリスなどのヨーロッパの王室がおこなう政府とは別次元の外交などと違い、政府の政策と矛盾し対立することもある。今日の混乱の原因のひとつは、タックシンの「国の改造」政策が王室が目指した「足るを知る経済」と衝突したためである。そして、著者は、つぎのようにこの終章をむすんでいる。「結局のところ、中進国タイには二つの道があると言ったが、ありうる選択は「現代化への道」と「社会的公正の道」を折衷したものに行き着く。ただし、それは時代の流れに柔軟に対応し、バランス感覚を大切にするタイのひとびとにとっては、もっとも現実的な道と思えるが、どうであろうか」。
たしかに、この20年間にタイ社会を取り巻く環境は大きな変貌を遂げた。にもかかわらず著者は、前著と同じくつねに「タイらしさ(Thainess)」を考えながら、本書を書いている。読者であるわたしも、ぶれない視点で本書を読むことができ、数々の疑問が解けた。しかし、わかりにくいことも多々ある。空港を占拠したり国際会議を妨害したりしても、本気で再発を防ぐ方策はとられていないようにみえる。しばしば変わる憲法に基づいた憲法裁判所による、もっともとも思えないような理由での首相解任や党の解散命令を、なぜ当事者たちがすんなり受け入れたのか。タイ人のいう「民主主義」とはどういうもので、あきらかに国益を損なうことがなぜ繰り返されるのか、そして「タイらしさ」とはなになのか。タイ人自身によるタイ研究の飛躍的な進歩に連動する日本人のタイ研究者の考察・分析に注目し、著者のいう3つのキーワード「民主化、現代化、そして王制」とともに、今後のタイの情勢をみていきたい。タイ人が微笑みを取り戻すことを願いつつ・・・。
(ロンドン行きの飛行機のなかで本書を読みはじめ、時差ぼけで眠れない「早朝」に書評を書いた。)