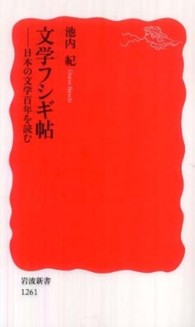『ロラン・バルト伝』 カルヴェ (みすず書房)
ロラン・バルトが亡くなって10年後に出た初の本格的な伝記である。
力作といっていいと思うが、「作家の死」を提唱した文学理論家に普通の伝記を書いてしまったために(伝記素がどうのこうのと能書を書いているが、結局は物語風の伝記になっている)、笑いものにされこそすれ評価されることのなかった本である。ある意味気の毒な本といえる。
著者のルイ=ジャン・カルヴェは社会言語学者で、伝記は本書が第一作となるが、その後シャンソン歌手のジョルジュ・ブラッサンスの伝記も書いているとのこと。
どれだけ意味があるかは疑問だが、新事実がいろいろ書いてある。その中で重要と思われるのは戦死した父親が職業軍人ではなかったことだろうか。
バルトの父のルイ・バルトは1916年10月北海の海戦で戦死した海軍士官と記されてきたが、もともとは民間の船乗りで、第一次大戦勃発とともに予備役海軍中尉として徴兵された。
ルイ・バルトが指揮していたのは小さなトロール漁船に57mm砲を一門とりつけただけの「哨戒艇」だった。海戦がはじまると艇はすぐに被弾し、バルト船長は致命傷を負った。漁船に砲弾があたったらひとたまりもない。
航海士の資格をとると海軍の予備役あつかいになる制度は戦前の日本にもあったらしいが、職業軍人と民間の航海士では遺族の「戦死」の受けとめ方はずいぶん違うだろう。『哲学の歴史12 実存・構造・他者』を読んでいて、第二次大戦後に活躍したフランスの哲学者に戦死した海軍将校の遺児が多いのが気になったが、海軍将校とはいってもバルトの父のように徴兵された民間の航海士が他にもいたかもしれない。
バルトは19才の時に喀血し、20代の8年間をサナトリウムですごすが、最初にはいったサン・ティレールの学生サナトリウムはグルノーブル大学附属で、グルノーブル大学の教師が出張講義をおこなっていた。バルトはこのサナトリウムでエリアス・カネッティの弟のジョルジュと知りあっている。
フランス人には自明のことかもしれないが、外国人にはわかりにくいキャリア形成や出版事情についての記述もある。日仏学院のようにフランス政府が外国に設けたフランス語教育施設が若い知識人の受皿となっていて、結核によってアカデミックな経歴をいったんはあきらめたバルトは外務省の嘱託としてブカレストのフランス学院に赴任する。役職は図書係だったが、シャンソンをテーマとした連続講演をおこない好評を博す。
カルヴェは一般の聴衆を相手にした講演にとりくんだことが後年のバルトのスタイルを決定したとしている。
博識を通俗解説に盛り込み、学問的でありながら一般大衆にもわかるように話すことによって、彼はそれと知らずに一つのスタイルを試していたのだ。それはのちに『神話作用』で用いることになるスタイルであり、自分が話しているその場から生まれるスタイルである。大学で教えていたとしたら、他の形を採らざるをえなかったろうし、大学の古典的な言説の鋳型にはまらざるをえなかっただろうが、ここでは、この学院では、教養はあるが専門的ではないそうした聴衆を前にして、彼はのちに自分の書き方となるものを、しゃべることによって作り上げていたのだ。
ルーマニア革命によってブカレストのフランス学院は閉鎖される。バルトは失業を心配するが、スタッフの多くはアレクサンドリアのフランス学院にまわされる。バルトはそこで後に構造意味論の大家となるグレマスと知りあう。グレマスはソシュールを教えてくれただけでなく、語彙論研究者のジョルジュ・マトレを紹介してくれる。バルトはマトレを介してアカデミックな経歴の端緒をつかむのだから万事塞翁が馬である。
本書で描きだされるバルトは弱く傷つきやすい。結核の療養のためにエコール・ノルマルを受験できなかっただけでなく、
「わかるだろ、ぼくが書くものは遊戯的だから、攻撃されると何もかもなくなってしまうんだ……」と彼はフィリップ・ルベロールに説明している。同じ頃、アラン・ロブ=グリエが語っているところによれば、バルトは「ピカールの非難によって極端に動揺していた(……)。古いソルボンヌの怒り狂った視線が、とつぜん、憎しみと恐れの入り混じった複雑な感情で彼を震え上がらせたのだ」という。フィリップ・ソレルスの記憶によれば、バルトは「ピカール万歳」というあのほとんど全員の叫びを前にして、ひどく傷つき、苦い思いをしていた。彼は敵意を示す社会に対してよろいもなく、無防備な自分を見出したのだ。
『批評と真実』の颯爽とした反論と、その後に勝ちえた世界的な名声からすると意外な印象を受けるが、よくよく考えればその通りだったろう。
本書が描きだすバルトは勤勉というかマメである。勤勉さやマメさは後期のバルトからはもっとも遠い特質に思えるが、国立科学研究センターで最初にえた語彙論の研究員というポストは国立図書館で1830年代の商取引に関する文献を調査し、資料カードを作成するというもので、勤勉でなければつとまらない。
勤勉さ自体はサナトリウム時代から発揮していた。バルトはミシュレ全集からの書き抜きを資料カードでおこなっていたが(10年以上後、最高傑作『ミシュレ』として結実する)、900枚を超えたところで資料カードの使い方が間違っていたと気づき、すべてのカードを正しい書き方で転記したというのだ。いくら時間がありあまっていたとはいえ、根がマメでないと到底できないだろう。
バルトはアカデミックな資格を学士号以外もっていなかった。
学位論文を書くということは、ある種の大学的な言葉遣いに自分を従わせるということである。それは人文科学の研究者たちにとって研究成果の発表を可能にするやや生彩のない手段としての言葉遣いである。ところが、彼はその好みからして、より型にはまっていない、より個人的な別の文体に向かわずにはいられない。おそらく彼は、この学位論文も、他の学位論文も、自分はついに仕上げることがないだろうと感じて、自分のそうしたやり方ないし無力さをすでに、作家と著作家という、その後有名になった区別によって理論化していたのだ。つまり、一方には、彼が退ける例の文体、エクリヴァンス(&eacc;crivance)があり、他方には、ある思想を伝えると同時に言説としての自己を問題にする例の言説、エクリチュール(&eacc;citure)がある、というわけである。
カルヴェの見方は説得力があると思う。『物の体系』でも通ったのだから、『モードの体系』が通らないはずはないと思うが、バルトには譲れない部分があったのだろう。