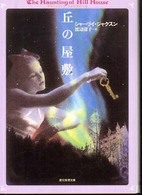『丘の屋敷』シャーリイ・ジャクスン(東京創元社)
「恐怖のありか」
ヒロインのエレーナ・ヴァンスは、青春時代のほとんどを、つねに不機嫌で病弱な母の介護に捧げ、「ぬぐいきれない無力感と終わりのない絶望感にじわじわと押さえ込まれてきた」。そして母の亡き後は、「この世でもっとも嫌っている」姉家族のもと、窮屈な暮らしを余儀なくされているうえ、ひとりの友達もないという孤独な女性である。
そんな彼女にとって、「丘の屋敷」への招待状は、自身では見当もつかずにいた「あたらしい人生」の門出を照らし出す一筋の光のごときものだった。
『丘の屋敷』の原題は"The Haunting of Hill House"、つまりそこは、これまで借り住んだ人たちのことごとくが、短期間で去っていってしまうという、いわくつきの屋敷である。
心霊学研究者のモンタギュー博士は、心霊現象の謎を学術的に解き明かすという野望をもって屋敷を借り、調査の助手として何人かの人間をそこに招いた。集まったのは、透視能力をもつセオドラ、屋敷の持ち主の甥であるルーク、そしてエレーナである。エレーナも、自宅の屋根に突然石が降ってくるという不可解な現象を子どものころに経験していた。
この手の小説を読み慣れていない私が本書を手に取ったのは、おなじシャーリイ・ジャクスンの『ずっとお城で暮らしてる』(市田泉訳、創元推理文庫)を読み、この作者に興味をもったためだが、「超自然的要素」を排した恐怖小説である『ずっとお城で暮らしてる』とはちがい、『丘の屋敷』は常識では考えられない現象がつぎつぎとおこる。
ある夏、モンタギュー博士をはじめとする四人の人間が、屋敷で経験するさまざまな「心霊現象」には、身の毛がよだつ、という譬えそのままの思いをさせられた。とはいえ、おそらく真の恐怖小説のほとんどがそうであるように、この小説のほんとうの怖さは、そうした怖ろしい現象そのものにあるわけではないだろう。
モンタギュー博士は、いわゆる「幽霊屋敷」という呼び方を嫌う。それは、このことばから人々に連想されるあらゆる現象と、それらへの先入観からなるべく自由であろうとする学術的見地のためだが、はたして、彼ら四人の経験した「現象」は本当に"Haunting"であったのかどうか。そうとしか思えない音や振動、大量の血、突然あらわれる壁の落書き……。すべては、何も起こっていなかったといえばそうとも思われる。ただひとつたしかなのは、彼ら四人と、読者のなかの恐怖だけなのではないか。
「幽霊屋敷もの」の古典と称される本書は、スティーブン・キングの『シャイニング』にも影響を与えたというが、ヒロインのエレーナ・ヴァンスの面影は、おなじキングの『キャリー』のヒロイン、狂信的な母親のもとで抑圧的に育った少女・キャリーとも重なる。
物語の冒頭、いかなる恐怖が待っているとも知らず、窮屈な暮らしを抜けだし、束の間の希望に胸を躍らせながら、屋敷へと車を走らせるエレーナはなにより印象的だ。結末に辿りついたとき、ふたたびその彼女のドライヴを思うと、屋敷での出来事が「心霊現象」であったのがどうかは、ますますつかみどころのないものに感じられ、そのことがなにより怖ろしいのである。