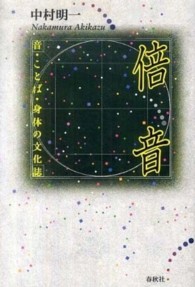『思い出を切りぬくとき』萩尾望都(河出文庫)
今年六十になる友人知人を思い浮かべてみる。彼らについていちどは、この人は萩尾望都と同い年、と思ったものである。自分がまだ二十代の頃は、二十一年長の人はとてつもなく大人にみえたもので、その頃から萩尾望都は私のなかではこの世代の代表だった。こちらももう四十となれば、その年の差もさほど気にならなくなっていて、親しみをもって語り合える人もおり、そこでふたたび彼らは萩尾望都と同年、と思うとやはりそこにはある種の感慨がある。萩尾望都が漫画家となって、今年で四十年だという。
その、四十年を記念して、と帯にはあるが、本書は七十年代半ばから八十年代半ばにかけて書かれたエッセイをまとめた単行本の文庫化であって、そこにいるのは二十代後半から三十代後半の作家である。このたびの文庫化にあたっての「まえがき」には、若書きの文章に対するテレをさらりと書きつけている著者であるが、その、そっけないくらい一文とともに、二十年以上もまえの自分を差し出している。エッセイの中身は過去なのに、そちらのほうが現在で、まえがきがまるで未来からの声のよう。なにやらSFめいている。彼女のことだから余計そんな気がするのかもしれない。
若かりし頃の自分の書いたものに対して、「若いというか物知らずというか幼いというかピリピリイライラしているというか、困ったもの」というけれど、書いた本人はともかくとして、読者にとって漫画家の年齢は感知の埒外にあるようなもので、だからこそ、還暦であるという事実に驚きもするのだが、二十代だろうと四十代だろうと六十代だろうと、やはり萩尾望都は萩尾望都なのである。シンプルでもったいぶりがなく、慎ましく爽やか、淡々としており、じっと目を凝らしてやっと、ひそかな情緒の揺れ動きが垣間見られる、といったふうで、これのどこが「ピリピリイライラ」だというのか。無垢と老成の同居したようなキャラクターを描いてきた人ならではの文章である。
それらが発表されたのは、新書館の『ペーパー・ムーン』や『グレープ・フルーツ』等、寺山修司の関わった雑誌のために書かれたもので、やはり寺山の編による同社のフォア・レディース・シリーズにも著書のある彼女は、同じシリーズ内でマンガとイラストレーションの投稿による本を寺山とともに作っている。寺山亡きあと、その告別式の日のことを書いた表題作では、最後に会った日を回想してこうつづける。
いろいろ、たあいない話をして別れた。まだ、いつでもあの続きを話すことが出来るような錯覚にとらわれる。寺山さんに、そのうちまたマドレーヌ菓子を焼いてさしあげますと約束をしていた。もう約束は破棄だという気持とこんどもっていこうという空想的な気持が半々である。実際に、寺山さんにとおみってもうお菓子は焼かないし、企画に寺山さんを、と、言い出すことはないだろう。
でも寺山さんがいないことを実感としてとらえられるのはもう少し先のことのような気がする。私にとっていつもこういうことは、とらえどころがないのだ。
感情をあらわにすることなく、しかし、人の死に触れたときの気持ちが正直な書かれてある。かなしむより、どう受け入れるかを思案している。それは彼女の作品に流れるなにかと繋がっているいきかただと思う。
解説のよしもとばなな氏も指摘しているが、そうしたなかでも、姉について書かれた部分だけは、ほかのものとは温度がちがうのが心に残る。とても世話焼きで親切な姉。人の好意を悪くとる者はその人の所為であるとまるで悪びれずに言い切る姉に、妹は抵抗する。
悪気じゃなくても、よかれと思っても、経過や結果が悪くでることもある。だから、困りもすれば悩みもする。それを、「ぜんぶ相手が悪いのよ」
単純にかたして自分の手を汚さないでいられるなら、こんな楽なことはない。だったら、いつも何をやっても自分は清く正しく美しくいられるってもんだ、他人が汚れていくばかりで。
あとがきで、人見知りをまったくしない子どもだった彼女は、無防備に他人になついては傷つき、それが怖くて用心深くなり、すると孤独になるのでまた人に近づく、この「無防備と用心深さの両極端をいったりきたり」していたと書く。不器用、といってしまえばそれまでだが、その率直さと性懲りのなさは神々しいばかりだ。これまで、彼女のマンガ作品から受けとってきたもののを、いまさらのように確認できた気持ちがする。