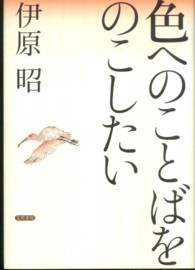『たのしい写真』ホンマタカシ(平凡社)
「ホンマタカシの新たなる意思表明」
1990年代後半にホンマタカシが登場したとき、写真界に新しい動きが出てきたのを感じた。それまでのカラー写真では、露出を半目盛り絞ってアンダー気味に撮るのが流行っていたが(代表的な例は藤原新也だ)、彼のカラー写真は色が薄くてオーバー気味で、露出操作を失敗した写真のように見えた。
撮るものも、ニュータウンの建物や、そこの住人が通うチェーンのレストランやハンバーガーショップなど、これまで写真家が目を向けてこなかったものが多く、写真界には当初、評価を保留するような雰囲気があったように思うが、1999年、郊外のシリーズで第24回木村伊兵衛賞を受賞すると、新世代を代表する存在として認知された、。
本書はその彼がはじめて写真について書いた本である。
プロの写真家が、アマチュア向けに写真の見方や撮り方を説いた本が、かつてよく出ていたが、その形式をならって「講義編」「ワークショップ編」「放課後編」「補習編」の4パートから成っている。パロディーはホンマの得意技だが、ガイドブックのような体裁をとりつつも、実は彼の写真観を表明しているところが興味深い。
特におもしろく読んだのは「講義編」である。今日の写真を考える上で重要な点として、「決定的瞬間」「ニューカラー」「ポストモダン」の3つを挙げている。
「決定的瞬間」とは言うまでもなく、アンリ・カルティエ=ブレッソンの著名な写真集(1952年)の邦題で、決定的な瞬間を逃さずに撮るのが写真の使命であるというように、写真のひとつの特質を代弁する言葉にもなった。
「ニューカラー」は1970年代に登場した動きで、自分たちを取り巻く世界を大型カメラで客観的にとらえようとした。カラー写真が中心だが、給水塔を撮ったベッヒャー夫妻のようにモノクロ写真も含まれる。代表選手には、南部のありきたりな日常風景を撮ったウィリアム・エグルストンが紹介されている。
「ポストモダン」は1990年代以降の動きで、状況を設定して撮るセットアップ写真の登場、ちいさな私的な物語へのこだわり、写真と美術の境界線があいまいになったことなどが特徴で、フィリップ・ロルカ・ディコルシア、ナン・ゴールディン、ヴォルフガング・ティルマンズなどの名前が挙がっている。
日本の写真家でページが割かれているのは中平卓馬だけで、ホンマが欧米の写真家の仕事を参照して、写真への理解を深めてきたことがうかがえるが、これらを潮流をカメラ機材と撮り方の問題に回収して語っているところが、いかにも彼らしい。「「決定的瞬間」と「ニューカラー」の最大の違いはシャッタースピードにあるのです」と言うとき、その当たり前の指摘にぽかんとなるのだ。
「決定的瞬間」では、小型カメラで動くものをとらえるので、シャッタースピードは速くなるが、「ニューカラー」では大型カメラを三脚に据えて撮ることが多いので、シャッターを好きなだけ長く開けておくことができる。同じ写真でも、そこに焼き付けられた時間は、一方は125分の1秒ほど、もう一方は何分にもわたるというふうに、大きな開きがあるのだ。
ものを長く見つめれば、より多くものもが見えてくる。反対に瞬間的に見れば、意識の網にかかったものだけが見える。どちらが正しいというのではなく、両者では視覚のメカニズムが異なってくる。このことに気付くと、小型カメラでスナップするか、大型カメラに三脚を付けて撮るかという選択に、意識的にならざるを得ないだろう。
「ポストモダン」の登場についても、彼らしい考察がなされていて、ターニングポイントのひとつは、1991年、ニューヨーク近代美術館の写真部長がジョン・シャーカフスキーからピーター・ガラシに替わったことだという。
91年、着任早々にガラシは「Pleasures and Terrors of Domestic Comfort」という展覧会を手がける。その展覧会カタログの表紙には、細部まで作り込んで構成したディコルシアのセットアップ写真が使われた。それまでにもこうした写真を撮る写真家はいたが、このガラシの展覧会によってセットアップ写真はポストモダンのメジャーな潮流として権威づけられた、と主張する。
ひとりの男の手がけた展覧会によって写真の流れが変わったというのは、身も蓋もない話だが、歴史の変遷には必ずそうした生々しい事実が付きものだし、表現者がそうした現実とまったく無関係ではいられないのもまた、事実である。現物を機械操作によってとらえる写真は、とくに時代の影響を受けやすい。
「講義編」の最後は、「スタイルチェンジ」という興味深い内容で締めくくられている。ロバート・フランクを取り上げ、彼の代表作である『アメリカ人』を振り返りながら、過去に無関心で、常に変わっていこうとする彼の姿勢を絶賛する。
「……ボクはどうしてもスタイルをチェンジした=転向した作家に惹かれてしまうのです。このことは趣味嗜好の問題です。どちらが良いとか悪いということではありません。ただ単純に、ボクの場合はどうしても変化の方が気になってしまうのです」
過去の作品を超えようとする意志を持つこと、自己再生産にノーと言うこと。フランクを引き合いに出しながら、ホンマはそう表明するのだが、これを読んで、『たのしい写真』とほぼ同時期に発表されたホンマの新しい写真集、『trails』を思い浮かべずにいられなかった。
『trails』を出したのはデザイナー町口覚のオフィス、マッチアンドカンパニー。取り次ぎを通さずに個人販売する版元の意気込みにも感服したが、20数ページの薄手の写真集に込められたホンマタカシの新たな挑戦にも、瞠目した。
雪の上に何か赤いものが落ちている写真ではじまる。私にはそれが赤い木の葉に見えた。よく見ると、かすかに赤いものが飛び散っており、見直すうちに別の想像が湧いたが、当初は紅葉した木の葉だと思った。
雪の降り積もる森のカットがつづく。雪上に生き物の足跡がある。樹皮の剥かれた木も見える。折り重なった枝のあいだには、さらにはっきりと赤い徴が落ちている。その徴は線となって川を越え、よろけながら丘の上に続いている。その徴をクローズアップした写真がつぎにつづく。引きと寄りとふたつのカットが並んでいる。ここにおいて赤いものの正体がはっきりする。獣の血なのだ。
撮影者の発見に、見る者の視線が刺激され、よりしっかり見ようと目を凝らす。現実の血痕を見ることと、それを写した写真を見ることは、別の次元に属するはずなのに、その差が消えてしまう。赤いものにそそぐホンマのまなざしに、自分の視線が重なり、たったいまそれが見えてきたような錯覚に陥る。
ホンマは「物語」を剥ごうとする意志の強い写真家である。つねに状況の外に立って、既成の価値観を離れて、出来るだけ公正にものを見ようとする。その視点が、『たのしい写真』をこれまでの指南書とはちがうものにしている。
だが、『trails』には、そのような物事の外側に立とうとするのとは、反対のベクトルが働いているように思われる。見えてしまっているものを観察するのではなく、何かが見えてくるのを待っているように感じる。
目を開いていれば、何がしかのものが網膜に映る。それはただ映っているにすぎず、見ているのとはちがう。ものは見ようとしなければ見えない、と言われる所以であり、これが視覚の働きの鉄則なのだが、『trails』を見ていると、これとはややちがうレベルのことが感じられてくる。
意志的に「見る」のと「見える」とのあいだにあるもの、と言ったらいいだろうか。両者をたゆたう何かが流れていて、赤い木の葉だという最初の誤解すらも、見ることのうちに含まれている、そんなことが不思議な余韻となって迫ってくる。