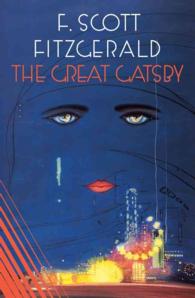『山田脩二 日本旅 1961ー2010』山田脩二(平凡社)
「時代を超越して写しだされたもの」
『日本村 1969ー79』という写真集を見たのは、1979年の出版時よりずっとあとのことだが、日本中をこんなにエネルギッシュに撮りまくっていた写真家がいたのかとびっくりした。しかも作者の山田脩二はそのときすでに職業写真家に「終止符宣言」をし、瓦職人に転じていた。のちに『カメラマンからカワラマン』という本が書かれる。人間的におもしろくて変わり種が多い写真家のなかでも突出した存在だ。彼がなぜカラワマンになったかも興味深いが、いまは写真の話のほうである。その後に撮り溜めたものも集めて、この度、『日本旅1961ー2010』という写真集を上梓した。
1961年、22歳のときに瀬戸内の四国側をまわったひと夏の旅の写真からはじまる。最初からものすごくうまいのに驚く。いや、「うまい」などという言葉は平板すぎる。写真では「うまい」と言うと、ただうまいだけでそれ以上のものが感じられないニュアンスがあって、褒め言葉にならない。山田の写真からは「うまい」を超えたものがほとばしり出ており、ただひたすら見ていたい気にさせられる。
よく知られる彼の写真に蝟集する人間を撮ったものがある。新宿西口広場の渦巻き型の道路を埋め尽くした1969年のフォークゲリラの群衆。船橋ヘルスセンターで何列にも並んだ長い座卓で飲み食いする客たち。豊島園のプールの水際ぎりぎりにまであふれかえった水着姿の男女。どの写真にも人が集合したり密着したときの熱やエネルギーが横溢する。撮影は素早いはずだ。被写体がもっともダイナミックに見える位置を直感的にとらえ、撮りたいものをど真ん中にすえてシャッターを切る。思い惑いは一切ない。そのストレートな一撃が、どんと胸を撃つ。
山田は60年代から70年代を通じて建築写真を撮っていた。建物の完成時に居抜きの状態でとる「竣工写真」ではなく、人と建物と環境の関係を探った独特の建築写真で評判をとった。彼の写真を見ていると、そうやって建築を相手に鍛えあげた「眼」を感じる。建築は大きくモノを見なければとらえられない面が多い。対象が人間より巨大だから当然そうなるのだ。もちろん、建物の構造や細部の仕上げや収まりなどを見せるタイプの写真も重要であろう。だがそうした情報性や資料性が主ではない、環境のなかの建築を体感させるような写真を撮ろうとすれば、物事を大づかみにする視線がなくてはならない。
ビルの胴体から地下鉄がぬっと現れる渋谷駅ビルを俯瞰で撮った写真、そのとなりページのビルの裏側に「女の座」という映画の文字看板がでかでかとかかっている写真。どちらもコンクリートの塊のようなビルの、ふてぶてしい存在感が迫ってくる。風景をわしづかみにしているような実に大胆な手つきだ。都市風景だけではなく、人を間近でとらえたものもすばらしい。そこでは写真家の眼は人間のしぐさに引き寄せられている。頭をかいたり、笑ったり、列を作ったり、荷物をしょったり、立ち話したり、ただぼうっと佇んだりと、五体の表現する人間らしさに魅せられているのだ。
蝟集する人間をよく撮っていると書いたが、ページを繰るうちに、モノが蝟集するさまにも惹かれているのに気がついた。焼き物の町、常滑の道角に集積する瓦やドカンや便器。登り窯の鱗のような屋根瓦。林立する煙突。窯にくべる薪の山。おなじ形状の繰り返しが生み出すパターンに本能的に引き寄せられている。私はそれらの写真に、のちにカワラマンとなる彼の宿命のようなものを感じとった。瓦への興味がそこに現れ出ていると言いたいのではない。モノを生みだす循環のエネルギーと、パターンの繰り返しがもたらす造形的なダイナミズム。そこに彼は生命のリズムに似たものを感じとっているように思えるのだ。
そう思い至って初期の写真にもどってみると、最初の旅ですでにそういうものに反応しているのに心づく。海に面した棚田には細かな曲線の繰り返しがあるし、自然石を積み上げた石垣にも連続の美がある。へらのように舳先の尖った手漕ぎ舟の居並ぶさまにも、屋根瓦をおさえている石の連なりにも、トタン屋根の波うつさまにも、海岸を埋め尽くす小石にも、繰り返しのおもしろさと、ロンドのようなリズムが脈打っているのである。
巻末の対談で篠山紀信は「写真ってさ、寝かすとすごいよくなっちゃうわけだよ」と述べている。たしかに写真には撮り手の意志を超えて時が醸してくれるよさがある。もうなくなってしまった風景、情景、人のたたずまいに再会するのは、写真にだけに可能な、人と記憶との不可思議な邂逅のときである。だが山田脩二の写真から私が受け取ったのは、そうした特性を超えた何ものかなのである。2005年に撮られた東京ビッグサイトのコミケの写真がある。会場にひしめき合う人、人、人。手前から奥の壁際までフロアを隙間なく人が埋め尽くしている。この光景には、船橋ヘルスセンターや新宿西口広場の写真に通じる生命の律動があり、その時代を超えたものに肉体が感応するのである。
2007年に撮られた六本木ヒルズの写真も同様だ。低いビル群からぬっと建ち上がるさまをバストアップで撮っている。背後に山並みが写っており、見たことのないような六本木ヒルズがあらわになっている。1970年の神戸商工貿易センタービルの写真に見たのとおなじ暴力的なエネルギーが漂っていて、ここでも時間の越境がなされているのを感じる。
つまりこの写真集から伝わってくるものは、変っていった風景ではなく、むしろ変らない何かなのである。人も変る、風景も変る、建築も変る、風俗も変る。変らないものなど何一つないと言っていいほど、私たちの環境は絶え間なく変化しつづけている。彼はその変化をたどるのでも、逆に変らないものを追求するのでもなく、人や風景や、モノの形、その繰り返しのパターンが発するエネルギーの粒子に感応するのである。その結果、変らないものが明らかになった。それは何なのか。
人間関係の萎縮が言われたり、草食系男子が取り沙汰されたりするマスコミの物言いとは無関係に、彼は風景のなかに、モノの形のなかに、人の情景のなかに、生命の波動を見いだし、シャッターを切っていく。相手が生き物であれ、モノであれ、同じことである。屋根瓦にも薪の束にも生命を喚起させるリズムを見いだし、あたかも呼吸するように自らの肉体に取り込んでいく。彼にとって写真とは、外界にさざめく生命感とのやりとりなのだ。
最後の2点が作者の風景観を物語っていてすばらしい。3人の男が野良で一服している。1点が寄りで、もう1点が引きだ。寄ったカットでは三人三様のしぐさがおもしろく、物語が生まれてきそうな気配がある。引きのカットは中央に縦にあぜ道が通り、奥の用水路を越えて二手にわかれる。背後は森の繁みだ。なにげないようでいて、とても立体感のある風景である。いや、写真家がそのように撮って見せているのだ。男たちはその道の分かれ目に座っている。等間隔に座って膝に両手を置き、風景の一部になって溶け込んでいる。