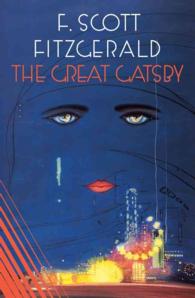『火の見櫓―地域を見つめる安全遺産』火の見櫓からまちづくりを考える会(鹿島出版会 )
一基にひとつの「火の見櫓物語」のスタートに
敦ちゃんちと俊ちゃんちの間に火の見櫓はあった。昭和40年代、山形県の内陸部の小さな集落を通る道と用水路が交わる地点で、近くには消防団のポンプ車庫がある。半鐘の音を聞くのは春と秋の火災予防週間で、朝夕定時に、カーン、カンカンカーンというリズムが繰り返された。子どもにとって火の見櫓は、その役割よりそれが立つ場所が重要で、「遊んではいけません」の鎖をくぐって湿っぽいコンクリートの土台に座り込んだり、鉄骨にのぼったり用水路を飛び越えたりして遊んだものだ。
櫓に見晴し台はなく、左手で梯子につかまったまま右手で半鐘を鳴らすタイプのものだった。火の見櫓なんてどこでもだいたいそんなものだろうと思っていたら、とんでもない。本書に収録されているのはおもに静岡県内のものだが、細部にわたってあまりにも多彩で驚いてしまう。まとめたのは「火の見櫓からまちづくりを考える会」(以降「考える会」)で、生まれ育った家で火の見櫓を見ていたがいつのころからか妙に気になり出した塩見寛さんが有志を募って立ち上げた団体である。調査のほか、2003年2月には大井川中流で「火の見櫓サミット」を開催している。
※
まずもって「考える会」の調査報告が美しい。静岡県内の火の見櫓を2000年から2003年まで悉皆調査し、構造をとらえつつ周囲の環境をおさえた写真や形状の特徴をとらえたスケッチ、櫓からの視野や音の伝わりをあらわした地図などの資料、そして、鉄造か木造かコンクリート柱か、櫓型か櫓梯子型か梯子型か、屋根のあるものはそのかたちが□か△か○か10角か8角か6角か、その稜線は直線か反りかアーチかオージーアーチか、果てはねじの素材や止め方にいたるまで、あまりにきめ細やかな分類がなされていていかにも楽しい。火の見櫓が、まちづくりを考えるシンボルになりうる確信があってこその、綿密な分析だろう。
その成果を持って、サウンドスケープ研究の鳥越けい子、構造デザインの今川憲英、環境防災の重川希志依、都市計画の西村幸夫各氏専門家を迎え、りりしい立ち姿/半鐘の聞こえる集落/手仕事のエンヂニアリング/火の用心の教え/小さな安全遺産、と分けた各章が、ひとつの火の見櫓を作り上げるかのように端整に並ぶ。読み終えた私たちが立つのはそのてっぺんで、ひとしきり見渡したら目の前にある半鐘を打ち鳴らし、どこか遠くに火の見櫓を探しに出かけてみたくなる。
※
火の見櫓は、明暦の大火(1657)の翌年設けられた、旗本による定火消が火消屋敷に建てたのがはじまりだそうである。1718年には町火消が組織され、これが明治の消防組に引き継がれていく。公設消防組に火の見櫓の設置は必須、当然公費でまかなわれるべきところ、実際は寄付金などで建てられることが多かったそうだ。しかも、標準的なモデルこそあれ製造はそれぞれ地元の鉄工所に任せられたために、構造や装飾が多様多彩になったという。造った櫓をたてて安全に固定するのも、高い櫓にのぼり半鐘を鳴らすのも、戦時中の金属供出を乗り切るのも戦後建て替えるのも、なにもかもが地域単位で行われてきた。地域の威信や職人の技をかけて、住民はシンボルとして櫓を大切に守ってきたのだろう。
日本ではかつてほとんどどこの家からも、火の見櫓が見え、半鐘の音が聞こえたはずである。櫓はそこにひとがのぼってはじめて安全のシンボルとしての機能を果たし、その足元には自主的な防災のしくみと意識があった。半鐘の音を同時に聞くことができる範囲で、しかもそれを見渡すことのできる一点があるというのは、起きて半畳寝て一畳やコルビジュエのモデュロールではないけれど、小さな社会単位をからだで感じさせてくれる。今や緊急を知らせる最速手段は携帯電話となって、その基地局は安全のシンボルのひとつに違いないが、成り立ちはあまりに異なる。
※
果たして全国に、どれくらいの火の見櫓が残っているのだろう。案じる前にまずは出かけてみることだ。「考える会」が言っている。
風景に溶け込んでいる火の見櫓が、その気になると見えてくる。そして、火の見櫓が見えてくると、集落が見えて、人々が見えてくるだろう。
生家近くにあった櫓を、今度確認してこようと思う。半鐘を鳴らす位置からの眺めを、今はじめて想像してみる。西村幸夫さんが言っている。
自分たちの身近にこんなにおもしろいものがあるとすると、それだけでも少しは元気が出るというものである。物語そのものが人にエネルギーをもたらす。火の見櫓の物語そのものからまちづくりを考えることが可能なのである。
ひとつとして同じ火の見櫓はなく、一基ずつに別の物語があることを本書は示す。本書を手本に、あの火の見櫓の記録をとってみるつもりだ。なにしろそれが物語のスタートだからだ。