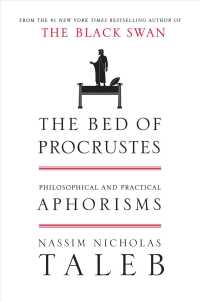『The Bed of Procrustes : Philosophical and Practical Aphorisms』Nassim Nicholas Taleb(Random House)
「現代のニーチェ(?)の言葉」
2007年に原書が出た『ブラック・スワン』の衝撃は忘れられない。その年の大晦日に徹夜して読了したが、その後、完徹の読書をしてないような気がする…。
2009年に邦訳が出たとき、ビジネス書として売り出されたのは少し残念だった。そういうカテゴリにおさまらない本だと思うからだ。
白鳥は白いものだと誰もが思っていた。オーストラリアで黒い白鳥が発見されるまでは…。千の実例から得た「真理」も、たった一つの反例で崩れ去る。
災害やテロだって、そうだ。ずっと起こらないから今日もだいじょうぶだと思う。しかし、今日起こるかもしれないのだ。今年10周年を迎える9.11を想起しよう。
「ありえない」と思うからこそ、実際に起こったときの衝撃ははかりしれない。そういう現象を「ブラック・スワン」と呼び、従来の学問では対処できないと看破したのがこの本だった。著者の証券市場のスペシャリストとしての豊富な経験、数学・経済そして哲学・文学にわたる博識が縦横に発揮された、とびきり面白い知的読み物。意表を突く挑発的な筆運びの連続に、とにかく読まされてしまう。
しかし、『ブラック・スワン』の真の魅力は、偶像破壊的でありつつ(とりわけ現実の経済を予測できない従来の経済学への批判は辛辣を極めるが、先般の金融危機により著者の確信は強められただろう)、単なる懐疑主義(著者が嘲笑するポストモダニズムのような)にはとどまらず、どこまでも錯誤に陥りやすい人間性(行動経済学が明らかにするような)を自覚した上で、わたしたち自らの実践としていかに「ブラック・スワン」とつき合うかを示唆するところだ。
そこには、紛争の地レバノンで、砲火の音にさらされながら数々の古典を読破したという著者の特異な知的遍歴も反映している。かつてはヘレニズム文化が花咲き、長きにわたって多様な宗教・民族が共存していた彼の地も、短い現代史の間に終わりなき争いに巻き込まれてしまう。「ブラック・スワン」の経験の原点であり、のちに誰も予想しなかった市場の大暴落が起きても、著者は既視感を覚えるのだ。
近代の知は、人間が知りうることの範囲を広げはするが、知りえないことについても知りうるという傲慢を育む。知りえないこととどう向き合うかは、先人たちの方がはるかに深く考えていた。アリストテレスからモンテーニュ、ポパーからマンデルブロート(フラクタル理論で有名)にわたる古今の洞察を武器に、驕りやすい今日の知性に痛撃を加える著者の姿には、現代のニーチェとでも呼びたいような畏敬を覚える。
その著者が、ついに「哲学的実践的警句集」という副題を持つ本書を出した。おりしも日本では『超訳 ニーチェの言葉』の大ベストセラーという現象があった。ニーチェの著書から断片を(毒消しして?)切り売りすることには議論もあるが、忙しいビジネスマンの知的サプリとして歓迎されたのだろう。なんとなれば、寸鉄人を刺す古代の警句(アフォリズム)の伝統を近代に蘇らせた中興の祖がニーチェであり、そういう受容もありうるわけだ。そして、そのニーチェを半ば愛し半ば憎むという著者がその衣鉢を継ぐことに不思議はない。
題の「プロクルステスのベッド」は、ギリシャ神話にちなむ。宿の主人プロクルステスには、旅人の足がベッドより少しでも長ければ切り落とし、短ければ引っぱって伸ばす奇癖があった。最後にはテセウスに同じ方法で退治されるのだが、ここでは現実を思い込みの型に当てはめて解釈し道を誤りがちな人間の性になぞらえている。
(これと似た話をある戦争体験者に聞いたことがある。その方は兵隊に取られて、軍服を着せられたのだが、サイズが合わなかった。それを上官に言うと「おまえが服に合わせろ」と言われたそうだ。「これじゃ日本は負けだと思ったよ」とその方は述懐された。)
ここでも、「プロクルステスのベッド」的な状況に陥りがちなわたしたち(特に制度化された学問やジャーナリズム)への批判は辛辣を極める。それは、警句というかたちをとるがゆえにいっそう効果的だが、著者が「あとがき」で言うように、「技術に合わせて人間を改変し、雇用の都合に倫理を当てはめ、経済学者の理論通りにお金を使わせ、ある物語の型に人間生活を押し込める」(p. 107)本末転倒な状況への根底的な批判なのだ。しかも、その根っこには「2500年もの間、誰もその影響から私たちを守ってくれる強靭な知性が現れなかった」というプラトン的な理念化の魔力があるのだから、いくら批判しても足りないわけだ。
しかし、警句の魅力は、そのような「毒」の部分もさることながら、「あるある」と思わず頷く人間的洞察や、はっとした後に思わず笑いがこみ上げてくるような(人間的な、あまりに人間的な)観察にも求められる。本書は、「偶然、成功、幸福、ストア主義」「強さと脆さ」などのゆるやかな章題で区切られ、それぞれが著者の思索の体系にリンクしているようだが、気まぐれに部分を取り出して面白がるのも、警句の立派な楽しみ方である。ここでは、気になったいくつかの言葉を、散漫を厭わずに挙げておこう(順番はバラバラ)。
「本当に嫌なときの方が”ノー”とは言いにくいものだ。」
「”よい聞き手”と言われるのは、たいてい、技巧的に洗練された無関心の持ち主である。」
「土地や製品が広告より劣るのは、ままあることだと受け入れる。しかし、人が第一印象より劣るのは許せなかったりする。」
「個人が自慢すると、ひどい悪趣味と見なされる。しかし、国家がそれをやると、”国の誇り”ということになる。」
「科学に人生や生に関わる事柄を説明させるのは、文法学者に詩を説明させるようなものだ。」
「愛と幸福のちがい。愛について語る人は、たいがい愛に生きている。だが、幸福について語る人は、たいがい不幸である。」
この警句の後には、「幸福についての学術会議に出席したら、学者たちは誰もが不幸そうだった」というものもあった。
「真の文学」を愛するこの著者は、本の世界についても、一家言も二家言もある(”The Republic of Letters”という章に以下の言葉が見られる)。「ある種の本(真の文学、詩)は要約不可能だ。また、ある種の本は10頁ほどに要約できる。しかし、大部分の本は要約すれば0頁だ」とは、大変キビシイ。「いわゆる”ビジネス書”とは、深みも文体も経験的厳密さも言語的洗練も欠いた書き物のために書店がつくったカテゴリである」と言われると、本好きのみなさんは頷くのかな。ノーコメント!(笑)
出版物の洪水もよく批判されるところであるが、誰もが使うネットとの付き合い方もむずかしい。「情報爆発の時代とは、言語的失禁症に似ている。やたらと話せば話すほど、ますます聞く人がいなくなる」というのは言いえて妙だろう。いささか不穏当だが、「物理的に相手を殴れば、スッキリする。しかし、ネット上で悪口を言っても、自分自身を傷つけるだけだ」というのも一面の真理である。新聞を一切読まず、ジャーナリストからメールをもらうと沐浴して身を清めるという著者ほどでなくても、自分の身の丈に合った情報の生態系を考えないと、溺れるままになってしまう。
本書の金言をもう一つ。ここだけ原文で引用する。"You exist in full if and only if your conversation (or writings) cannot easily reconstructured with clips from other conversations." (p. 41)
そのような存在を得たい人には、著者の言う「哲学者であること」は有効かもしれない。「哲学者になりたければ、まずゆっくり歩くことから始めよう」とはユーモラスだが、思考のリズムは生き方の問題なのだ。『ブラック・スワン』にも、走って電車に乗らないことにしただけで考え方が変わったという話があった。判然としないものに既知のパターンを当てはめるのは人の常だが、判断を引き延ばし、知らないということに意識的になれる人には、もっと広い世界が広がっている。
その毒舌にもかかわらず、著者のすすめは、決してシニカルな懐疑一辺倒といったものではない。アリストテレス的な、古典的美徳(勇気、エレガンス、博識)を目指す生き方である。その意味で、本書の底に流れる精神は、「哲学的」かつ「実践的」なのだ。それにしても、サンデル教授の正義論を読んでも、アリストテレスに帰った方がいいらしい。そんな感じで、『超訳 ニーチェの言葉』を手にしたビジネスマンが、本書によっても思わぬ方向に導かれると面白いではないか。
(洋書部 野間健司)