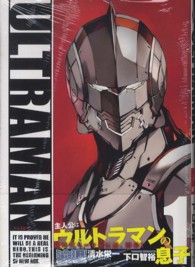『ULTRAMAN』清水栄一:原作、下口智裕:作画(小学館クリエイティブ)
「メジャー化する二次創作と「大いなる虚構」は両立するか?」
本作は、誰もが知る特撮作品『ウルトラマン』の二次創作である。
舞台は、ゼットンに倒された初代ウルトラマンが宇宙へと帰っていってから数十年後。ウルトラマンと同化していた科特隊ハヤタ隊員の息子、早田進次郎は、父から受け継いだウルトラマン因子の影響で、生まれつき特殊な能力を持ち合わせていて、それゆえに新たな敵との戦いへと巻き込まれていく・・・というのがあらすじである。
おそらくこうした二次創作はこれまでにも多々存在してきたものと思われるが、本作が一線を画しているのは、「メジャー化した二次創作」ということである。すなわちそれは、同人誌のような限られた市場にだけ流通する作品ではなく、一般の店頭でも売られているということなのである。
昨今では、手塚治虫の名作『ブラック・ジャック』の前史ともいえる部分を描いた、『ヤング ブラック・ジャック』(脚本:田畑由秋、漫画:大熊ゆうご)など、こうした「メジャー化した二次創作」が増加傾向にある。
こうした傾向は、かつて東浩紀が『動物化するポストモダン』(講談社現代新書)で指摘した「データベース消費」が、まさにメジャーなものとなってきたことを物語っていよう。
すなわち「データベース消費」とは、この社会における「(理想や夢といった)大きな物語」の崩壊に伴って起こった、創作活動や作品の受容をめぐる新たな動向である。
つまり創作活動やその受容の主たる目的が、「大きな物語」を志向することにあるのではなく、むしろ多様化し散在するいくつもの「小さな物語」を、時々においてデータベースから呼び起こし、せいぜいその組み合わせの妙を楽しむぐらいのことに変わってきたということである。
こうした動向は、もともとはオタク系文化や、特に同人誌などで先駆的に見られてきたものだが、それが今日では完全にメジャーなものとして定着しつつあるということなのだろう。
その一方で、こうした「メジャー化する二次創作」の中でも、本作は突出した課題を抱えた注目作なのではないかと思う。
それはすなわち、「メジャー化する二次創作」と「大いなる虚構」が両立するのかどうか、ということだ。二次創作の方向性が、異性キャラに対する萌えであったり、あるいはその人物像への掘り下げのようなところへ向かうならばともかく、本作では、正義の味方であったウルトラマンが再び(といっても今回は姿をだいぶ変えて)登場し、そして敵も登場する。
こうした「敵-味方図式」は、それこそ「理想」や「夢」といった「大きな物語」が存在していた過去の社会ならば共有されやすかったものだが、はたして「データベース消費」が広まっている今日においては、どれだけの広まりを見せられるものだろうか。
いうなれば、これまでの二次創作は、そのほとんどが複数のオルタナティブストーリー(ズ)にあたるものであり、「大きな物語」が崩壊した時代における「(多数の)小さな物語(たち)」を描いてきたわけである。そこに果たして「大きな虚構」を描くことは成立するのか、単行本ではまだ第一巻しか刊行されていない本作の行方を、今後も注意深く見守っていきたいと思う。
実は同じような期待は、『ケトル』誌2012年10月号(太田出版)で評論家の宇野常寛氏も述べていたことである。
この点について、さらに別な表現で述べるならば、1990年代後半以降に放映された『エヴァンゲリオン』は、かつての「大きな物語」を描いたアニメ作品の残滓あるいはその引用をノスタルジックに眺めていた年長世代と、アダルトチルドレンな主人公のありように感情移入していた若年世代との、二層のファンのマッチングによって大きなブームを呼び起こしたと言われている。
本作は、それと同じパターンで受容されることになるのか、それとも「メジャー化した二次創作」という全く新しい境地を切り開くことになるのか、昭和特撮世代として、大いに今後を期待したいところである。