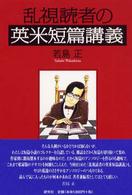『乱視読者の英米短篇講義』若島正(研究社)
「明晰な情事」
大学生にお薦めの批評入門第二弾。文学とのお付き合いの方法がわからないという人には、是非手にとってもらいたい一冊である。いわば恋愛指南の書。
著者はこの何十年、文学という異性とさまざまな形で付き合ってきた。声かけ(ナンパ)や、十年越しの片思いや、別れや、喧嘩や、場合によって悲恋や、あるいは思わずこちらが赤面するほどのディーーーーップな秘め事もあった。いやあ、先生、お盛んですな、と思わず言いたくなる。しかし、そんなに情熱的で経験豊かなのに、まるで何事もなかったかのように淡々と、明晰に語ってみせるところが何よりすごい。ほんとうの淫乱とはこういうものかと思う。
著者の若島正は、英文学界では知らない人はいないほどの学者だが、果たして一般にはどうか。渋谷のセンター街で道行く女子高生に「若島正って誰?」と聞いても、ちゃんとした答えを返してくるのはせいぜい10人中1~2人くらいだろう。未熟者め!と思う。
しかし、若島正の魅力は、決してポップにはならないところにこそある。なぜポップにならないかというと、若島正はいつもほんとうのことを言うからである。批評めいたものを一度でも書いたことのある人なら経験があると思うが、書くという作業には、どこかでウソをつくことでつじつまを合わせて、それでやっとほんとうのことを言う、というような側面がある。別に悪いことではない。それは会社経営に喩えるなら、一方で借金して、その借金を投資に回すことで利益をあげる、というようなやりくりと似ている。
いや、本書も完全な無借金経営ではない。思わせぶりな謎かけや偶然の出遭いはお手の物。「ふふふ。もうおわかりかと思うが…」なんていう明智小五郎みたいな台詞も頻出する。いずれも、経験豊かな京風遊び人ならではの恋愛「テク」の一端だ。そこにはほどよいウソが紛れこんではいる。
しかし、肝心のところで甘くは落とさない、つまり、ウソをついてまで無理矢理盛り上げたりしないのが若島流なのである。次にあげるのは、おそらく本書の中でももっとも感動的な一節である。
わたしには人間がわからない。人間のなかでもとりわけ女性がよくわからない。たぶん、子供のころから将棋盤の上の世界に取り憑かれていたせいなのだろう。盤上で駒たちが形作る複雑な磁場や、抽象的な数学が、自分にとっては一番しっくりくる世界なのだ。ところが、人間たちが織りなす心理模様となると、突然わからなくなる。人間によって構成された社会の力学には、まったくと言っていいほど関心がない。文学をやりはじめたのは、そうした歪みをいささかなりとも矯正したいという自己治療の意味合いが大きかったのかもしれない。それでも、やはり人間というものがよくわからない。他人というものに興味がなくて、自分自身のことばかりを考えているのは、一種の病いなのだろうかとよく思う。
あまりに本質的なことを言われてしまって、どう反応していいかわからないくらいだ。渋谷センター街のヤンキー女子高生よ、よく聞け、と言いたい。
この一節、本書のかなり後の方に出てくる。私たち読者が若島流の文学遊びを堪能したあとに、とどめの一撃のようにして繰り出される言葉なのだ。「あとがき」に、もとの雑誌連載時には編集長の津田正氏(このブログのお隣さん)に尻をいじられながら、そそのかされるようにして書いたとある。だとすると、この一節は著者自身にとっても、ようやくどこかに辿りついたような感慨とともに思わず書いたものなのかなという気がする。こんなことを、こんなにあっさりとわかりやすく言ってしまう書き手を、信用しないわけにはいかないでしょう、ということだ。怖い人だな、とも思う。こういうところを出発点にしている批評――あるいはいっそ「文学」と言ってもいいのだが――は、ちょっとやそっとではへこたれない。
本書は、文学を隅々までわかってしまった人の自伝的自慢話的「お講義」などではないのだ。人間も世界もよくわからないで、日々冷や汗を書きながら生きている人が、いかに文学作品と情事を重ねることで、世界をいわば裏側から理解してきたかを語る書物なのである。
だからこそ、どの章もいきなり作品の話からはじまるのではなく、著者若島正を起点にすることで、じわりそろりと始動するという体裁をとる。この書評もついつい著者のことばかり書いてしまったが、そもそもがそういう本なのだから仕方がない。全体は、英米それぞれ12の章と、「シニコー夫人への手紙」と題された秀逸な「おまけ」からなるが、作家名で言うと、アメリカ編ではアンブローズ・ビアス、ジョン・アップダイク、ウラジミール・ナボコフといった有名どころの間に、コンラッド・エイキンやシャーリー・ジャクソンといった名前ががひょろっと入っていたりする。イギリス編ではもう少し偏愛性が強く、ウィリアム・トレヴァーやH・G・ウェルズ、ヴァージニア・ウルフ、ジェームズ・ジョイスの狭間に、A・E・コッパード、ショーン・オフェイロン、フラン・オブライエンといった作家が並ぶ。
批評の方法としておもしろいのは、若島氏が下手に読者に語りかけたりしないことだろう。説得なんか興味ない。言いっぱなし。やりっ放しである。ふだんの講演でもそうなのだが、若島氏の話術というのは、いろいろと仕掛けがあるにもかかわらず、まるで独り言のように聞こえるところにある。文章は誘惑的に読みやすいのだが、こちらは誘惑されていることに気づかない、そんな文章だ。
一箇所、読んでいて「え?」と思うのは、著者が「わたしは文章が書けない」と述懐するところである(ギャスを扱った章)。まさか、と、まあ、思う。しかし、これはつまらない謙遜などではない。この一節に触れてからあらためて気づくのは、若島氏がリズムに乗って語ることのウソっぽさに敏感だということだろう。よけいな比喩もつかわない。(比喩を使うときには照れまくりなところもおもしろい。「陳腐な比喩で気が引けるが、もぎたての桃をかじるような、そんなみずみずしさがオフェイロンの文章にはみなぎっているのである」というような一節、たいへんいいです)
すでに引用した箇所だけでも十分おわかりいただけたかと思うが、今時めずらしいほど、たたずまいの立派な文章なのである。凛としている。走らないし、揺れない。踊らない。ごまかさない。だから、短いスペースの中でも、鋭く作家の急所が突ける。ためしに覗いてみるなら、まずは「ちぎれた足」と題された最終章のジョイス論をお薦めする。ジョイスは若島正にとっては、永遠の恋人などでは決してないのだが、にもかかわらずずっと気になっているという実に微妙な作家である。その章の中で若島はこんなことを言う。
わたしには、この退屈なダフィー氏という人物がよくわかる。なぜなら、わたしもまた彼そっくりに退屈な日常を送る男だからである。まるで鏡を見ているような気がするほどだ。こういう人間が退屈な日常を逃れようと思えば、おそらく銀行員をやめるしか手はない。そうすれば、グレアム・グリーンが傑作『叔母との旅』で描いたような、心躍る冒険が待っているのかもしれない。しかし、それは小説の中だけでしか起こらない出来事であり、現実には残念ながら、こういう人間は永遠に銀行員でありつづけるしかないのである。それがダフィー氏の宿命だ。言葉を誤解されたと受け取って人間関係の絆を自ら断ってしまう、それがダフィー氏の限界だ。
こういう一節を読んで、こんな文章は書けないであろうわたしたちも、つかの間、若島正と同一化して「まるで鏡を見ているような気がする」と思ったりする。それが批評というものの不思議な作用であり、治癒力なのだろう。