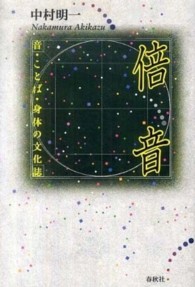『倍音』中村明一(春秋社)
「〝こんばんは、森進一です〟の謎」
書評空間で今井顕氏が取り上げておられるのを見て、目をつけた本である。期待に違わずあやしい領域に踏みこんだ、楽しい本であった。
まず誰もが気になるのは、「倍音」という聞き慣れない言葉だろう。これはいったい何なのでしょう?
音に含まれる成分の中で、周波数の最も小さいものを基音、その他のものを「倍音」と、一般的に呼び、楽器などの音の高さを言う場合には、基音の周波数をもって、その音の高さとして表します。つまり、基音が四四〇ヘルツなら、ピアノでも三味線でも四四〇ヘルツの音=ラ(A3)と言うわけです。「倍音」のことを「上音」と呼ぶこともありますが、基音より下に付くこともあるので、「部分音」と言った方がより正確です。この本では、一般に使われている「倍音」という言葉を使うことにします。(9)
もしこのような説明が冒頭にあったら、学校時代、物理も数学も音楽も苦手だった筆者は、「ごめんなさい。私が悪うございました」と言って即座にこの本を閉じていただろう。そもそも物理が苦手な人間というのは、「…と言った方が正確です」などとあるだけで、首でも絞められたような青ざめた気分になってしまうのだ。
しかし、著者の中村氏もそのあたりはよくわかっている。ここに至る前に、それはそれは懇切丁寧に「怖がらなくていいからね」という準備をしてくれる。物理が苦手な人には、直前にあるやさしい導入が効果を発揮するだろう。
まず、大切なことを、ひとつ、理解していただく必要があります。一般的に、音は、ひとつの音として聞こえる場合でも、複数の音による複合音からなっている、ということです。「ひとつの音」と思って聞いている中に、さまざまな音が含まれているのです。それらのさまざまな音がどのように含まれているか、によって、音色はつくられます。音色(音質)をつくっているのが「倍音」なのです。(8-9)
ああ、これならわかるかも。非常に野蛮なまとめ方をすると、音というカタマリ、というか広がりの、下の方にどてっとある部分を「基音」と呼び、どちらかというと上の方でぷわぷわ浮いている成分を「倍音」と考えればいいのだ。「基音」というくらいだから、音を頭で理解したり整理したりするときには下の方にだけ注意をはらえばいいのだが、どうやら私たちは「基音」以外の高い方の音も知らず知らずのうちに耳にしている。そして、私たちが音を聞いたときの印象を形成するのは、この高い方の「倍音」をも含めた、音の総合的な表情なのらしい。
本書の目的は明確である。「基音」と違ってなかなかうまく記号化するのが難しいこの「倍音」の領域に光をあて、それが人間の文化の中でいかに大きな役割を果たしてきたかをあらためて強調する、そして、日本の伝統文化がいかにこの倍音に対する敏感な感受性に支えられてきたかを確認する、ということである。その過程では森進一の声の秘密までが解き明かされる。
しかし、一難去ってまた一難。倍音には二種類があるという。その呼称がいかめしいのだ。ひとつは「整数次倍音」。すなわち「基音の振動数に対して整数倍の関係」にある倍音だそうだ。う~ん。よくわからない。何しろ私たちは物理も数学も苦手なのだ!もうひとつの方は「非整数次倍音」というらしく、こちらが「基音の振動数に対して整数倍の関係」にはないということくらいは想像がつくが、そう言われてもあまりわかった気はしない。しかし、このあたりを中村氏は次のように説明してくれる。
弦がどこかに触れてビリビリとした音を発することがあります。このように整数倍以外の何かしら不規則な振動により生起する倍音が「非整数次倍音」です。(12)声の例で考えるとわかりやすい。整数次倍音が強い声というのは「ギラギラしてまぶしい声」なのだそうだ。美空ひばり、郷ひろみ、浜崎あゆみ、松任谷由実、黒柳徹子、タモリ……。これに対し、非整数次倍音の強い声は「濁った声」に聞こえる。ザラザラした、ガサガサした声である。宇多田ヒカル、明石家さんま、ビートたけし、堺正章、桑田佳祐……。
そして森進一が登場する。森進一のあのカサカサした声こそは典型的な「非整数次倍音」の声だという。「非整数次倍音」の多い声は、親密感、情緒、重要さを訴えかけてくる。森進一の声というのは、だから、親密でしかも大事なことを言っているように聞こえる。「整数次倍音」の多い朗々としたよく通る声では、ぎらぎらしたカリスマ性が生み出され、声が遠く上の方から響いてくるように聞こえるのとは対照的なのである。
さてほんとうにおもしろいのはここからだ。中村氏は推論するのである。カリスマ的でどこか遠い所から響いてくるようなタモリの「整数次倍音」は、実はタモリが芸人たちとからむ際の親しげな所作とちょうどコントラストをなしているのではないか。つまり、声にカリスマ性があるからこそ、仕草の親しさやなれなれしさから来る非カリスマ性が生きてくるのではないかというのである。反対に「非整数次倍音」で親しげな声を持つビートたけしが毒のある発言をすると、親密さの中に突き放すような冷酷さが混じって聞こえ、「非整数次倍音」の持ち味である親しさをより生かす効果がある。声に影響力のある有名人というのは、こうして正反対の要素をうまく混合させて使っている、というのが中村氏の考えである。
そこで再び森進一の話となる。「こんばんは、森進一です」と言うだけで人は笑う。なぜか?何がおかしいのか?自己紹介をしているだけではないか?(この「こんばんは、森進一ですネタ」はいささか古いギャグのような気もするが、それは本質的な問題ではない)この疑問に対する中村氏の答えは次のようなものである。
[森進一の]声には[非整数次倍音]が非常に多く含まれているので、それを聞くと日本人の頭の中では「重要だ!」という反応が生じてしまうのです。さして重要ではない言葉と「重要だ!」と感じさせる声の響き、頭の中でその両方がぶつかる、それによって私たちの頭の中では相反する二つのものが齟齬をきたし、どうしてよいか分からなくなり、笑うしかなくなってしまうのです。(56)この説明については、「そいつはあやしいなあ~」というのが筆者の正直な感想だが、この本の魅力はこうした推論の過程でつまらぬ学者っぽい逡巡などせず、おおらかに大胆に問題をとらえていく著者の想像力の飛躍ぶりにある。そうしたいわば「三振を恐れぬ想像力のフルスイング」によってしかとらえられない事柄はきっとあると筆者も思う。
本書の中で、著者の持ち味がとりわけ出ているのは日本文化の特性を考察した「第4章 日本という環境・身体・言語」「第5章 日本文化の構造」のあたりだろう。ここでは中村氏は果敢に「日本とは何か?」という問に立ち向かっていく。その過程では、たしかに飛躍もある。たとえば、日本では湿気が多く地面が柔らかい落ち葉に覆われているので「日本中が響かない空間になっていたのです」(78)とか、「[日本は]足場が非常に悪いのです」(82)とか、「日本には、低い声の人があまり多くみられません」(102)といった部分だけ読むと、「そいつはあやしいなあ~」と言いたくなるかもしれない(筆者の経験で言うと、イギリスではあちこちに牛の糞が落ちていて非常に足場が悪かったし、ニューヨークではみんなきんきん声で話しているような気がした)。しかし、中村氏自身、「基音」を軸に考えるのではなく、「倍音」で思考する人なのではないかと思う。その発想法は連想の詩学に根ざしている。ならば読者としても、その飛躍の妙味をこそ味わうべきなのかもしれない。
経歴からして不思議な人である。中学生の頃はエレキギターに凝って、ビートルズやベンチャーズからスタート。それがジミ・ヘンドリックスに出会って衝撃を受けたかと思うと、後に尺八に目覚め、いきなり尺八の達人に弟子入り。しかも、大学は工学部応用化学科卒(量子化学専攻)。本書の文献リストを見ても、哲学、文学、心理学から音響工学に至るまで幅広い資料がとりあげられている。そして中村氏は行動する人でもあるのだ。尺八の音を別の素材で出そうと実験を重ねついにそれが鋼であることを発見するもあまりに重くて楽器化を断念したとか、理想のスタジオづくりを目指して試行錯誤を重ね、ついに部屋中に大理石をしきつめたといったエピソードを読んでも、科学的なデータ主義と奔放な思考とが混在していて、ちょっとしたカリスマ性さえ感じられる。後半で展開されるシンクロと、リズムと、人間社会をめぐる議論もなかなかおもしろく――そしてどこかあやしい。肩書きは尺八奏者とのことだが、単なる「芸術家」ではなさそうだ。