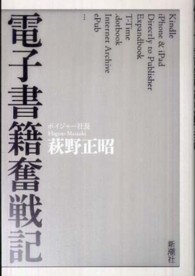『医療・合理性・経験――バイロン・グッドの医療人類学講義』バイロン・J・グッド(江口重幸・五木田紳・下地明友・大月康義・三脇康生訳)(誠信書房)
「「説明モデル」から「物語」へ」
前回(2007年10月)の当ブログで、A.クラインマンの「説明モデル(explanatory model)」概念をご紹介しました。この概念を一歩進めて「物語」という言葉を導入したのが、バイロン・グッドです。
私がこれまで出会ったさまざまな人たちによる病いの語りには、確かに、独特の意味世界があるように感じました。ただ、「説明モデル」という言い方をしてしまうと、どうしても生物医学モデルに比肩する体系性や一貫性を想像してしまって、どうもしっくりこないと思いました。そんなとき、「物語」という概念が、単に文学的な様式というにとどまらず、人々の自己認識や世界認識にベーシックな機能と役割を果たしているという考え方があることを知り、直感的に「これだ!」と思うようになりました。単なる思いつきの域は出ていないのですが、かねがね持っていた「なんだか一篇の物語が語られているようだなあ」という感覚にもピタリとはまるし、そうした見方が大真面目な学問研究として勃興してきているというのなら、こだわってみてもよいのではないか、と考えたのです。
グッドの研究も、この「物語」の潮流にのった人類学研究で、特に後半(特に第6章)で「物語」概念の導入が積極的になされています。この本の底を流れる問題意識は、異なった文化の言葉を自分の文化の言葉に持ち込むこと、例えば「私たちの社会で○○と生物医学的に呼ばれている病気は、あの社会では××と考えられている」といった記述を行うことの問題です。このような記述を行うとき、私たちは、あからさまに「××」を「迷信」と決めつけてしまったり、あるいは、そこまであからさまでない場合でも、「本当は生物医学的に○○としてとらえられるべきもの」という前提を暗に忍び込ませやすいのです。グッドは、そうした自民族中心主義的な翻訳からできるだけ距離をとり、それぞれの文化の人々がそれぞれのやりかたで意味を編み出してゆく、すなわち「物語」化するさまを記述することが人類学の仕事だと考えました。
第6章では、トルコの人々による癲癇の自己物語を聞きとる調査が報告されています。そこでグッドが見出した病いの物語の特質は現実の「仮定法化」と呼ばれるものです。「仮定法化」とは、物語は多元的な読みの可能性をはらむことを指しています。例として挙げられているケリムという一人の青年に注目してみましょう。インタヴューで彼は、まず、市街地を走って横断していたときに犬に吠えられて驚いたエピソードと、それから一年半後、仕事中に初めての発作に見舞われたということを語ります。それではその驚いたエピソードが失神と関係があるのかと聞かれると、ケリムは、今度は「サル・クズ」という「精霊と同じようなもの」に遭遇したエピソードを語ります。彼は「サル・クズ」を見たわけではありませんが、その気配を感じた後、その場を離れようとして発作で崩れ落ちます。
ケリムは結婚を間近にしており、そのためにアメリカで手術を受ける相談をしに医師のもとを訪れます。医師は「二つの静脈瘤が炎症をおこしている」といって錠剤を処方します。一方、ケリムを心配する友人はある宗教治療者に彼を合わせます。その夜、精霊が、ケリムと友人のもとを、かつて彼を驚かせた犬の姿で現われて、このように言います。ケリムはかつて自分たちを踏みつけにして子どもたちを殺した、だからわれわれはケリムのことを苦しめているのだ、と。しかし、結局、精霊たちは、今後ケリムを苦しめることは(祈りを捧げ続けることを条件に)しないという約束をします。ケリムは、インタヴューでこう言います。もし結婚予定月になってもよくならなかったら、自分は医師のところに行って、薬が効かないようだからやはり手術をお願いするつもりだ。
何だかごちゃごちゃした話ですね。彼の物語には、宗教的ないし神秘的な物語と、西洋医学的な物語とが混在しています。ある見方をすれば、彼に子を殺された精霊が犬の姿で仕返しをしたが、最終的には許してくれた、という物語として読めます。しかし、もし彼が明確にそう信じているなら、犬に吠えられたエピソードが失神と関係があるのかと聞かれたときに、「サル・クズ」の話などせずに「その通り」と答えそうなものです。また、彼は医師の存在をまったく軽んじているわけではなく、薬物療法を試すことにも同意したし、手術を念頭におき続けています。ケリムの発作は、この精霊との出来事以来おきていませんが、見方によっては、医師の処方した薬が効いただけではないか、という可能性も否定できません。いずれにせよ、ケリムの物語には、いろいろな読み方の可能性があるといえます。このように物語が決して一つの病いの説明に真実性を与えないことが、「仮定法化」と呼ばれていることなのです。(物語がしばしば単一の読み方をさせないことについては、以前(2006年12月)このブログでマイケル・ローゼン『悲しい本』を取り上げたときにもふれました)。
どうして物語がこのように「仮定法化」されているかというと、それは病いをめぐる状況は常に変化するものだからです。ケリム青年の発作がこれからどうなるのか、彼がどのような苦しみを感じることになるのか、そしてその場合に彼がどのような方法にすがるのか、こうしたことは誰にもわかりません。すると、完璧な一貫性をそなえた物語よりも、むしろ曖昧な部分を含んでいた物語の方が、この先の変化する状況にあわせていろいろと変化させやすいと考えられます(これをグッド自身は「変化に開かれた性質」と呼んでいます)。もちろん、ケリム青年がそのように意図したわけではなくて、彼がいろいろと病いについて悩み模索した結果そのような物語が産み落とされたにすぎないのでしょう。しかし、それが結果として未来の状況の変化に対応してゆくための資源になるわけです。
つまり、グッドの「物語」は、私たちに次のことを教えてくれています。病いの語りに対するとき、決して「説明モデル」という言葉からイメージしてしまいがちな一貫性を考える必要はなく、むしろ曖昧で多元的な読みの可能性を孕むところに積極的に目を向けるべきであること。そして、そのような物語が病いの状況とともにどのように変化するかが重要なポイントなのだということ。
全体を通して学ぶことが多いのですが、今回は特に「物語」が用いられている第6章をご紹介しました。お勧めの一冊です。