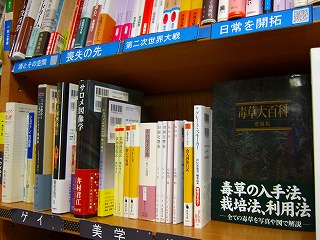『娘と話す メディアってなに?』山中速人(現代企画室)
「メディアと人間の失われた全体性の回復」
曲がりなりにも教育に携わっていながら、最近まで「入門書」というものにまったく興味がなかった。何より入門書の押し付けがましさが好きになれなかったし、入門書の類には著者自身が心底面白いと思っているものやこだわりといった身体性のようなものがまるで投影されていないと感じてしまうからだ。どちらかというと、学問であれ習い事であれ、門などというものは人に導かれて入るものではなく、多少無謀であっても強引にこじ開けてみるものだろうと思っている。そんな評者が入門書に興味を持つようになったのは、昨年、自分自身がほぼ同時期に2冊の入門書(藤田真文・岡井崇之編『プロセスが見えるメディア分析入門』(世界思想社)、伊藤守編『よくわかるメディア・スタディーズ』(ミネルヴァ書房)の出版に携わる経験をしたためである。
近年、「○歳からの」「○○でもわかる」「○時間でわかる」というように、いかにハードルを下げたかを競うように宣伝する「形容句付き入門書」が次々に出版されている。その様相は、視聴者を獲得するため他局より放送開始時間を1分、2分と早めるニュース番組の競争のようでもある。
自分の高校・大学時代を思い出してみると、「誇示的消費」(ウェブレン)というのか、大して分かりもしない哲学や現代思想の本を無理して読んでいたものだ。しかし、現在「おバカキャラ」といわれるタレントが広く受容されていることが示すように、教養がないことを人に見せることは恥ずかしいことではなくなっている。そればかりか、「おバカになれないとうまくコミュニケーションが取れない」といった内容の話をよく学生から聞く。
さて、本書の紹介へと移ろう。
だが内容へと話を進める前に本書のスタイルについてもう少し考えてみたい。本書の内容も「形容句付き入門書」同様、かなり分かりやすいものとなっている。だが内容の分かりやすさとはまた別に、興味深い工夫がスタイルに埋め込まれているのである。
「娘と話す」というのはシリーズ全体に共通する形容句だが、なぜ、「息子」ではなく「娘」なのだろうか。文化やメディアを子どもに語るということを想定した場合に、「父」が「息子」にという構図が暗黙のうちに設定されがちである。書籍検索サイトで見てみると分かる。「父と息子」で検索すると無数に出てくるが、「父と娘」だと、田中角栄と真紀子氏のような有名人親子の話か、もしくはアダルトなジャンルに限定される。しかし、「娘と話す」といったときに主語は母かもしれないし父かもしれない。また、「娘」は血縁関係の娘ではないかもしれない。このように、本書はまず読者の固定観念をずらすところから出発する。
先日、知人から「『父と娘』をテーマにした絵本があったら教えてほしい」と頼まれた。だが、自宅の本棚を見渡しても、大型書店で探してもなかなか見つからない。「7匹のねずみ」シリーズ(山下明生著/いわむらかずお絵)のように子どもたち(あるいはキャラクター)のなかに女の子が含まれるものはあっても、父親と娘が2人で向き合うというものがないのである。そこで考えたのは、恐らく、父と娘(あるいは他人の娘)が対話するという設定が日本の文脈では成立しにくいのではないかということだ。これまで多くの父親が子育てに参加してこなかったし、子どもと話し合う回路を持っていなかったことの表れかもしれない。
もう一つの特徴的なスタイルは、会話体であることだ。「Q&A」のような会話体は確かに分かりやすい。日常会話を用いているため読み手の身体に違和感なく入り込んでいく。しかし、著者自身が疑問(アジェンダ)を設定して、同じ著者が答えるというのはある種の情報操作につながりやすい側面も併せ持つ。例えば政党紙などを見ると、ある政治問題について親子の会話などのスタイルをとった記事をよく見かけるが、あれは明らかに政治的メッセージを盛り込んだ説得コミュニケーションとして設定されている。つまり、分かりやすい会話体ほど、実のところメディア・リテラシー(批判的読解能力)を要するのである。
しかしながら、本書がとる会話体はそのような陳腐な定型ではない。フィクションであるとはいえ、生きた言葉・物語となっており、まったく新しい入門書スタイルといえるものだ。
ハワイの大学に留学してきた架空の少女・ナニは、ゼミの指導教授の勧めで小さなFM放送局で番組制作に携わる。そして、制作現場での経験を通じてメディアが持っている歴史的な意味合いから今日的な問題までを学んでいく。メディアと戦争・プロパガンダから、効果論、産業論、法制度論、メディアイベント論にいたるまで実に幅広いテーマがカバーされている。
「ナニがおそるおそるカモメFMの玄関のドアを開けると、フロアの一部を防音ガラスで仕切った小さなスタジオが目に飛び込んできた。スタジオの中ではパーソナリティらしい女性が、ヘッドフォンを耳にかけ、マイクに向かっておしゃべりを続けていた。スタジオには、この女性一人だけしかいなかった。驚いたことに、この女性はみずからミキサーらしい機械も操作していた。何もかも一人で放送番組を進行しているのだった」
「たとえば、一九七〇年代のアメリカでは、それまでのアフリカ系アメリカ人に対する否定的な決めつけに対して、逆に「ブラック・イス・ビューティフル(黒人は美しい)」という肯定的なイメージをぶつけるというやり方をとった。否定的イメージに対して、マイノリティたちが戦略的に肯定的イメージをぶつける遣り方を戦略的本質主義と呼ぶ人もいるわ」
このように、語られている内容も何気ない現場の描写から理論的に踏み込んだものまでバラエティに富む。
著者が本書全体を通じて意図しているのは、二重の意味で「全体性」を取り戻すということではないだろうか。現在、メディアを語る言葉は、現場/学問、批判学派/経験学派のような二項対立的な立ち位置、あるいは法制度論、産業論、歴史学のようなアプローチによって非常に細分化されている。そのせいかどうかは分からないが、「メディアってなに?」という問いに全体的に答えようとする本がめっきり少なくなった。一つめの意図はそこにあろう。
二つめは、メディアによって失われてきた人間の全体性や身体性の回復である。本書で繰り広げられる物語は、大学生のナニがラジオ制作という実践を通じてメディアが人間をとりかこむ環境を理解していく過程を描いており、圧倒的なテクノロジーのなかで失われた人間の全体性を再構築していくような試みといえるものだ。
「被災のまっただ中で、在日外国人などのマイノリティが生きるために必要な情報を自らの手で地域にとどけるために、当初は無許可のいわゆる海賊放送局として設立されたこのラジオ局に、メディアの原点をあらためて発見したのです」
著者が、本書の設定をミニFMとした理由が、甚大な被害を出しライフラインも寸断された阪神大震災後のFMの活動に携わった経験にあると言うことからも、評者にはそのように読めた。そこらの「形容句付き入門書」とはひと味もふた味も違うこだわりと奥行きが本書にはある。