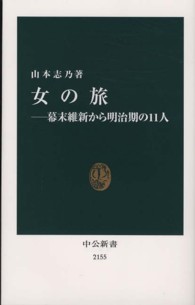『深沢七郎外伝』新海均(潮出版社)
「天才作家の苦い味」
何しろ、あの深沢七郎である。伝記的事実の記述だけで十分スキャンダラス。実際、本書からは深沢の破天荒な生き方が生々しく浮かび上がってくる――そういう意味ではすぐに作品を手に取りたくなるような格好の「深沢七郎入門」となっているのだが、それだけではすまない。読み進めて引きこまれるのは、意外な箇所なのである。
まず冒頭から目につくのは、この本に「深沢七郎について正しいことをぜんぶ言うぞ!」という構えがおよそないことだ。「オレの話を聞け!」というようなオレオレ性もない。「外伝」と銘打ったのもそのためだろう、著者は「月刊宝石」の編集者として晩年の深沢から原稿をもらった人だが、自身の「深沢体験」の他に、新聞や雑誌で報道されたこと、関係者のコメント、噂、記憶などを切り貼りのようにしてつなぎあわせ、コラージュ風に深沢七郎という人物を浮かび上がらせるという手法になっている。中心は過去形の思い出語りであり、言ってみれば、壮大な「後日談」。本全体に「あとがき」のような風情がある。そのゆるさがいい。ジャカ♪ジャカ♪ジャカ♪と音楽が聞こえてくる中で、話を聞いているような気分で、まさに居酒屋風の語り。少なくとも本書の四分の三くらいは、そんなふうにして過ぎていく。
深沢は山梨・石和の出身。その原点は音楽にあった。中学でギターを覚えると、クラシックからロックまでカバーし、25歳ではじめて個人リサイタルを開く。ギター奏者としての自分に深いこだわりがあり、リサイタルもその後38歳まで18回にわたって開かれつづけた。35歳のときに最愛の母が死去。深沢は四男だったが、癌を患った母親に付き添って介護を続けていたのであった。
この母の死を契機に深沢は故郷を離れ、バンドに加わったり行商をしたりしながら各地をまわり始める。そんなある日、彼のリサイタルを観て興味を持った男がいた。日劇小劇場の丸尾長顕である。丸尾はギタリストとして深沢をスカウトする。この丸尾との出会いが深沢の運命を変えることになった。日劇小劇場は日劇ミュージックホールの前身でストリップ専門だったが、丸尾はここでストリップの演出を手がける一方、「歌劇」の編集長もしていた。丸尾の指導の下で深沢は、「楢山節考」を書き始めたのである。
その後の深沢の人生はよく知られた通りだ。丸尾の丁寧な指導の下に完成した「楢山節考」は第一回中央公論新人賞に応募され、伊藤整、武田泰淳、三島由紀夫という審査員の全員一致により当選が決まった。三島由紀夫をして「こわい小説を読まされた」と言わしめ、うるさ方でならした正宗白鳥が「人生永遠の書として必読すべきもの」と激賞した。
しかし、鮮烈なデビューを果たした作家深沢七郎は、まもなく禍々しい事件に巻き込まれることになる。あの「風流夢譚事件」である。『中央公論』1960年12月号に載った深沢の「風流夢譚」が天皇を愚弄していると怒った右翼少年が、中央公論社長宅を襲いお手伝いさんを殺害、夫人にも重傷を負わせる。はじめは脅迫など相手にしていなかった深沢も、すっかり右翼の攻撃におびえるようになり、全国各地を転々としながら「逃亡生活」を強いられることになった。中央公論社はお詫びの社告を載せ、嶋中社長も「あんなくだらない小説を自分は載せる気持ちはなかった。編集長のミスだ」とのコメントを出す。編集長も解任。
こうして見ると、たしかにこの事件には政治性や社会性が目につく。「言論の自由」から「天皇制」に至るまで研究者が飛びつきそうな話題ばかりだ。しかし、肝心の作品はどうだろう。「風流夢譚」の掲載された『中央公論』のバックナンバーの頁を、筆者はかつてある市立図書館の薄暗い書庫でどきどきしながらめくったのだが、う~ん、正直言って拍子抜けであった。「楢山節考」はたしかにすごい。しかし、「風流夢譚」はどうだろう。果たしてこのために人が殺されるほどの作品なのか。
そういう事情も間違いなく関係したのだろう、受難の作家に対する世間の反応は今ひとつちぐはぐなものだったようだ。弁護する批評家作家ももちろんいたが、今ひとつ歯切れが悪い。実際、中央公論社の対応に代表されるように、その後、各社とも右翼に対してはかなり神経質な対応をとらざるをえなくなる。その傾向は今に至るまで続く、と新海は指摘する。
しかし、深沢はこの事件を契機に生涯の友と知り合った。「ヒグマ」こと森兼宏と「ヤギ」こと深谷満男である。放浪をへて埼玉菖蒲町に落ち着いた深沢は、このふたりに助けられながら「ラブミー牧場」をつくった。ラブミー牧場以降の深沢は、あいかわらずの破天荒な生活ぶりとはいえ、デビュー期のような派手さは少しずつなくなっていく。本書の中でもこの時期の深沢を描いた部分はほほえましい牧歌性をたたえ、著者の作家に対する敬意と愛情のあふれた、一種の〝賛歌〟となっている。
それが、である。第8章から話が急に変な方向に動き出す。「突然、Aと名乗る男からの電話」などという、思わず「なになに?」と身を乗り出さずにはおられない剣呑なセクション見出しがあって、「A」なる人物が登場。すべて深沢がすでに亡くなってからの話なのだが、このあたりから作家の死後に残された人物たちの、さまざまな意味での跡目争い・遺産争奪戦が繰り広げられることになる。これこそほんとうの「後日談」なのだが、そこではどうもあまり格好良くないというか、いや~な匂いの漂う出来事がいろいろと起きた。著者もそこに巻き込まれることになる。
新海氏は白黒はっきりさせて論じたり、声高に何かを主張するタイプではない。そのかわりに、いかにも編集者らしい忍耐強さと、「目」を持っている。その「目」が、輝かしい天才的な部分を持ちながらも、きわめていい加減でいかがわしいところもあった深沢七郎という男の残した、決してさわやかではない後味をあますところなく語りの中でとらえているのである。だから、本書の最後の四分の一はきわめて〝苦い〟。
おそらく著者はそのような部分を書きたくない気持ちもあったのだろう。「Aと名乗る男」などという登場のさせ方からして嫌悪感丸出しなのに、その「A」の記述はどこか小出しというか中途半端。嫌々ながら書いているのである。しかし、実は大部分を占める「深沢七郎賛歌」の部分よりも、この最後の四分の一の苦い部分こそが、本書のもっとも文学的なところであると筆者は思った。
何人かの人物が出てくる。小さい頃、近所の深沢にギターを習ったという元自衛官は、誰も来ないような田舎で、自宅の一部を改造して深沢七郎の記念館をつくった。妻と離婚した後は、スーパーで残業をこなしながら家のローンを払いつづける。それでも記念館は守った。「ヤギ」は、「ヒグマ」が恋人をつくってラブミー牧場を去った後も、ひとりで老いた深沢の面倒を見続け、太ももから内股からときに陰部に至るまで、深沢にマッサージを施してやったりした。「ヤギ」は深沢の養子として著作権を相続するが、深沢の死後、四〇代にして精神状態が不安定となり、極度の不安と人間不信から印税の受け取りすら拒むようになる。そのせいもあって以降、深沢の著作物の刊行は困難を極めることになった。
そして問題の「A」である。「ヤギがおかしい」という噂の流れる中、「A」はラブミー牧場に残された深沢の遺品を安い値段でごっそり買い取る。井伏鱒二から届いた、深沢への弔文まで含めてありとあらゆるものを持ち去った。そして山梨の笛吹市の役場と交渉し、この遺品を元に文学館を建設してその館長におさまろうとする。格安の公営住宅付きである。しかし、きまぐれな「A」には粘着質なところもある一方で、理解しがたい奇行も多く、最後はまとまりかけた交渉をご破算にしてしまう。そのあたり、事実関係の不明瞭さともあいまって、忸怩たる思いの著者が必死に「A」に対する感情をこらえながら書いているさまが伝わってきて、たいへん引き込まれる。
舎弟のような若い男二人を従えて埼玉の田舎で牧場をやった深沢。当然そこからは「同性愛説」めいたものが飛び出してもおかしくはない。女性やセックスについての発言も旺盛だった深沢だが、「深沢は欲望の大きい人だった。欲望が大きすぎてぼくには応えられなかった」(162)という「ヤギ」の発言は意味深長に響く。しかし、新海氏がするのはせいぜい第7章に「欲望の大きい人だった」というタイトルをつけるだけで、よけいな推論や断定には走らない。深沢が少年と一緒に風呂屋に行きたがり、「まえをだせ」といって陰部をいじったというような話はあってもそれ以上は踏みこまない。そこがいいのだ。白黒つければいいわけではない。人間のセクシュアリティというのはたいへん微妙なものだ。その微妙さがあるからこそ、「楢山節考」のような作品が生まれえたのである。そのあたりをとらえるバランス感覚はやはり編集者ならではだな、と雑多な音楽の鳴り響くかのような語りを読みながら思ったのである。