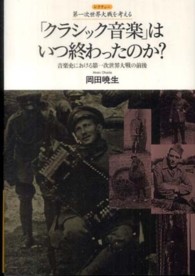『「クラシック音楽」はいつ終わったのか?-音楽史における第一次世界大戦の前後』岡田暁生(人文書院)
「王様と戦争」の歴史にかわる、社会史や全体史の重要性が唱えられて久しい。しかし、ちょっと考えてみると、「王様と戦争」を中心に語ってもかまわない、いや語った方がいい時代や社会もあれば、そうでない時代や社会もある。「王様と戦争」より社会史や全体史のほうが、その時代や社会にとって重要な意味をもつことを理解しなければ、歴史学としては皮相なものに終わってしまう。本書で、著者、岡田暁生が音楽史を扱うのは、そんな皮相なものではなく、王様より市民・国民が主体となった第一次世界大戦の前と後の音楽を通して、時代や社会が見えてくるからである。
長い19世紀を通して成立した市民社会が行き着いた先は、総力戦というなにもかもを「暴力」で打ち壊す大戦争であった。音楽も例外ではなかった。「この戦争で生じた社会の根底的な再編成が、一八世紀後半の啓蒙の時代以来のインテリ・ブルジョワ文化の没落をもたらし、さらにはファシストとボリシェヴィキ革命の温床になった」。そして、「一九世紀市民社会が作り出したクラシック音楽の語法・美学・制度とは決定的に違った音楽」が、第一次世界大戦前後に登場した。
「第1章 戦争の「前」と「後」-音楽史の亀裂としての第一次世界大戦」の5つの節のタイトルをみれば、いったいなにがおこったのか想像できる:「1 アヴァンギャルドの誕生」「2 アメリカ・ポピュラー音楽の勃興」「3 録音音楽の時代」「4 音楽における国際主義」「5 国有化される音楽?」。そして、第2章で戦前、第3~4章で戦中、第5章で戦後について、もうすこし詳しくみていく。
「第2章 モダニズムからアヴァンギャルドへ-大戦勃発前に起きたこと」では、伝統的な音楽が完全に否定された例として、「「ド」の音/「ドミソ」の和音」をあげている。従来、「曲の途中でどれだけ不協和音を使ったとしても、必ず最後はドミソという協和した響きに戻って終わる」ものが終わらない。著者は、「絵画とはキャンバスに絵具で様々な事物を描いたものである」とか「文学とは意味のあるセンテンスを組み立てて書くものだ」といったことと同じくらいに自明の法則だったものからの逸脱・解放だという。
「第3章 熱狂・無関心・沈潜-戦中の音楽状況」では、戦争が長期化するに従って、音楽家たちの戸惑っていく様子が描かれている。「大戦が勃発したとき最も熱狂したのは、いわゆる知識人たち」で、「文化の力で現実政治を動かすことが出来ると、大真面目に信じ」、「精神文化によってこの未聞の大戦争を勝ち抜く」と、音楽に課された「国民を励ます」という役割を果たそうとした。しかし、現実には、知識人たちは「文化の絶望的な無力」、「偏狭なナショナリズムの愚かさ」を思い知らされることになり、「個人の刹那の感情を超えた客観性を追求する必要性」を感じることになる。
そうしたなかで、「第4章 社会の中の音楽-パウル・ベッカー『ドイツの音楽生活』をめぐって」では、「音楽は社会が作る」というテーゼが議論される。ベッカーは、つぎのように嘆く。「音楽には常に社会的要素が不可欠であり、かつては音楽の注文主であった教会や王侯が、その役割を担っていた。だが今や音楽家と社会との間に、創造せず媒介するだけの、エージェントが割り込んできた。彼らは音楽を商品としてその利益を中間搾取しているだけであり、様々な娯楽音楽を人々のニーズに応じて提供することでもって社会の一体感を分断してしまい、社会全体に呼びかけるという音楽本来の使命を見失わせるに至った。社会は享楽を求める者、無関心な者、教養を求める者へ分裂し、音楽家は利益に関心がある諸グループへ解体し、仲介業者の支配は音楽家として本来の使命を忘れさせた」。そして、「大戦の最大の原因ともなった一九世紀ナショナリズムを克服する必要性」を説き、「音楽は社会が作る/音楽が社会を作る」「音楽は人々が作る/音楽が人々の絆を作る」を主張した。
さらに、「第5章 音楽史における第一次世界大戦とは何だったか-戦間期における回顧から」では、「行動する音楽」の美学が議論される。戦後流行るのが、「ジャズやキャバレー・ソングだが、近代社会ではほとんど見られなくなった労働歌、あるいは中世のモテットなどにも同じ特徴が見られる。そもそも本来の音楽とは「する」音楽であって、近代芸術音楽のように身体も動かさず粛々と傾聴する音楽の方がよほど特殊なのだ」という「ブルジョワ資本主義批判としての一九世紀音楽批判」を取りあげている。戦争を通して、「人々を集団的な死に向かわせる程の力を音楽は持ち得る、ただしそれは国歌や軍歌であって、決してオペラや交響曲ではない」ことを、人びとは学んだ。著者は、この章を「この苦い事実に一体どういうスタンスを取るのか。これこそが、音楽と真剣に向き合おうとする人々に対して第一次世界大戦が突きつけた、最大のアポリアであったかもしれない」と結んでいる。
そして、著者は最後に「あとがき」で、「第一次世界大戦と音楽」という主題への課題を、つぎのように述べている。「第一次世界大戦からの精神的武装解除として一九二〇年代の音楽を考えるとき、とりわけ重要になってくるのは、音楽家たちの「内面生活」を、第一次世界大戦をコンテクストとして、読み解く試みであるはずである。とはいえ、「内面」を推し量るためには、状況の「外面」の把握がやはり不可欠だ。第一次世界大戦中の各国における音楽生活の現実。前線においてはどうであったか。銃後においてはどうであったか。総動員体制の中で音楽はどう位置づけられていったか。そこで音楽家たちはどういう問題に向き合わねばならなかったか。しかしながら、これらの問いに答えてくれるような文献は、今のところ皆無だ。従来の二〇世紀音楽研究において第一次世界大戦は、やはり一種の盲点になっていたのであろう」。「本書は、「第一次世界大戦というコンテクストを組み込んでみると、一九一〇/二〇年代のヨーロッパ音楽史がどう見えてくるか」についての、試論にすぎない」。
このヨーロッパ音楽史が見えてきたとき、第一次世界大戦の前と後でヨーロッパ社会がいかに変貌したかが見えてき、さらにヨーロッパを越えて世界の音楽史や新たな時代・社会が見えてくることだろう。それが今日の社会に、どうつながるのか、重要な研究であることがわかったが、先は遠いようだ。本書は、開戦100周年にあたる2014年に最終的な成果を世に問うことを目標としている、京都大学人文科学研究所の共同研究の中間的な成果報告として刊行されたシリーズ「レクチャー 第一次世界大戦を考える」の1冊である。シリーズ名に「レクチャー」と銘打っているのは、全学共通科目で実際に講義した内容と重なるものが多く、本シリーズが広く授業や演習に活用されることを期待しているからである。「中間的な成果報告」であるだけに、著者自身解決不可能と思われるような難題を覚書きしているものもあり、共同研究という性格上ほかのメンバーに問いかけているものもある。シリーズ全体で、第一次世界大戦の総合的理解がより容易になり、本書を含めそれぞれの仮説がいっそう深められ、洗練された最終的な成果となることを期待したい(わたしも共同研究のメンバーのひとりなのだが、こんな他人事のように書いていいのだろうか・・・)。