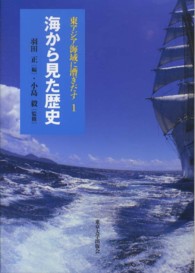『東アジア海域に漕ぎだす1 海から見た歴史』羽田正編・小島毅監修(東京大学出版会)
『海域から見た歴史-インド洋と地中海を結ぶ交流史』(名古屋大学出版会、2006年)の著者、家島彦一は、つぎのように明確に自らの立場を述べている。「海(海域)の歴史を見る見方には、陸(陸域)から海を見る、陸と海との相互の関係を見る、海から陸を見る、海そのものを一つの歴史的世界として捉えたうえで、その世界のあり方(域内関係)、他との関係(海域外や陸域世界との関係)を見る、などのさまざまな立場が考えられる。私の研究上の立場は、それらのうちの最後にあげたように、陸(陸域)から海(海域)中心へと歴史の視点を移すことによって、海そのものを一つの歴史的世界として捉えること、そして海域世界の一体性とその自立的な機能に着目すること、さらには海域世界から陸域世界を逆照射(相対化)することにあるといえる」。本書は、前2者の「陸(陸域)から海を見る、陸と海との相互の関係を見る」立場で書かれている。「海から見た歴史」にもいろいろあるが、本書は比較的閉じられた海域である東アジア海域を中心に扱っており、陸の関与が大きいため、この立場になったのだろう。
全6巻からなる本シリーズを読み終えたとき、「あなたの世界観はきっと変わっている」と、「刊行にあたって」の最後に書かれている。本シリーズでは、「八九四年の遣唐使廃絶から一八九四年の日清開戦にいたる」「一千年間を対象とし、ほとんど正式な国交がなかったにもかかわらず、多彩で豊富な交流の営みがおこなわれ、それらが日本で、〝伝統文化〟と呼ばれているものを生みだすうえで決定的な役割を果たしたことを明らかにしていく」という。
その第1巻「海から見た歴史」は、画期的な編集方針のもとに執筆された。編者、羽田正は、そのことをつぎのように「あとがき」で説明している。「研究会を頻繁に開いて、参加者全員が納得するまで徹底的に議論を交わし、いくつかの概念や歴史の見方、歴史叙述の方法について共通の理解を得ようとしたのである。そして、その理解にもとづいて、「東アジア海域」の過去を解釈し、叙述することを試みた。すでにさまざまな考え方があるところで新たな歴史理解や叙述方法を打ち出そうとするのだから、当然、研究会での議論はつねにおおいに白熱した。異なった見解を持つ研究者同士がどうしても譲らず、いささか険悪な雰囲気に陥ったこともあった。結果として、すべての点において、参加者の合意が得られたとは、残念ながら言えない。しかし、この方法を採用したことによって、参加者間での情報共有が飛躍的に進み議論がおおいに深まったことは間違いない。そして、一人の研究者による個別研究では到達できないようなレベルと広がりを持つスケールの大きな共同研究の成果を提示できたのではないかと思う」。
具体的には、つぎの4つの段階に分けて本書の執筆・編集作業が進められた。「1 プロローグと第Ⅰ部から第Ⅲ部という四つのパートについて、執筆と編集を担当する複数の編著者を決め、彼らが草稿を作って各部と全体の研究会に提出した」。「2 原稿の大筋が一応できあがったところで、四名の方に通読、コメントをお願いした」。「3 編著者グループから各部の主編者を決め、彼らが、各部の原稿のとりまとめを担当し、四つのパートを通読して、相互に記述内容の重複や矛盾、用語の意味などについてコメントし、各々の原稿の推敲をおこなった」。「4 四つのパートの主編者が、最終稿を仕上げて東京大学出版会に提出し」た。
このような「理系の研究でふつうに見られるような研究者の連名による発表方法」を採用した結果、本書は「海によって結ばれた、近代以前の東アジアの往来の歴史を、俯瞰的に見つめなおす」優れた概説書に仕上がった。その基本的なスタンスを、編者は「プロローグ 海から見た歴史へのいざない」でつぎのように述べている。「私たちの多くは、これまでなかば無意識のうちに陸の権力の視線で当時の歴史を理解してきた。しかし、海域の側から見れば、同じ対象が異なって見えるのではないか。陸中心の政権の目で記されてきたこれまでの東アジア史を見直し、海と陸をあわせた東アジアを想定し、その歴史を描いてみたい。海を真ん中においてそこに生きる人びとの目線で歴史を考えてみたい」。
本書で呼ぶ「海域」は、「ある区切られた範囲の海をさす自然地理的な用法とは異なり、人間が生活する空間、人・モノ・情報が移動・交流する場としての海のことをさしている」。そして、「本書の主要な舞台となる「海域」は、具体的にいえば、東シナ海と黄海を中心に、北は日本海・オホーツク海、南は南シナ海へと南北に連なるユーラシア大陸東辺の海である」。
本書は3部からなり、「少し変わった叙述スタイルを試みている」という。「歴史書によくある時系列に即した通史的な叙述ではなく、時間的に異なった三つの時期を取り上げて、その時代の海域とそれを取りまく地域の特徴をモデル的に再現しようとした。このような構成をとったのは、抽象的な概説ではなく、できるだけ、海の中心に視座をおいて周囲をぐるりと見回すパノラマのような具体的なイメージを読者に届けたかったからである。しかし、すべての時代にわたってそのような記述をおこなうには、紙数にも時間にも制約がある。そこで、この海域の歴史的特質が浮かびあがるように、三つの「百年間」を選びだして、それぞれの時代の特徴や多様性を具体的に描き出してみようというのである。このような手法は演劇ではよくみられる。本書を三部構成の海から見た歴史劇と見立てていただくのもよいだろう」。「三つの「百年間」とは、次の通りである」。「第Ⅰ部 一二五〇年-一三五〇年 ひらかれた海」「第Ⅱ部 一五〇〇年-一六〇〇年 せめぎあう海」「第Ⅲ部 一七〇〇年-一八〇〇年 すみわける海」。
さらに「本書では、三つの「百年間」を叙述するにあたって、海から眺める視角やものさし、叙述の流れなどを、できるだけ揃えることにし」、「まず、各部の冒頭には「時代の構図」が置かれ、それぞれの「百年間」の海域の位置づけと特徴が述べられる。つづいて、「人」がテーマとなる。私たちは海域と関わった人びとを、(1)政治権力やこれと密接な関係をもつ人びと、(2)航海や貿易と関わる人びと、(3)沿海で暮らす人びとの三つの範疇でとらえることにした。それぞれのグループが海域の歴史の展開にどのような役割を果たし、どのように関わったのかが説明され、また、各時代に海域交流の舞台となった港町とそこでの貿易の実態や「国外」から来た人びとの存在形態や権力による管理などの特徴についても述べられる。次は「モノ」だ。海上を運ばれたモノの多様性や時代的特徴を明らかにし、モノの観点から、各時代の東アジア海域の経済面での特徴が論じられる。最後は「情報」である。技術、学芸、美術、信仰、思想など、広い意味で「情報」に関わる要素の受容や拒絶の諸相が取り上げられ、それぞれと東アジア海域の歴史との関わりが説明されることになる」。
本書から「陸の世界から見えにくい」海域を、明確な問題意識をもって「陸地人の目線・文脈にそって書かれている」史料を丹念によみ、再構成することによって、その内実や「陸域」との関係性を具体的に明らかにしようとしている。「海域に生きる人びとの権力への帰属意識や「よそ者」との距離のとり方は、陸の人びとと同じだったのだろうか。「家族のために汗をながす」漁師や船乗りと、「人殺しをものともしない」海賊や兵士はどういう関係にあったのだろうか」という問いにたいして、「海域を中心に据えた歴史、すなわち「海から見た歴史」」を明らかにして答えようとしている。その試みは、本書の設定した「海から見た歴史」において、現在の研究成果を存分にいかして、成功しているといっていいだろう。読者の世界観も変わり、学ぶことも多かっただろう。
本書から、陸の人びとが海を媒介にして、あるいは海と接点をもつことによって明らかになった「海から見た歴史」を、さらに発展させ、冒頭で示した家島のいう「陸(陸域)から海(海域)中心へと歴史の視点を移すことによって、海そのものを一つの歴史的世界として捉えること、そして海域世界の一体性とその自立的な機能に着目すること、さらには海域世界から陸域世界を逆照射(相対化)すること」へと考察を深めていくためには、海域を主体性をもった空間として研究している地域研究者や自然科学者との共同研究が必要になるだろう。そうすることによって、陸の人びとが海と接点をもったその先の海域世界が姿を現してくるだろう。また、本書はあくまでも、人間中心の歴史である。鶴見良行の『ナマコの眼』(筑摩書房、1990年)のような視点が加われば、陸の海商が手に入れた海産物や林産物、中国で南海の物産と呼ばれた商品が、どのような環境(自然や社会)のもとで収集(生産)され、運ばれ、海商の手に届いたのかも、その一端がわかってくるだろう。領域・領海を近代国民国家の1要素と主張する「紛争の海」の危険性から解放するためにも、陸から離れた共存・共生する海の主体性を語る歴史観が必要になる。