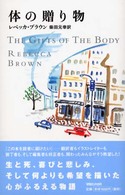『体の贈り物』レベッカ・ブラウン[著] 柴田元幸[訳] (マガジンハウス)
「ケア小説における引き算の効果」
高校の友人で最近はケア関係のライターやっている石川れい子から、『家庭の医学』を薦められたのが、レベッカ・ブラウンを知ったきっかけ。その時はただぱらっと見ただけ。正直言えば、介護事業をしている私が人様の介護話を読んでも楽しいかなあと思ったりしてた。当事者にとって良い編集者やライター、学者とは、啓発的で教育的な友人であって、常日頃からオルグすべき作家を紹介してくれたり、新刊を送ってくれたりするのだ。ありがたいことに。
ただし、不勉強な当事者の場合、貴重で無視できないはずのアドバイスの多くは日々の雑事の後回しになってしまうのだが、やっと芽が出たから、悦べれい子。レベッカ・ブラウンは私も「良い」と思う。
この種の小説の多くで、ケアラーの感情労働がテーマになり、要するに私たちにしてみれば、何かが過剰に描かれるのが常である。それが体験者にとっては重苦しい。また、病人話も大方がそう。『モリー先生との火曜日』も大変に評判が良いのだろう。でも私には辛い記述が多かった。というのも一般読者と違って私たちは行間を、意図的に隠されたり事実や、盛り込まれた物語を読んでしまうから。それは裏読みといえばそうなのだろう。しかし、患者の体験、家族の体験、介護者の体験だけが、飾りなく描かれてもいいと私は常々思ってきた。
ここでレベッカは、エイズで死にかけている人たちとヘルパーのやりとりを描写しているが、ドラマティックな何かが起きるわけでもないし、病いの体験から何かを学べというわけでもない。西海岸の陽射しの差し込む白い部屋にやせ細った人が横たわっている。定時にたずねてくるヘルパー(作家)は、エンシュア入りのパンケーキを用意し、バスタブにお湯を張り、ハーブエッセンスを数滴落とす。ジャムと石鹸の香りに、嘔吐物と汗のニオイが混濁すると、窓を開けて空気を入れ替え、服を脱がせ風呂にいれて、丁寧に洗い、湯冷めしないようにしっかり毛布で包んで話を聞く。そんな介護の様子がリアルに描かれているだけであるが、文面では語られない情感は十分に伝わってくる。また、エイズ末期の者の生活も何通りも語られる。彼らは、UCS(アーバン・コミュニティ・サービス)のホームケアサービスを受けながら、ホスピスの順番待ちをしているのだ。それは長いリストのはずだが、自分の番は意外に早く回ってきてしまう。そんな彼らをホスピスに見送るヘルパーたちに神話などない。エイズ患者にとってのホスピスとは、ひっきりなしに友人が死ぬ場所、だから友人を作る気もなくなるような場所。一度入ったら二度と出てこられない場所、ただ死を待つだけの場所であるから。
私たちは、ホスピスや死をモチーフにした多くの名著に差し込まれた過剰な何かを、この小説を通して改めて知ることができる。余計な感情表現を一切排除した文体に光る何かも。