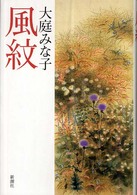『風紋』大庭みな子(新潮社)
「「ナコ」と「信さん」」
大庭みな子の小説には、長らくアメリカで暮らした女性がたびたび登場する。久方ぶりに帰国した彼女たちは、自分の生まれた国のありさまを不思議な風物を眺めるようにして見、切り離すことのできないいびつな根っこのような日本を自らの内に見出いだす。
みな子の作品は、登場人物たちの思惑と果てしのない述懐が複雑に絡み合い、戦争の傷と戦後の繁栄のなかで押し歪められた現代人の強烈な自我が幾重にも重なり揺らめく織物である。そこに、そんな女性のまなざしが織り込まれているのに出会うたび、思い出すのは小島信夫とその作品だった。
小島信夫が「アメリカ」に対して持つ、滑稽なまでに痛烈な敗北感は、大庭みな子には感じられない。夫の転勤にともない、十一年間アメリカに暮らした大庭みな子は、その経験からあらためて日本をみつめ、かの地で見聞し、感じたもろもろを作品のなかで展開させた。広島で終戦をむかえた大庭みな子は、原爆投下後の広島市に救援隊として動員された経験を持っているが、当時まだ少女であったみな子にとってそれは「アメリカ」がもたらした悲劇というよりは、彼女の生の途方もなく深い部分に暗い影を落としたようにみえる。
とりかえしのつかないものに、なお手をのばしては格闘しもがき、その自らのさまをこれでもかと書かせたのが小島信夫の「アメリカ」なら、夫の仕事の都合という、女性だけに許される理由でアメリカへ渡った大庭みな子は、それを何食わぬ顔で体のなかにとりこみ、自らの書くことを培っていった。
このふたりの作家のそれぞれの「アメリカ」に、男と女のどうにもわかちあい難いもののみかたや感じかたのちがいを見てとり、けれどもそれは対立するものではなく、ただ、ふたりの作家の一部分が、あるものの裏と表を介して密着しているかのようなイメージを私は持っていた。
大庭みな子の没後に出された本書は、三つの短編と六つのエッセイ、そして夫・大庭利雄氏のエッセイからなる。表題作の「風紋」は、小島信夫が倒れたという知らせを聞いたみな子が、小島信夫との思い出を綴ったものである。小島とみな子はしばしば訪問しあい、またよく電話で長話をする間柄だったというが、彼女の小島信夫への思いがこれほど深いものだったとは。みな子の作品からしばしば小島信夫を連想してしまうのは、アメリカという主題を透かしてみていたせいもあるが、みな子の小島へのこのなみなみならぬ熱情のためだったのではないかとすら思う。小島の小説にはみな子が実名で登場しているらしいけれど、みな子の小説のどこかにも小島は描かれているのだろうか。彼女の小説ではたいてい男は酷く書かれてあるけれど、どんなに酷く書かれても、小島はそれを優しく笑って許しただろう。
「この作品が雑誌に載るころはいったいどういう状況になっているのだろうか。小島信夫氏が倒れたという知らせに大庭みな子は狼狽している。」
差し迫った状態らしい「小島信夫氏」を、「大庭みな子」は案ずるというより、彼がこの世からいなくなってしまうことにただただ怯える子どものようだ。冒頭の「小島信夫氏」と「大庭みな子」は、彼女が言葉を重ねるにつれてその呼び名を変化させてゆく。「小島信夫氏」は「小島さん」、「小島氏」から「信夫さん」、そして「信さん」に。そして「大庭みな子」は「私」から、夫の「トシ」こと利雄氏との暮らしのなかでの自らの呼び名「ナコ」へと。
「小島さん」と「私」はまだ、共通の知り合いである編集者などもふくめた世界に住む、小説家同士のふたりである。「私」は「小島さん」との長電話で、文学や小説についてのさまざまを学んだが、
「ときには身辺にまつわる愛妻や息子さんなど家族についての悩み事などを、そんなに細かい個人的な事情を他人である私に話してもいいのだろうかと思うほどはなされた。もっともこの種の話は私だけにでなく、他の女性編集者にも同じようなことを聞かせていたというから、小島氏は他人にいろいろ語っている間に、次第に自分の作品を創りあげているのではと思うこともしばしばだった。」
「生涯人間のことを考え続け、人間の心理の不思議さに捉えられ、その心の動きの妖しさを追い続ける態度は世俗を超越して、ある意味では読者などは眼中にない傲岸さも備えながら、ひたすら彼独自の文学を追い続けた。その航跡が彼の作品群であり、彼は小説を書こうと思って書いたのではなく、思い続けたことを書いたものが小説になったに過ぎないというべきだろう。」
こうした「小島信夫論」から、夫婦同士で出かけた旅や小島の仕事場のある軽井沢での思い出をくぐりぬけ、「ナコ」の「信さん」への思いは深まる。
「ナコは信さんを何十年間も好きだったが、抱き合ったこともかければキスしたことさえなかった。今になってあんなに何度も会ってもっと近付く機会はいくらもあったはずなのに、そうしなかったのはどういうわけだろう、と不思議に思う。ナコはいつでも思い立つとのこのこと出かけてゆき『もっと強く抱いて頂戴』と言いたがっていた。けれど一度もそんなことを実際に言ったことはなかった。しかし、いつでも思ってはいた。」
もう意識のない相手に向けたこの告白を、みな子は夫のトシに口述筆記させているのである。脳梗塞で倒れて以降、ままならない車椅子のからだをまるごと夫に保護される生活のナコであった。巻末の大庭利雄氏のエッセイのなかで氏はこう書く。
「みな子の最後の短編『風紋』が発表されたとき、どこからか『こういう小島信夫氏へのラブレターを口述で文字化した夫の利雄はどういう気持ちでキーボードを打ったのだろう』という声が聞こえてきたが、そういう疑問は利雄にはピンと来ないほど、二人の間は世間の常識を離れた、馴れ合った夫婦関係になっていたようだ。みな子ははばかることも、はにかむこともなく小島氏への想いを口に載せたし、利雄は何の心のざわめきもなくキーボードを叩いていた。」
朦朧としてとりとめのない「風紋」には、みな子の小島信夫への思いと、夫利雄氏への思いが交錯している。しかしみな子はただ小島夫妻と自分たちという二組の夫婦によって、この人間関係の不思議を描いてみせただけなのかもしれない。
もうひとつ、エッセイとして発表された「企まない巧み」では、みな子小島の作品を、彫刻家の舟越保武の作品とならべてこう評する。
「舟越氏の作品には女性像が多いが、どの作品も具象のようで具象ではない、どこでも出会うようでいて、どこにもいない女性像は抽象の作品そのものの神秘性をたたえた魅力がある。その根底にあるのが彼の対象に対する貪欲なまでに鋭い観察眼であり、その結晶が透明に女神に近い女性像になっといえよう。(……)
小島氏も舟越氏に通ずる鋭い眼で常に人の生きるさまをじいっと観察している。お二人の作品に共通するものは一見具象性をもっているのに、それは実在するものではなくて、抽象性に満ちたものだということだろう。」
「具象性をもっているのに」「抽象性に満ちている」。小島信夫の小説は、その具象性と抽象性の双方に、ピントを合わせながら読まなくてはならないものだろう。どちらにピントを合わせるかによって、物語は悲しくも可笑しくもなる。いや、読み手はみな、それを自在に操ることなどできないのかもしれない。前々稿、『アメリカン・スクール』を読んでの私の船酔い感覚は、そのピントの合わせ方のつたなさのせいだったと、このみな子の巧みな評を読むとあらためて気づくのである。