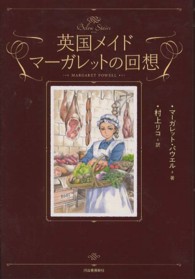『英国メイド マーガレットの回想』マーガレット・パウエル/村上リコ・訳(河出書房新社)
村上リコ『英国メイドの日常』では、さまざまな元メイドたちの回想録から当時の彼女たちの生活が紹介されていたが、そのなかでも英国でもっとも広く知られているのが、このマーガレット・パウエルの回想録である。
1907年、マーガレットは、英国サセックス州のホーヴという海辺の町で、ワーキングクラスのなかでもことに貧しい家に生まれた。父は雑役夫、母は日雇いの家事雑用をしていたが、父の仕事の減る冬場ともなると家族はその日食べるものにすら事欠く困窮ぶりだった。
長女だった彼女は、母に代わって朝食の支度やかたづけ、下の子たちの送り迎え、買いもの、なんでもやった。おいしかった母親の料理、路上での昔ながらの遊び、比較的余裕のあるときには映画にも行けたし、なにより楽しみだったサーカスには、空き瓶集めや肥やし拾いで小遣いを稼いで、兄弟みんなで出かけた。いつもお腹をすかせていたが、少女時代を振り返る彼女の筆は楽しげだ。
なにより彼女は学校が好きで、本をよく読み、また成績も良かった。奨学金にパスしたけれども、貧しい家計で、後にひかえる兄弟たちのいる身で進学するなんてとても不可能なこと。卒業したその翌週、十三歳のマーガレットは働きにでた。
通いの家事手伝い、菓子屋、ホテルのリネンルームなどいくつかの職場を転々としたがどれも長続きしない。そんな娘に母親は、それなら使用人になれと言う。しかも、裁縫が苦手なマーガレットは、キッチンメイドになるしか道がない。キッチンメイドとはコックの下で働く雑用係で、バトラー(執事)、フットマン(客の案内や給仕をする男性使用人)、パーラーメイド、ガヴァネス(女性の家庭教師)、上級下級のハウスメイド、庭師や運転手など、あらゆる家事使用人のなかでももっとも序列が低い。
キッチンメイドなんて、誰でもない人間。なんでもない存在。誰も話を聞いてくれない。ほかの使用人にすらこき使われる、卑しい女中【スキヴィー】でしかないのだ。
朝は五時半起き。レンジと暖炉に火を入れ、玄関の金具を磨き、石の階段をこする。それから家中の靴とブーツ磨き、ナイフの手入れ、使用人の朝食の準備。朝食がすむと、「階上の人びと」の食事の準備にかかる。
階上の人びとがとる朝食はいつでも大量で、客がいようといまいとそれは同じだった。ベーコン・エッグ、ソーセージ、キドニー、フィナンハドック(註・タラの一種の燻、スコットランドの名産品)やケジャリー(註・米、白身魚や燻製、ゆで卵などで作った英国料理)も。――この中のひとつか二つ選ぶんじゃなく、全部をいっぺんに出すのだ。
貧乏暮らしの父さんと母さんのことを思わずにはいられなかった。あの二人が食べられるのはトーストばかり。なのに、この大量の食事をとる人たちは、働いたことなんて一度もない。人生の不公平について考えずにはいられなかった。
そんな思いを上司であるコックに話しても理解してもらえない。
「だって、お金を持っている人たちがいなくちゃ、あたしらみたいな人間はどうなる?」
「でも、もうちょっと平等でもいいと思うんです。――もっと公正で――あの人たちにあんなにたくさんじゃなくて、私たちがもうちょっと多く持っていてもいいんじゃないかって。あなたと私はこんな快適さのかけらもない地下牢で働いてるのに、どうして階上では何もかもひとりじめできるんでしょう」
私はさらに言った。
「考えてもみてください、ミセス・マクロイ、結局、私たちの食事も住む場所も、報酬の一部ですよね。お金の形では月に二ポンドだけど、食事と宿泊で補うから安くしていいんだってことになっている。でも、宿泊っていったってメアリーと私が寝起きしてるみたいな屋根裏だったり、食事が貧弱だったり、ちっとも外出できなかったりしたら、公正な報酬とは言えないですよね?」
あんなに若い頃でさえ、私はこんなことを考えていた。
厳然たる階級社会で、マーガレットは自分の境遇を運命なのだと受け入れることなく、常に世の中の不公平と不平等について考えてつづけていた。
この回想の面白さは、なによりマーガレットの持つ、物事を冷静にみつめる眼による。「階上の人びと」はもちろん、ともに働く使用人たちについてもそれは同じだ。
コックの姉夫婦がマーガレットの職場へ食事をしにやってくることがあった。姉もある家でコックをしていて、夫のミスター・モーファットはそこの執事だった。そんなときは、階上の食事の終わった後、マーガレットはコックとその客の食事の給仕をし、その後に他の使用人たちの食事の準備をするので、皆から猛烈に怒られることになる。
給仕の順番は、まずミスター・モーファットからだった。ポートを注ぐときも彼が最初。彼は最重要人物だった。そして、自分の働いている家の高い地位を、その身体いっぱいに染み渡らせていた。そう、きっとこれが、世の人の言う、使用人の生きる目的というものなんだろう。
……ミスター・モーファットのような人は、当然ながら、雇い主側にはとても好まれた。使われる側の人格が使う人の中に完全に取り込まれてしまえば、主人たちは使用人の最大限の力を引き出せる。私が良い雇われ人についぞなれなかった理由はそこにある。私にとって使用人の仕事は、ただ目的を達成するまでの手段にすぎない。そのときの生計を立てる手段。そして目標は、可能な限り早く使用人の世界を抜け出すことだった。
ある家の主人は、使用人たちがみな寝静まった時間になってからたびたび呼び出しのベルを鳴らした。するとメイドがガウンを羽織って用事を仰せつかりに主人の寝室へ行く。ところで主人の本当の目的は、髪にカーラーを巻いたメイドの姿を見るため、彼はヘアカーラーフェチだったのだ。ネットをとらせてカーラーを触らせてもらうと、主人はメイドにチョコレートやストッキングをくれる。
私でも、ほしければもらえたかもしれない。呼び出しに応じたのが誰であろうと、ガウンとカーラーをつけたまま行きささえすれば、彼は気にしなかったからだ。でも私は一度も行かなかった。彼にカーラー姿を見られることが問題なんじゃない。もし相手が若い男性なら、そんな格好を見せるのは、絶対に避けたい。百年の恋も一瞬で冷めるし、未来の夫候補に逃げられてしまうだろうから。でも。ビショップ氏が相手だったら関係ない話だ。そうじゃなくて、私が応じなかった理由は、これもまた使用人という立場の下等性をありありと示す行為のひとつだからだ。家に招待したお客様を、カーラー姿で呼び出そうだなんて、彼は夢にも思わないだろう。でも使用人ならプレゼントで釣れば喜んで応じて当たり前だと思っている。けれど、この件に関してヒルダとアイリスは私に同意してくれなかった。
「ねえ、何が問題なの? 別に減るもんじゃないし、私たちだって得をするわけでしょ」
二人にもわかってほしかった。だって、彼女たちだってのし上がりたい願望はあるのに、こんなことを許していては、どこへも行けないじゃない。……
独立心に富み、誇り高く、正直なマーガレット。きつい仕事や不当な待遇に不平を鳴らすばかりではない。同僚のメイドの郷里に出かけたときには、都会と田舎の生活のちがいについて考え、自分は食べることができなくても、階上の人たちのための食材が、今とは比べものにならないくらい新鮮で質がよかった説く。また、自分についても客観的に考えることができる。だから当然、ユーモアのセンスもある。働きはじめはあまりのみじめさに泣いていた彼女だが、しまいには雇い主の小言に言われても、巧みに切り返すまでになった。
地元からロンドンへでて、そこでもメイドとして働いたのちに、マーガレットは晴れてコックとして雇われることになる。そして、いくつかの職場を経て結婚。この時代、女性が「使用人の世界を抜け出す」にはそうするより他ない。マーガレットは階級差だけでなく、性差についてもたひだひ考えた。
当時の世間では、男性が愛人を持つのはよくあることと見なされていた。でもね、もし女性がそんなことをしたら……。たしかに不公平な話で、女が男を囲う愛の巣など、どんなに作りたくても許されるものではなかった。女性が対象の「赤線地帯【レッド・ライト・デイストリクト】」もないでしょ? どうして男性だけが優位な性生活を送れるんだろう? 結局のところ、女の手に入るのは稼ぎの悪い夫だけかもしれないのに、当の夫は、男なら誰でも、ちょっとした料金で楽しませてくれるようなところへ行けるのだ。私たち女は恵まれない性だと思う。人生におけるあらゆる点で。
とはいえ、結婚をしてめでたしめでたし、でおさまらないのがマーガレットだった。
結婚生活は成功させたかったし、人生におけるそのほかのことにも成功したかった。そして、使用人の世界を抜け出すことだけをあまりにも考え続けてきたために、自分が家庭生活だけでは満足できないと気づくまでには時間がかかった。それに気づいたときには三人も家族が増えていたので、どんな願いもひとまずは忘れなければならなかった。いずれにしても三人の子どもの育児は、私にとってはフルタイムの仕事に他ならず、あの頃の私は文字通り骨の髄まで母親だった、と思う。
子育てを「フルタイムの仕事」と喝破しているのがなんとも彼女らしい。三人の男の子を育てながら、マーガレットは臨時のコックとしてふたたび働きにでる。仕事ぶりは評価され、紹介であらゆるディナーを請けおうことになった。
……私はこの小さな冒険を、本当に楽しんでいたのだ。お金に加えて、この仕事をすることで、今まで知っていたものとは異なる生活スタイルに対する見識を養うことができた。人びとは以前とはまったく違っていて、みんな親切だった。キッチンに出入りしては、まるで自分たちの一員のように話しかけてくれた。家事労働の世界は、たしかに変化していた。
息子たちが大学に進むようになると、マーガレットは彼らの会話について行けないことに気づく。そこで、貧しいゆえにできなかった勉強をしようと、大学の通信講座に学び、五十八歳にして、「Oレベル試験(普通レベルの教育終了認定試験)」にパスする。そして、本書をきっかけに彼女は作家の道を進むことになるのだ……とはいえそれはまだあとの話。
一世紀前の英国では働く女性の職業の筆頭だったメイド。その仕事と生活は当時のごくありふれた女の子のものだったが、マーガレットという個性にとってそれはとても強烈な体験として彼女の心に居座りつづけ、こうして一冊の本にまとめられた。マーガレットが1968年に本国でこの本を出版するまで、メイドという仕事とその生活が顧みられることはなかった。家事使用人を扱う歴史書には必ず引用され、ドラマや映画などで家事使用人と雇い主との生活を描いた「階上と階下もの」の原点ともなっているという。