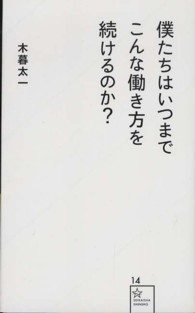『僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?』木暮 太一(星海社新書)
ホントに見事なタイトルである。思わず肯いてしまう人もいることだろう。
しかし本書は、ありがちな「転職」や「独立」や、ましてや「サボリ」を勧めるような類の本ではない。マルクス『資本論』を手掛かりに、労働の本質を捉え、「僕たち」の働き方を考え直そうと試みる、だいぶ射程の長い本だ。著者は『資本論』とロバート・キヨサキの『金持ち父さん 貧乏父さん』の二冊を深く読み込んで考えた成果だといっているが、『金持ち父さん』が料理のトッピングソースだとしたら、肝心の食材でより多くの血肉になっているのは『資本論』であろう。
著者は、例えばこんな問題を立てる。
・なぜ僕たちの「年収」は「窓際族」のオジサンたちよりも低いのか
・なぜ僕たちは「成果」を2倍上げても「給料」は2倍にならないのか
・なぜ僕たちの「人件費」は「発展途上国」よりも高いのか
給与が不平等で、成果に見合っていない、という巷間よくある問題だ。
だが、これらの疑問に対し、著者はマルクスの資本主義経済の分析を介して、企業は成果に対して報酬を支払うわけでない、と説明する。企業は労働者が生活していけるだけの社会的な「必要経費」しか支払わない。だから、二十代の独身者より、家族を抱えるオジサンたちの給料の方が高いのだし、発展途上国より生活費が掛かる日本で働く労働者の給料の方が高くなるのだ。
企業の利益は、労働者から「剰余的価値」を引き出すことで生まれる。「剰余的価値」とはマルクスの用語で、詳しくは本書の分かりやすい解説を読んでもらいたいが、労働者が「必要以上に働いた分」である。労働者は企業や組織の中で、限界ギリギリまで働かなければならない。だから、年収300万から1千万円の仕事に転職できたとしても、楽々と左団扇で暮らせるわけではないのだ。ネズミが車輪の中を走る「ラットレース」が永遠に続く。これが「搾取」である。
そこでマルクスは、労働者を搾取から解放するために「共産主義革命」を唱えた。一方、小粒になるが、キヨサキの『金持ち父さん 貧乏父さん』は「投資(不労所得を得ること)」の必要性を唱えた。この両者に対して、著者は大学を卒業する際、どちらも現実的ではない、と考えた。ここが著者の真骨頂だ。とっても現実的である。
著者は十年間、企業社会で働きながらこう考えた。
・「自己内利益」を考える
・自分の「労働力の価値」を積み上げていく(資産という土台を作る)
・精神的な苦痛が小さい仕事を選ぶ
売上300万で利益が100万の仕事と、売上1千万あるが利益が50万の仕事と、どちらが良い仕事であろうか。働く人にとっても同じだ。もらえる収入から「必要経費=精神的な肉体的な苦痛やストレス」を差し引いて、自分の中に残る「利益」を考えてみよう。「売上」が多いことは華やかに見えるが、それよりも内実の「利益」から捉える方が良いはずだ。
また、短期的な損益計算だけではなく、長期的に利益を生み出す土台=資産を見ることが大事だ。働く際にも「BS思考=貸借対照表的な考え方」を採ってみよう。一年間、すり減るように働いて100万円の利益を得ても、続かなければ意味がない。毎年すり減り続けるだけだ。それより、最初は少額の利益しか得られなくても、自分の中に利益が上積みされ、資産がかたち作られていくような働き方を心掛けることが大切だ。
業界を選ぶ場合にも、インターネット業界のような日進月歩で変化の激しい世界より、例えば建設業界のような変化が乏しいところで働いた方が、かえって資産を醸成しやすくて良いのだ、と著者は説く。良心的なアドバイスではないだろうか。
本書でいう「僕たち」とは、著者より若い二十代・三十代前半の若者を指しているのだろうが、ひと回り違う世代の評者にとっても、本書は説得的で、十分に魅力的であった。それもそのはず、本書でいうことは、街場のオヤジたちが言わずと実践してきたことなのだ。だが、こんなことを教え諭すオヤジたちがいなくなってしまった。なぜいなくなったのか。それはまた別の問題だが、本書は街場にあった真理を、丁寧に掘り出してくれた本なのである。本とはそういうものだ。多くの人におススメしたい。
最後に、本書は「次世代による次世代のための 武器としての教養」をうたう星海社新書の一冊になる。「旧世代」扱いされた読者には煙たい思いがするが、本当の狙いは違うだろう。この新書シリーズからは、他にも、山田玲司『資本主義卒業試験』のようなラディカルな本が出ている。『僕たちはいつまで』とはまた違った切り口で、資本主義社会での生き方を問い直す「前代未聞の哲学書」である。こちらも世代とは無関係に、併読をおススメしたい。
(カタロギングサービス部 佐藤高廣)