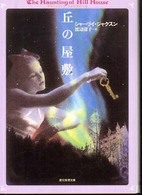『同日同刻----太平洋戦争開戦の一日と終戦の十五日』山田風太郎(ちくま文庫)
「表紙は原爆ドーム」
没後7年、山田風太郎の人気は落ちない。つい先ごろも『サライ』が「山田風太郎の恬淡哲学」なる特集を組んでいた。風太郎ぐらい寿命の長い作家は少ない。代表作である忍法帖シリーズが『甲賀忍法帖』をもって始まったのが昭和33年、なんと半世紀前である。ここに紹介する『同日同刻』のオリジナル版は30年ほど前の出版である(ちくま文庫に入ったのは2年前)。いま読んでもまったく古びていない。
山田風太郎という作家の人気の高さはどこに由来するのか。根っからのストーリーテラーとしての才能ということもむろんある。しかし、たぶん、風太郎を愛する者は、彼の作品すべてに通底する、ある種の世界観に魅せられるのだと思う。
忍法帖シリーズを読んだ人には納得されると思うが、それは忍者たちが奇想天外な忍法を使って壮絶な闘いを展開するだけの物語ではない。忍者たちは権力者たちの命令によって、自分の名誉をかけて忍法を駆使し、無残に、無意味に、死んでいく。忍法帖シリーズのほとんどの作品の末尾は、ただ、死、死、死。忍法のあまりのノンセンスぶりに呆れ、笑いながらも、このシリーズの基調を成すのは明るいユーモアではなく、凄絶な虚無である。身体の弱い医学生であった風太郎は出征することはなかったし、彼の作品に、具体的な戦闘シーンが描かれることはなかったはずだが、風太郎の夥しい数の作品を浸しているニヒリズムには、まちがいなく、戦争体験の影がある。
山田風太郎が無類の読書家であったことはよく知られている。NHKの特集番組で、風太郎の書斎が映ったことがあった。太平洋戦争についての本が本棚まるまる一つにぎっしりと詰まっていた。その読書体験の間接的な影響が忍法帖シリーズや『魔群の通過』のような作品にあるとすれば、直接的な影響がはっきり見て取れるのが、この『同日同刻』である。この作品は、1941年12月8日の1日と1945年8月1~15日の15日間について書かれた無数の文書や記録を多数引用して、太平洋戦争の全体像を描き出そうとするものだからだ。
今日は8月15日だから、玉音放送前後の記述を見てみよう。終戦の詔勅を出させまいとクーデターを企画する軍部、敗戦の責任をとって自害する阿南惟幾陸軍大臣の動向を記したあと、風太郎は、天皇の玉音放送を聞いた者たちがその時に何を考えたのか、何を思ったのかを引用していく。徳川夢声は「日本敗るるの時、この天子を戴いていたことは、なんたる幸福であったろうか。…この佳き国は永遠に滅びない!」と日記に書く。高村光太郎は「五体わななきてとどめあえず」と悲歌を歌う。83歳の徳富蘇峰は「永久に記念すべき悪日である」。内田百閒「熱涙垂れて止まず」。高見順「遂に敗けたのだ。戦いに敗れたのだ。夏の太陽がカッカと燃えている、眼に痛い光線。」そして、政府や軍部にいる人、有名作家たちと並んで、まだ無名の医学生だった自身の日記を素知らぬ顔で忍び込ませたあと、文章は一気に加速する。
斎藤茂吉は。---「たとえしのびこらえしのびて滅びざる命遂げむときおいたてつまる」
釈迢空は。――
「戦いに果てしわが子も聴けと思う かなしき御詔うけたまわるなり」
(中略)
荻原井泉水は。――
「ああ秋日面に厳し泣くべきものか」
ただしかし、久保田万太郎は、
「何もかもあっけらかんと西日中」
「×年×月×日、あなたは何をしていましたか。」というようなアンケート形式の雑誌記事はよく目にするところである。この『同日同刻』の読みどころも、その「編集」の巧みさによるところが大きい。上の箇所においても、同じ玉音放送を聞いた日本人たちの、さまざまなレベルでの感慨が、風太郎の編集的な手法によって、俯瞰から一挙に眺められている。夏のじりじりとした暑さのなか、森閑として、いっさいが失われてしまった空無感を凝縮したような万太郎の一節は、いささか紋切型にも見えなくはない、慟哭、悲しみの短歌や俳句と並べられてみると、いかにも異様であり、印象的でもある。風々院風々風々居士(風太郎の戒名)の世界観にも通じるような一節である。
この作品には、引用してみたくなる箇所がほんとうにたくさんあるのだが、どうしても逸することができないのは、広島に原爆が投下された8月6日である。風太郎がもっとも力を込めて書いたのもここではないのか。エノラ・ゲイから投下された原爆によるキノコ雲を描いた部分を引用してみよう。
一万フィートの円柱は、突如巨大な茸となり、その根もとの周囲三マイルを物凄い塵埃の雲が荒れ狂った。この茸はさらに高く大きく膨張をつづけ、四万五千ないし五万フィートの高さに達するまで昇りつづけると、紫色を帯びたクリーム状の数層の白い塊となった。「0の暁」のW・L・ローレンス(注・この人はニューヨークタイムズ紙の記者)は書いている。
「それは雲の上に屹立した山に、巨大な自由の神様が腕を空にあげて、人間の新しい自由の誕生を象徴しているかのようであった」
自由の名のもとに、多くの無意味な死体が積み重ねられるというのは、いまも変わることがない。風太郎もまた、アメリカ人のいう「人間の自由の誕生」の神像の足下に積まれた20万人の日本人の死体についての証言を、次々と引用していく。
「….みな一様に両腕を少し前にさし出し、前搏部から上に曲げ、手首から先を下に垂れて幽霊のようだ。その手からも皮膚がボロボロの衣類のようにぶら下がっている。それがのそのそと続いて来る。まったく地獄絵図であった」
また蜂谷博士は書いている。
「ピカの一閃に、強い者も弱い者もなくなってしまった。みな一様に精根をぬかれて黙々と郊外に歩いた。聴けばきまったように後をふりむいてアッチから来たという。前方を指さしてアッチへゆくという。出てきたところもいえず、行く先もいえない羊のようなものになってしまった」
引用文というものは、どんなにすぐれた書き手であっても、気持ちがふと緩んで、地の文からほんのちょっとだけ浮いて見えるものだ。ところが、引用文にはご丁寧なことにすべて出典まで記されているのに、不思議なことに、どの文章も風太郎その人が綴っているかのように見えるのである。それほどに風太郎は引用文を自分のものとしているということだ。
風太郎は、テキストのなかで、怒りの言葉を殆ど記していない。ローレンスが誇らしげに使った「自由の誕生」というような言葉だとか、エノラ・ゲイより先に広島に到達した気象観測機「ストレート・フラッシュ」の機体に「日本兵が下水のなかで溺れている」漫画が描かれていたというようなグロテスクなディテールを書き込みつつ、それと並べるようにして、死に行く者たちを記録した書き物を淡々と引用していくだけだ。禁欲的な書きぶりが逆に読者の心を激しく揺さぶる。「聴けばきまったように後をふりむいてアッチから来たという。前方を指さしてアッチへゆくという」という一節は、いま書き写していても、言葉を失う。過去も未来もなく、現在の悲惨のなかをただ歩くほかなかった被爆者を記述するこの箇所を電車のなかで読んでいて、筆者は落涙するほかなかった。
地獄と化した広島は戦後に奇跡的な復興を遂げる。その広島を舞台にして、忍法帖シリーズのごとき世界を描いた作品があることをご存じであろうか。それは深作欣二監督・笠原和夫脚本の「仁義なき戦い」のシリーズだ。ヤクザの抗争を描くこの作品群は、忍法帖がただの活劇ではないように、ただの暴力ヤクザ映画ではない。下っ端のヤクザたちの無意味な死と、暴力団の上のほうに居座って保身のみに汲々とする権力者たちとの対照を描くこの作品は、戦争をくぐってきた人間のみが描きうるような虚無感に浸されている。「仁義なき戦い」は作品の最後に、原爆ドームを映し出す。原爆ドームはこの映画が広島が舞台であることを示すためだけのものではない。それは、抗争で死んで行くヤクザたちを、太平洋戦争で亡くなった無辜の人々と重ね合わせていることの象徴として存在している。
風太郎の忍法帖シリーズはいろいろなところから再版が出ている。筆者がいま手元に置いているのは講談社の新書版で、装丁が横尾忠則のものだ。しかし、いま、この風太郎の忍法帖シリーズの表紙に筆者があしらってみたいのは、原爆ドームの写真である。この偉大な大衆作家はじつは昭和最大の戦争作家でもあることがこれによって明らかになるはずだ。忍法帖なら『風来忍法帖』を、時代小説はちょっと、という人ならば、太平洋戦争を描いた日本屈指の作品である、この『同日同刻』をぜひ読んで欲しい。この作品は、風太郎の、(隠れた)傑作中の傑作である。