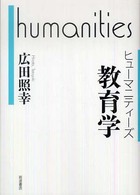『ヒューマニティーズ 教育学』広田照幸(岩波書店)
出だしをどうするか、迷った。帯の表も裏も使える。表紙の見返しも使える。「はじめに」にも使えるものがある。それだけ、今日の教育学は問題が多く、切り口も多いということだろうか。まず、これら4つを引用して、本書の概略をつかんでみよう。
まず、帯の表には、つぎのように書かれている。「普遍的な基礎づけを失ったいま、われわれは、希望を持って教育学を語れるのか。実感主義/体験主義を超え、教育学的思考の未来を切り拓く」。
裏は、もっと具体的である。「ポストモダン的な価値の相対化の地点から、「教育の目的」をたなあげにしてしまうのは、「教育学のシニシズム」を生んでしまう。……誰をも屈服させるような強力な「教育の目的」を、ある社会がもってしまうことも危ない。二つの極の間で、「教育の目的」をどう論じることができるのか。これからの教育学に求められているのは、これである。社会が多元的であるにもかかわらず、教育はある体系性や統一性をもって組織される必要がある-この難題に教育学者がどう取り組むのか、ということである」。
表紙の見返しでは、大きな視野のなかでの教育について語られている。「教育は社会のあり方やその変化と無縁ではありえない。その思想や制度は、近代の大きな変動のなかで変容を遂げ、経済のグローバル化や地球規模の課題が、現代の教育にさらなる変容を迫っている。未来の人間や社会のあり方を考え、そこに働きかけていく営みに向けた知として、いま教育学の何が組み換えられていくべきなのかを考える」。
「はじめに」では、本書をどのように読んでほしいのかが述べられている。「教育学をこれから学びたいと思っている人も、教育学を見直してみたいと思っている人も、一つひとつの細分化された専門領域の問題に閉じこもるのではなく、「教育を全体としてどう考えたらよいのか、教育学を全体としてどういう知として考えたらよいのか」といったことに注意を向けてほしい」。教育学は、「単なる教師養成の技術知としてではなく、人間や社会のあり方を深い次元で見つめ直し、社会の組み立て方や人間の生き方に示唆を与える学問としても発展してきた。その意味で、教育学は、総合人間科学でもあり、総合社会科学でもある」。
本シリーズ「ヒューマニティーズ」では、それぞれの学問の過去、現在、未来を語るということで、それぞれの章の副題を「どのように生まれたのか?」「学ぶ意味は何か?」「社会の役に立つのか?」「未来はどうなるのか?」「何を読むべきか」で統一している。
「一、教育論から教育学へ」では、「哲学を基盤に据えた一九世紀の教育学」から「実証科学をモデルとした二〇世紀の「教育の科学」」への変遷を、「議論の根拠はあやしいもの」から「危うさがつきまとっていた」ものの変遷ととらえて論じている。
「二、実践的教育学と教育科学」では、「よりよく教育を組織・実施するための知と、教育に関連した諸事象を科学的なルールに従って考察し、記述しようとする知」の「教育学内部の二つの知について」考察している。また、ここでは「教師になる人にとっての必要な教育学の知」と「一般市民(になる人)にとって、教育学を学ぶ意味」についても考察している。
「三、教育の成功と失敗」では、「一九世紀の末に登場してきた二〇世紀の教育学の本流を作る、進歩主義教育運動」が論じられている。この運動の根本には、「「子ども一人ひとりがちがっているから、それに応じた教育をする」という、革命的な考え方」があった。そして、それに対して登場したのが、「すべての子どもにバラバラなことをさせつつ、同時に、どの子も学習が進むような教授技術であった」。このような技術が必要になったのも、「すべての子どもが就学する公教育の制度が発達」したためである。以前は、「学校は困った子どもを追い出し(放逐)、子どもは学校がつまらなければ簡単にやめた(退出)」。公教育が、近代教育学にとって大きな問題となったのである。
つぎに大きな転機になったのは、「一九八〇年代から九〇年代にかけて広がったポストモダン論」で、「もともと脆弱だった教育学の認識論的足場を、根底から破壊することになった」。「四、この世界に対して教育がなしうること」では、困惑し迷走する教育学の現状から「未来」を考えている。そのポイントは、帯の裏に述べられているとおりであり、その解決のためには、表紙見返しにあるようなことを考えねばならなくなった。
考えるためには、当然、本をじっくり読むことが必要であり、「五、教育学を考えるために」では「何を読むべきか」、どう読むべきかが紹介されている。まず、「本をじっくり読むためには、線を引いたり、書き込みをしたり、付箋を貼ったりして、読みながら考えたことや感じたことを形に残しておくことが、とても重要である」と説く。つぎに「本を読み進めるうえで決定的に重要なのは、読む側が問題意識や関心を持っているかどうかである」。「また、本を面白く読むためには、ある程度の予備知識が必要なことも多い」という。
しかし、本を買って、「線を引いたり、書き込みをしたり、付箋を貼ったりして」じっくり読んだことのない者は、本を読むための予備知識もなければ、問題意識もない。大学4年生になって「「私は教育学の本は読んだことありません。大学に入ってからの自主的な読書は、ほとんど小説だけです」などと言い放つ者」は珍しくともなんともない。そう思っている大学教員は、超一流といわれる大学の教員を含めて当たり前で、小説を読んでいるだけ、ましだと思っているだろう。
まずもって、多くの学生は、教科書に書かれていないこと、学校で教えてくれなかったことを知らないのは当たり前で、恥ずかしいことではないと思っている。それだけで、日本の学校教育、家庭教育が失敗であったと言わざるをえない。学校教育は、自主的に学ぶための基本ときっかけを与える場にすぎないはずだ。それが目的化したために、学んだことが実生活、実社会でいかされない状況になっている。教育が生きる力になっていない。
本を読むことも、本書で書かれている卒業論文という課題に直面してはじめて読むことを知った学生は、まだ「幸運」である。卒業論文を課していない大学も多いので、本を読むことを知らない「学士」様は珍しくない。ほんとうは、高校で新書くらい読む習慣をつける教育をしてほしいのだが(もっとも最近の新書のなかには、これはちょっと…、というものもあるが)、そうも言っておれないので、大学で本を読むための予備知識や問題意識をもつための教育からはじめなければならない。本シリーズ「ヒューマニティーズ」も、本を読めない者(学ぶ姿勢ができていない者)には無用の長物となる。著者の言うように、「本当に奥が深い知や情報は、大学図書館の書庫や巨大な書店の片隅に眠っている。誰かに決めてもらったテキストや、誰かの講義から学ぶのではなく、自分で読むべき本を探して、本と自分とで対話をしていくことが必要である」。
著者は、「「教育学しか知らないバカ」にならないように、広い読書を心がけてほしい」と言い、「たくさんの講義や演習で教育学に関する勉強をしてきたとしても、授業で教わったものが「教育学」なのではない。講義や演習だけで身についた知識は、断片的で限界がある。その知識を活用しながら、自分自身で教育学の本を読むことによって、初めて教育学を深めることができるのだ」と説く。そして、「おわりに」で、「教育学内部でのタコツボ化が進む中で、無責任な御用学者や視野の狭い個別トピックの専門家ばかりが増殖している」現状を、「大問題である」と警告する。
本書は、おもに「教育学をこれから学びたいと思っている人」、「教育学を見直してみたいと思っている人」を対象に書かれている。本書が「ヒューマニティーズ」の1冊であるなら、わたしのようなヒューマニティーズの1つの歴史学を専門としている者が、議論に参加できるようなかたちでの問題提起もほしかった。これは、本書だけでなく、本シリーズの各巻に言えることで、「思考のフロンティア」シリーズのように、総括する別巻があると、「ヒューマニティーズ」としての各巻の立ち位置がよりわかってくることだろう。本書でも繰り返し述べられているように、教育学は教育学者だけで議論する時代ではない。教育学は、いまの時代・社会、これからの時代・社会に必要な知識・技術を提示してくれる学問なのだから。