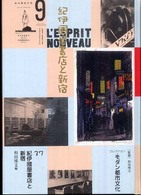『検閲と文学――1920年代の攻防』紅野謙介(河出書房新社)
「政治と文学」を論じ直すために(評者・成田龍一)
検閲とは、表現の自由の根本にかかわる問題である。思想史研究の鹿野政直は、『近代日本思想案内』(岩波書店、1999年)で、近代日本の思想の歴史的展開をたどるとともに、それを抑圧した法制に言及し一章を割いている。鹿野は、近代日本における思想表現がいかなる対抗関係のもとで実践されていったかという問題意識をもつが、紅野も同様に本書の副題を「1920年代の攻防」とし、表現をめぐる統制と抵抗を描き出そうとする。
近代日本の検閲の考察は、現象的な(ということは、傷を負った作品を主とする)言及が大勢を占めるとともに、いくつかの時期を焦点としている。近代の検閲の開始である「明治期」は発禁年表を含む詳細な考察があり、猖獗を極めた「昭和期」、さらに敗戦後「占領期」の(占領軍による)検閲にも関心が寄せられている。
このとき、紅野が着目する1920年代は、まだまだ手薄な領域である。この時期の雑誌を開いてみたときには伏せ字が多くあり、発売禁止となった書籍や雑誌が目につくにもかかわらず、なかなか1920年代の時期の検閲は主題化されなかった。
本書では、三つの主題が設定されている。第一は、検閲の概観である。紅野は、内務省警保局が実施する検閲に関わる法律として、出版法(1893年公布、1934年改正)、新聞紙法(1909年公布)を取り上げ、検閲の手順をたどってみせる。
検閲には「届出主義」(「事後の検閲」)と「検閲主義」(「事前検閲」)があり、この時期には「届出主義」が取られていた。処分として、行政官庁の「発売頒布禁止権」、司法官憲の「発行禁止権」があるが、いかなる手続きで検閲がなされ、処分を防ぐためにどのような出版社(編集部)との事前の措置がなされていたかを、あきらかにする。
同時に、「取締内容の曖昧さが担保」されてもいて、「恐るべき強面の検閲官は見られないが、検閲ではないと言いながら検閲係が存在し、編集者が「検閲係長代理」の綽名をつけられるような、奇妙で不思議な実態」がみられたともする。
こうしたなか、紅野は、出版社が校正刷り(二通)を内務省(警保局図書課)に提出し内々的に検閲を受け、その指示により掲載を案分する「内閲」に着目した。「べつなルール」として1920年代に「慣例として実施されていた「内閲制度」」を説明した個所が、おそらく本書の中心となろう。
「内閲」により、削除が「指示」され、予定目次や広告の段階でも掲載中止が「示唆」された可能性を紅野はみているが、出版社の側から見たときには、発売頒布禁止を回避するため、「削除」や「掲載中止」をおこなうこととなる。伏せ字は、編集部が行った「内部検閲、すなわち自主規制の結果」であり、「すでに内務省からの通達」があり「それを内面化することで導入された規制」としている。
しかし、こうした努力にもかかわらず、「予定外のアクシデント」ともいうべき事態がおこる。製本―納本をしてからの「発売頒布禁止処分」である。それが本書でのいまひとつの主題となるが、その前に第二の主題である改造社に触れておこう。
改造社の検閲が本書の主題となった背景には、改造社の史料が近年、大量に発見されたことがある。本書では、改造社の出版活動が述べられるなか、1919年4月に雑誌『改造』が創刊されたことが述べられる。
『改造』も検閲に関わる傷跡は少なくないが、1926年7月号の頒布禁止(二編の戯曲である藤森成吉「犠牲」と倉田百三「赤い霊魂」が筆禍にあった)に着目し、さらに1927年9月号の中里介山「夢殿」の該当ページ切り取りに言及する。
そして、第三に紅野は、頒布禁止に対抗する動きに着目する。執筆者の側も、統制と規制に甘んじていたのではなく、『新潮』合評会(金子洋文、佐藤春夫、広津和郎、山本有三)が声をあげ、文藝家協会により「発売禁止防止期成同盟」(1926年7月)が結成され、浜口雄幸・内務大臣を訪問、さらに内務官僚たちに面会したことが紹介される。
また『改造』1926年9月号に、「発売禁止に対する一抗議」とともに、特集「発売禁止に対する抗議」を掲げ、『新潮』も同様に、特集アンケート「発売禁止制度に対する批判とその対象」をおこなうなど、「文学、演劇、映画というジャンルを超えて、新たな運動が始まろうとしていた」ことに、紅野は着目する。
検閲との関係で作品を論ずるとき、(1)作者が負った傷として、見ること/表現することが規制され、相互批評もままならないことが指摘される。また、(2)出版社の傷も記される。そして、(3)「文学者たちが自分たちの権利の維持のために企業と交渉する」経験を有していたことが、対抗する運動の背後にあることをいう。いずれも的確な指摘だが、議論としては、読者がどのように傷ついたかも視野に入れ議論してほしかったと思う。
こうした三つの主題を貫く紅野の関心は、「政治」にある。『改造』1926年7月号の発売頒布禁止に関しては、まず「犠牲」の公演禁止があり(演劇の検閲は警視庁保安部保安課が担当し、事前の脚本の検閲であった)、次に雑誌の発売頒布禁止となる。
このことを指摘したうえで、紅野は、1926年7月に筆禍処分が集中する「ミステリー」を見出す。そして紅野は、これを疑獄事件の多発などを挙げながら「政党政治の迷走」という政治的な背景から説く。普通選挙の実施という、(成人男性たちの)国民化の政治状況のなかでの出来事とするのである。
そのため(といって、よかろう)、紅野の関心は、改造社が企画した「円本」の政治学的考察へと向かう。紅野は、円本の企画――32ページに及ぶ「内容見本」と一面を使った新聞広告の分析をおこなう。たとえば、円本は「文学の価値」を社会/政治のなかで「認知」させる試みであり、総ルビは「文学の民衆化」であり、「文学を「民衆」のものにすることによって恣意的な権力の介入に対して文学を確固とした地盤に打ち立てる」ものと解釈した。また、永井荷風は、そうした試みを見抜いていたともいう。
本書は、こうして、文学の「国民化」をめぐる「政治」の書となっている。紅野は「文学に介入してきた検閲制度と、それに対する広汎な抗議運動と内部対立」―「改正普通選挙法の施行を目前にして政治的主張を超えた幅広い読者の支持によって、文学の橋頭堡を示そうとした、そのような政治的パフォーマンス」を描くのである。
中里介山「夢殿」をめぐる動きは、こうした関心のもとで主題化される。おりから、「内閲」が廃止された直後であり、『改造』1927年9月号が「夢殿」のために検閲処分に会い、雑誌から「夢殿」の部分を切り取り、介山の連載は中断された。内閲廃止後の「新たなルールの適用」であるが、「民間」からの検閲の強化の圧力もあった時期の出来事と紅野は言う。
ふたたび文藝家協会により「検閲制度改正期成同盟」が結成されるが、文学者たちの一連の動きは表現の自由の擁護であり、「大正デモクラシー」のひとつの動きとなろう。「雑誌協会」「出版協会」も動き出し、「雑誌編輯者協会」が結成されるが、文藝家協会とは齟齬があり、検閲制度改正運動の亀裂―停滞もみられた。
このことを指摘したうえで、紅野はさらに、文学者たちの次々の代議士へ立候補に着目する(1928年2月の総選挙への立候補は菊池寛、藤森成吉。1930年2月は山本実彦、堺利彦、中西伊之助、室伏高信、1936年には中里介山が立候補した。また、応援者の文士も多数いる)。
すなわち、本書には1925年、26年に集中する「文学作品への検閲処分」、それへの抗議運動、円本を中心とする「文学の「民衆化」による広汎な読者層の獲得」、そして文学者たちの選挙への参加が記されることになる。
この時期は、さきの鹿野の提唱によれば「改造の時代」ということになる(『大正デモクラシー』小学館、1981年)。「大正デモクラシー」の後半期にあたり、それに先行する「民本主義の時代」を政治的に、より急進化する時期である。そのなかで、文学者たちも政治化していくことがここに明らかにされた。1920年代に着眼した、あらたな「政治と文学」にかかわる議論であるといえよう。
本書に対し、紅野は「いわゆる文学テクストの解釈や分析はほとんどない」が「あえて」その「方法」を採ったという。紅野は「文学者や出版人たちが立っていたその当時の場所であり、言説の場」を描こうとしたという。「彼らに見えていた現実の認識地図」。「文学の政治/経済的な文化基盤」を考えたいとした。
紅野の衒いであるように見えるが、しかし、ことは文学研究の方法と対象に関わっている。紅野のこの書を、あらたな「政治と文学」の書とするとき、かつての1930年代、また敗戦直後からの1940年代半ばから50年代にかけて、前衛党との関係で論じられていた「政治と文学」の議論とは、大きく趣きを異にしている。
彼我の「政治と文学」の論じ方――問題意識、対象、方法の差異に、80年間の推移を見出すことができる。1930年代から50年代(この射程は、さらに1970年くらいまで延ばすことができよう)までの議論と、21世紀初頭の「いま」とは「政治と文学」をめぐってある断絶が見られる。プロレタリア文学の再論など、再び「政治と文学」が論じられようとしているなか、本書の議論は見過ごすことはできない。
あらたな「政治と文学」の議論のために、本書はその領野を提示しており、ぜひ手に取っていただきたいと思う。