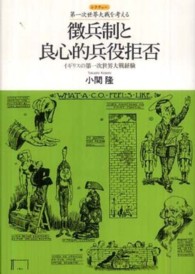『徴兵制と良心的兵役拒否-イギリスの第一次世界大戦経験』小関隆(人文書院)
シリーズ「レクチャー 第一次世界大戦を考える」の1冊である。帯に、「兵役拒否者は、独善的な臆病者なのか?」と大書してあり、その上に、「未曾有の総力戦を背景に、史上初の徴兵制実施に踏み切ったイギリス。その導入と運用の経緯をたどりながら、良心的兵役拒否者たちの葛藤を描き出す。」とある。どうやら「良心的」ということばがキーワードで、それがイギリスの特異性をあらわすようだ。
本題のイギリスの徴兵制の議論に入る前に、「はじめに」で恐ろしいことが書かれている。わたしたち日本人は、「第二次世界大戦」があるから、その前の世界大戦を「第一次世界大戦」と呼ぶようになったのだろう、くらいにしか思っていない。ところが、「イギリスの有力紙『タイムズ』には、早くも一九二〇年の段階で第一次大戦という表現が登場している」という。
著者、小関隆は、その理由をつぎのように説明している。「ヴェルサイユ講和条約が締結されたほんの翌年にこのことばが用いられた事実から読みとられるべきは、ヴェルサイユ体制による平和構築に関する悲観的認識、すなわち、あれだけの犠牲を出した戦争をもってしても火種が消えたわけではない、再び世界的な規模の戦争が起こることはおそらく避けがたい、といった絶望的な諦念であろう」。「終戦からほどなくして「第一次」と呼ばれてしまったこの戦争は、うまく終わらなかった戦争、次なる大きな戦争の予感を漂わせながらひとまず終わったにすぎない戦争と見なすことができるかもしれない」という。そして、「第一次大戦を理解するうえでは、戦間期および第二次大戦との連続性を念頭に置くことが決定的に重要になってくる」と、本書を読むにあたってのポイントを指摘している。「第一次大戦」という未曾有の体験をし、「第二次大戦」を予感しながら、人びとは「第二次大戦」を回避できなかったのだ。なんと、恐ろしいことだろう。
ほかのヨーロッパ諸国が、19世紀後半につぎつぎと徴兵制を導入していったのにたいして、イギリスは志願制を維持したまま第一次大戦に突入した。イギリス陸軍は、ヨーロッパ大陸諸国と比べて著しく弱体で、世界最強の海軍に頼り切っていた。大戦勃発直後は熱狂的に志願兵は増えたが、すぐに熱狂も冷め兵力不足に陥った。そのため、1916年1月27日に兵役法が成立した。が、「戦闘業務の遂行を拒む良心」にもとづく兵役免除の可能性を認める、いわゆる良心条項が含まれていた。「注目すべきは、ここでいう良心が宗教的なそれに限られず、思想・信条も含まれていること、そして、戦闘業務だけの免除のみならず、全面的な免除の可能性も留保されていることである」。
この「良心条項に基づく兵役免除を申請した者はトータルで約一万六五〇〇人(入隊者数の〇・三三%)」にすぎなかったが、社会への影響はけっして小さくはなかった。それは、反徴兵論者が、「イギリスの自由の伝統」というレトリックを持ち出して、ナショナリズムを刺激し、「大陸諸国に比べて徴兵制をもたないイギリスはより高度なのだ」と主張したからである。戦中の世論の大勢は「無責任な臆病者」というものであったが、戦争を忌避する言説が世論に広く受け入れられるようになる戦間期には、「反戦・平和の灯を守った人々として、彼らは称揚の対象にさえなった」。しかし、いっぽうで「筋金入りの平和主義者の多くが、戦間期にはいっさいの武力行使を否定していては現実に対処できないという考えに傾き、絶対平和主義の無効性を認識するようになる」という奇妙な現象も起こった。
戦間期の1920年4月にいったん廃止されたイギリスの徴兵制は、第二次大戦にあたって1939年4月に再導入の方針が打ち出されたが、反徴兵制運動は第一次大戦期ほどの広がりをみせなかった。その理由のひとつは、徴兵制の運用自体の寛容さにあった。そして、1960年に徴兵制は停止された。現実に大戦が起こらない限り、徴兵制が制定・維持されなかったイギリスで、志願制から徴兵制への移行が比較的すんなり実現した理由を、著者はつぎのように述べている。「志願入隊に任せていると、軍務に就くよりも国内での活動に従事する方が望ましい者たち、とりわけ専門的な知識や技能をもつ者たちが少なからず戦地に出てしまうことである」。「入隊率は社会的地位が上がるほど高く、しかも、士官の死傷率は兵卒のそれを上回ったから、人口比で見れば、階級が上であるほど犠牲者も多かった」。
イギリスの徴兵制が特異なのは、すくなくとももうふたつ理由があるように思える。イギリスが連合王国(グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国)であって、人びとが考えるナショナリズムがいくつかの層からなっていて愛国主義の捉え方が、そのときどきの状況によって変わったことが考えられる。このことについては、.著者のもうひとつのテーマである「大戦に際してアイルランドのナショナリストの多数派がとった戦争協力方針をめぐる諸問題」の研究に期待したい。もうひとつは、イギリス帝国がオーストラリアなどの自治領軍に加えて、インドなどの植民地軍、グルカなどの傭兵を抱えていたことだろう。現在、世界各地23,319ヶ所にあるイギリス連邦戦没者墓地委員会が維持管理する墓地には、これらさまざまな「イギリス兵」1,695,483人が眠っている。
本書から、著者が「はじめに」で書いた「第一次大戦を理解するうえでは、戦間期および第二次大戦との連続性を念頭に置くことが決定的に重要になってくる」意味が、よくわかった。そして、著者は、つぎのような文章で、本書を終えている。「世界恐慌の勃発、ナチズムの台頭、国際連盟の権威失墜、といった条件が出揃ってくる一九三〇年代のイギリスでは、軍備の拡張と軍事同盟の強化を求める声が平和主義のそれを最終的に圧倒してゆくことになる。ウェルズのいう「戦争をなくすための戦争」、換言すれば「最後の戦争」だったはずの戦争は、「第一次」大戦、つまり「新たな三十年戦争の第一段階」となってしまうのである。「ラスト・ウォー」の「ファースト・ウォー」への転化、第一次大戦にかかわる最大のパラドクスないし悲劇はここにある」。
因みに、戦争の呼称には注意を要する。国・地域や時代によって違い、意味があるからである。たとえば、日清戦争は中国では甲午中日戦争、日露戦争は韓国では露日戦争という。日本各地にある日露戦争記念碑で戦後すぐに建てられたものは、「明治三十七八年戦役」「明治三十七八年役」となっている。「支那事変」は1937年の廬溝橋事件が一般的になるが、28年の済南事件も事件後は「支那事変」とよばれた。中国では廬溝橋事件は七七事変、満洲事変は九・一八事変とよばれ、記念日には敏感である。
もうひとつ気になることが、「むすびに代えて」で、つぎのように書かれていた。「選挙権の拡大だけでなく、大戦を経験したイギリスがさまざまな領域で民主化を進展させていったことは間違いない。しかし、それは兵役をはじめとする戦争遂行への献身に対する報償の性格の強い民主化、いわば血で購われた民主化であって、血を流そうとしない者たちを容赦なく排除した。イギリスが再び世界大戦への道を辿ることを促す力は、こうした民主化のあり方の中に胚胎されていたといえるかもしれない」。これでは、「民主化」はファシズムと変わりないではないか!「第二次大戦」を回避できなかった原因のひとつは、民主化された社会が未成熟だったことにある。さて、いまの「民主化された社会」は、新たな大きな戦争を防ぐことができるのだろうか。その成熟度にかかっている。