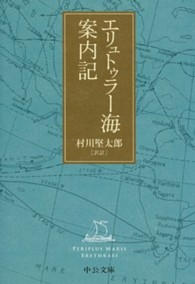『エリュトゥラー海案内記』 村川堅太郎訳註 (中公文庫)
世界史をとった人ならこの題名におぼえがあるだろう。エリュトゥラー海とはギリシア語で「紅い海」、紅海をさすが、東西の海上貿易がはじまると紅海につづくインド洋やペルシャ湾もエリュトゥラー海という言葉で総称されるようになった。
『エリュトゥラー海案内記』は1世紀の半ば――クラウディウス帝からネロ帝の御代――にアレクサンドリアのギリシア系商人が書いた実務本位の地理書で、紅海北端からアラビア半島を経てインドにいたる航路にどのような交易地があり、どのような商品が売買されているか、航行にはどのような危険があるかが記されている。
インド洋横断航路は南西の季節風の発見で可能になった。本書はその発見者はヒッパロスというギリシア人の舵手だとしているが(この季節風のことを「ヒッパロスの風」という)、フェニキア人やアラブ人がすでに発見していたという説の方が有力のようである。誰が発見したにせよ、プトレマイオス朝期にはエジプトとインドの海上交易がはじまっていたが、本格化するのはエジプトがローマに併合され、アウグストゥスの帝政がはじまってからだ。地中海世界にローマの平和が確立された結果、富裕層が増え東洋の奢侈品の需要が急増したからである。本書はまさにこの時期に執筆されたようだ。
東西交易というと陸のシルクロードが有名だが、交易量は海上ルートの方がはるかに多かった。冒険的な西方商人はインドの南端を越えてマライ半島まで船を進めていたことが確実視されているが(プトレマイオスの地理書は彼らの情報をもとに書かれたと考えられている)、本書の著者である無名氏はローマ交易の中心地だったインド西北部のバリュガザ(現在のバルーチ)までしか行かなかったらしい。
実際に訪れた土地については記述が詳しく生き生きしている。バリュガザの条を引こう。
ところでバリュガザのところの湾は狭いので大海から来た者にとり近づき難い。といのは右側なり左側なりに片寄ることになるからであるが、左側の方が別の側に較べれば楽に進める。即ち右側にはちょうど湾の入口に、マンモーニ村のところに当たってヘーローネーという険しい岩だらけの出鼻が横たわり、一方左手にはこれに向かい合ってアスタカブラの前面の岬があり、パピケーと呼ばれ、その辺の海流のために、また険しい岩からなる海底が錨を切り去るために停泊困難である。
湾内は浅瀬が多く航行が難しいので、王に仕える漁師がタグボートのような舟で出迎えにあらわれ、定められた船着き場まで曳航してくれるとある。こういうことは体験しないと書けないだろう。
一方、明らかに伝聞で書いたとわかる箇所もある。中国に関する条である。
この地方の後に既に全く北に当たって或る場処へと外海が尽きると、其処にはティーナイと呼ばれる内陸の大きな都があり、此処からセーレスの羊毛と糸と織物とがバリュガザへとバクトゥラを通じて陸路で運ばれ、またリミュリケーへとガンゲース河を通じて運ばれる。このティス地方へは容易に到達することが出来ない。というのは此処からは稀に僅かの人たちが来るに過ぎないから。其処は小熊座の直下に位し、ポントスとカスピアー海との最も遠隔の部分に境を接するといわれる。カスピアー海の傍らにはマイオーティス湖が横たわり、大洋に注いでいる。
ティーナイとは
本書は二千年前の西洋人の世界観をのぞき見ることのできる珍しい本である。本文は40頁ちょっとだが、見慣れぬ地名や人名(そのほとんどは史書に残らなかったローカルな支配者)ばかりなので、80頁の序論と140頁の註釈がついている。地名の考証や香料や象牙、犀角、珊瑚といった交易品の解説は推理小説的で面白いが、多忙な人には向かないかもしれない。
原著は奇書中の奇書だが、訳本が出た事情も異例である。「序」は校了直前に書かれたらしいが、その日付が昭和19年10月となっているのである。出版社からたびたび催促されたとか、註釈の組版で凸版印刷に面倒をかけたとあるから、空襲の激しい中、編集作業が粛々と進められていたことになる。
組み上がった活版はさいわい戦火にあうことなく昭和21年1月末に上梓の運びとなった。あの物資のない時代にこんな不要不急の本がよくぞ出版にこぎつけられたものだと思う。
先人の労苦に頭が下がるが、このような珍籍が安価な文庫で再刊されたのだから日本の出版文化もまだ捨てたものではない。