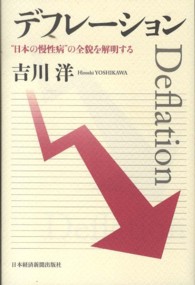『デフレーション』吉川洋(日本経済新聞出版社)
「デフレをどう捉えるか」
経済学はアダム・スミスの昔から優れて実践的な学問であったが、バブル崩壊後の日本経済が長いあいだ低迷し続けるうちに「デフレからの脱却」という課題が急浮上するようになった。だが、経済学者やエコノミストの見解が容易に一致しないように、デフレをどう捉えるかについてもいろいろな考え方がある。本書(『デフレーション』日本経済新聞出版社、2013年)の著者である吉川洋氏(東京大学大学院経済学研究科教授)は、わが国を代表するケインジアンとして知られているが、一読すれば、自説とは対立する理論や政策(現内閣の「アベノミクス」もそのひとつだが)との違いが明確となるような丁寧な叙述がなされているのに気づくだろう。啓蒙書の模範というべき好著である。
一昔前、インフレ抑制が重要な経済問題であった頃、アメリカの高名な経済学者ミルトン・フリードマンは、「インフレは貨幣的な現象である」としてマネーサプライの抑制を提言していた。もっと正確にいえば、マネーサプライを実質経済成長率の伸びと歩調を合わせて増やしていく「k%ルール」の提言だが、その理論的基礎は古くからある貨幣数量説の現代版に他ならなかった。貨幣数量説の思考法は、マネーサプライの増加は、短期的に雇用量や産出量に影響を与えることはあっても、長期的には物価の上昇につながるというものだったので、インフレ抑制のためにはマネーサプライの伸びを抑えるという政策が自然と導かれる。
ところが、いま問題となっているのはインフレではなく、その反対のデフレである。だが、このデフレ問題は、簡単にいえば、インフレ問題に対する貨幣数量説の思考法を逆にすることによって解決することができると主張する人たちがおり、いまやその勢力が現内閣の経済政策の舵取りにも影響を及ぼし始めた。吉川氏の理解もほぼ同じといってよい。
「多くのモノやサービスの価格がそろって下落し続けるデフレは『貨幣的な現象』である。だから、デフレを説明するうえで最も重要な変数はマネーサプライだ。こうした経済学の背後にある理論は『国際標準』の理論、『貨幣数量説』である。デフレを止めるために、日銀はインフレ・ターゲットを掲げてマネーサプライを増やせ、逆にいえば、デフレが止まらないのはマネーサプライが十分供給されていないからだ。」(同書、196ページ)
吉川氏は、たしかに、ゼロ金利でなければ、マネーサプライの増加が利子率の低下を通じて投資や消費を刺激し、景気にプラスの効果をもつことを否定しない。だが、ゼロ金利の状態ではそうではないという。「実際、これまでハイパワード・マネーあるいは貨幣数量を増やしても、それが実体経済にプラスの影響を与え物価を上昇させる、ということはなかった。マネーサプライの増加が十分でないとか、やり方が悪いというような議論は、説得力に欠ける」と(同書、197ページ)。
もちろん、量的緩和やインフレ目標を提言する人たちの理論的基礎はこれだけではなく、例えば、わが国でも人気のあるポール・クルーグマン(プリンストン大学教授)はもっと洗練されたモデルを提示している(注1)。クルーグマンの論文は、金利がゼロに近く、いわゆる「流動性のわな」(貨幣需要が利子率に関して無限に弾力的になる―もっと平たく言えば、貨幣愛が極めて強くなる状態)に陥った経済を解明したとされるものだが、吉川氏は、クルーグマンのモデルが次のような巧妙なトリックを用いていることを見逃さない。
「しかし、『現在』と『将来』という二つの期間からなる動学モデルであるクルーグマン・モデルでは、『現在』流動性のわなに陥っていたとしても『将来』は流動性のわなに陥っていないと仮定されているので、『将来』のマネーサプライを増大させる(より正確には、将来マネーサプライが増大するだろうという期待が持たれる)と、『将来』の名目物価は貨幣数量方程式に従い比例的に上昇する。つまり、将来マネーサプライが増大するという期待を生み出しさえすれば、期待インフレ率が上昇し、たとえ名目利子率がゼロであっても、実質利子率は低下する。実質利子率の低下により需要が刺激され、流動性のわなから脱却することができる――これがクルーグマン・モデルの論理である。」(本書、128ページ)
「期待」が景気の浮き沈みに大きな影響を与えることは間違いないが、クルーグマン・モデルのように、「将来」は流動性のわなには陥っておらず、マネーサプライと物価の間の単純な比例関係が成立しているという非現実的な仮定を置いている理論を信頼してもよいのだろうか。吉川氏でなくとも、誰もが抱く素朴な疑問だろう。
また、少し専門的になるが、吉川氏は、クルーグマンが最近の「マクロ経済学のミクロ的基礎づけ」に倣って、需要の「利子弾力性」の問題を「代表的」消費者の最適化(「異時点間の消費の代替の弾力性」)の類比で論じていることにも疑問を呈する。マクロはミクロの単純な合計ではないというのはケインズ革命の遺産であったはずだが、現代経済学の主流は、いつの間にか、この遺産を葬り去ったのである。この点はあとでまた触れることにしよう。
ところで、量的緩和やインフレ目標を掲げる人たちがマネーサプライの動きに注目しているとすれば、吉川氏は何に注目してデフレ現象を捉えているのだろうか。それは、端的にいえば、名目賃金の動きである。吉川氏は、10年ほど前、何をもってデフレと考えるかという質問に対して次のように答えたという。「たしかに物価指数はいろいろありますが、名目賃金が下がり始めるようなことがあれば、それはもう正真正銘のデフレーションです」と(本書、173ページ)。
かつては賃金には「下方硬直性」があると教わったものだが、1998年以降、先進国の中では日本だけ名目賃金の下落が統計データで確認されるようになった。97年には一連の危機(アジアの通貨危機、日本長期信用銀行や北海道拓殖銀行の破綻など)が発生していたことも見逃してはならないが、この前後に日本の賃金決定のメカニズムに変化が生じたという研究がある。すなわち、バブル崩壊後の不況と厳しい国際競争のなかで「終身雇用」がキーワードであった従来の大企業の雇用制度が崩れていき、「雇用か、賃金か」という選択に直面した労働者が名目賃金の低下を受け入れたのである。吉川氏は次のようにいう。
「名目賃金は『デフレ期待』によって下がったのではない。1990年代後半、大企業を中心に、高度成長期に確立された旧来の雇用システムが崩壊したことにより、名目賃金は下がり始めたのである。そして、名目賃金の低下がデフレを定着させた。」(本書、212ページ)
名目賃金(と生産性)の動きに注目して物価問題を考えるというのは、ケインジアンの正攻法だが、最近ケインズとともにシュンペーター研究にも打ち込んでいる吉川氏(注2)は、「デフレに陥るほどの長期停滞を招来した究極の原因」として「イノベーションの欠乏」を挙げている(本書、209ページ)。吉川氏は、『構造改革と日本経済』(岩波書店、2003年)以来、「需要とイノベーションの好循環」という視点から「需要創出型のイノベーション」の役割を強調してきたが、ここでもその立場は不変である。
さて、マクロ経済学のミクロ的基礎づけに関連して前に少し触れた点に戻ると、「全体は部分の単純な合計ではない」というケインズの視点から出発したマクロ経済学は、過去40年の間に一変し、いまや新古典派マクロ経済学が優勢になった(「合理的期待」理論、実物的景気循環理論など)。だが、吉川氏はそれを「進歩」だとは考えていない。とくに「問題は、特定の『資産市場』に適用したとき有効であるかもしれない合理的期待の概念を、無批判に、マクロ経済――しかも……そもそも期待が大きな役割を果たしているとは思えない労働市場、賃金――に適用したルーカスの理論にある」という(本書、214-215ページ)。
たしかに、資産市場や一次産品の価格は「期待」の影響を大きく受ける。だが、吉川氏は、ふつうのモノやサービスの価格や賃金決定に「期待」が関与する余地はないという。なぜなら、それらの価格は、ジョン・ヒックスやアーサー・オーカンが強調した「公正」の基準を満たすように決まるからである(本書を読むと、価格が生産費に利潤マージンを足すという「マークアップ」方式で決まることが念頭に置かれているようである)。それゆえ、吉川氏は、そのような当たり前のことを忘れてしまった現代経済学の現状を嘆くのである。
「こうしたことは、ヒックスやオーカンだけではなく、一世代前の経済学者はよく理解していた。『期待』を変えればデフレは止まる、と簡単にいう経済学者は、まさに合理的期待理論によって変貌した現代の『世界標準』にかなう経済学者たちである。ここで問題にしなければならないのは、そうした世界標準にかなう経済学である。」(本書、216-217ページ)
繰り返しになるが、「全体は部分の単純な合計ではない」というのがケインズ革命の遺産のはずであったが、現代経済学の主流は「マクロ経済学のミクロ的基礎づけ」を追究するあまり、この遺産を踏みにじってしまった。吉川氏も、「『マクロのことはマクロで』というのが、自然科学では確立された方法論であるのに、経済学では『ミクロの相似拡大』で『マクロ』を理解しようとしているわけだ」(同書、220ページ)というように、主流派に対して厳しいスタンスをとっているのがわかるだろう。
ところが、最近メディアにしばしば登場するアベノミクスは、本書の主張とは正反対の「世界標準にかなう経済学」と称する経済政策である。安倍総理の経済顧問のような役割を演じている浜田宏一氏(エール大学名誉教授)の『アメリカは日本経済の復活を知っている』(講談社、2013年)は、量的緩和やインフレ目標の必要性を情熱的に語っているので、本書とは正反対の視点に関心のある読者は手にとってみることをすすめたい。ただ、なんとも不思議なのは、吉川氏も浜田氏もともに、エール大学でジェームズ・トービンというアメリカの優れたケインジアンに学び、長いあいだ東京大学教授として日本の学界の発展に貢献してきた学者であるにもかかわらず、最終的に、このような見解の相違が生まれてしまったことである。経済学とは本当に面白い学問である。
1 Paul Krugman,"It's baaack:Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap," Brookings Papers on Economic Activity 2,1998.
2 吉川洋『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ』(ダイヤモンド社、2009年)を参照のこと。