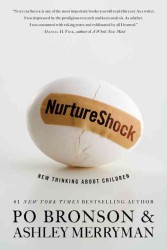『臨床の詩学』春日武彦(医学書院)
「なぜ詩と精神科の臨床現場は相性がいいのか?」
人に面と向かって「嫌いです」と言うことはないけれど、だれかと話していてそういう話題になることはあるだろう。しかも酒が入っていたりすると、「あの人、ちょっと苦手」と言うつもりがつい言葉の勢いで「あの人、嫌い!」と言ってしまったりする。その一言で舌に毒がまわり嫌いの度合いが高まることもあれば、反対に言葉の強さにはっとしてそんなに嫌いだっただろうかと反問することもある。かのように言葉には自立した力がある。発言した人の意識の流れを変え、相手との関係を動かしてしまうようななにかが。それが言葉のおもしろさであり、恐さでもあるのだろう。
春日武彦の著作を読むようになったのは、彼独特の文学作品の読み方に興味をもったのがきっかけだった。小説をこんな切り口で読めるのかといった驚きがあった。作品の完成度ではなく、主人公のこだわりや生理などを手がかりに人の心理や意識の不思議を読み解いていく。文芸評論家のそれとは明らかにちがうこうした距離感は、彼が精神科医であることに関係あるのだろうとは思っていたが、この本を読むうちにさまざまなことが具体的に腑に落ちていった。たとえばこのような一文ある。
「それにして、わたしは言葉に興味があるからこそ精神科医として生きていけるのだなあと、つくづく思うのである」
なるほど、精神科の場合は治療すると言っても体の器官の一部を取り除いたり、破れを縫い合わせたり、パーツを取り換えたりというのとはちがう。対象となるのはブツである肉体ではなく心という曖昧模糊とした現象である。もちろん心の動きには体の器官が作用している。肉体あっての心なのだから当然そうなのだが、器官と心の働きとが必ずしも相関しないところに複雑さがある。
「診察室で患者と出会うということは、リフトに乗ったまま反対方向から互いに近づき、やがて擦れ違い離れていくといったイメージに近いところがあるように思える」
ここでも、ああ、なるほど、とつぶやかずにいられなかった。診察といっても心が収まっている体に触れることすらしないのである。状態を診るのに使われるのは言葉だけ。それが「言葉に興味があるから精神科医として生きていけるのだ」という感慨を生むのだ。
本書のタイトルは『臨床の詩学』だが、ふつう「臨床」という言葉と「詩学」は結びつきにくいだろう。日常生活に必須とはいえない文芸のなかでもとりわけ浮世離れしているのが詩の世界である。統合失調症やうつ病患者の切迫した状況とは異質なレベルにあるように見える。ところが、手にする道具は言葉だけという状態で患者にむかうとき、言葉の力によって現場が動いたり、緊張関係が緩んだりすることがあるという。論理的に煎じつめて発した言葉ではなく、会話の流れや差し迫った状況下で口をついてでた言葉が奇妙な効果を発揮するのだ。そこに著者は詩の言葉と共通する働きを見いだすのである。
こんな一例が挙げられている。入院が必要な患者が目の前にいる。さっきから説得しているが、「治療は拒否します。人権の問題だ!」と主張し膠着状態がつづく。そこに別の電話が入ったのであえて後回しにせずに出たあと、「失礼、あなたとは別の苦戦中の患者さんでした」と説明した。電話の前に彼に、あなたは苦戦中だが、ひとりで闘うのは辛い、援軍になろう、という言葉とともに紙に「苦戦中」と書いてそっと見せていたのである。患者の態度は相変わらだ。これ以上説得しても無意味で力づくもやむなしと男性の看護師を呼び、「さあ、援軍もそろったから、病室に行こう!」と言ったとたん、彼はすっと席を立って自分から病棟に入っていったというのである。
「「苦戦中」という言葉の提示が事態の分岐点となり、そこへ「援軍」といった言葉を重ねることで、N氏へ当方の思いがある程度伝わったのであった。そして今になって振り返ってみると、なぜ「苦戦中」という言葉を思いつき、しかもそれが有効であろうと信じたのか、そのあたりの経緯が自分のことながら判然としないのである。ただしあの診察の場では、思いついた途端にそれがきっとN氏に訴えかけるであろうと予測がついた。だからこそ、わざわざメモ帳に書いて相手にそっと見せるというような芝居がかった仕草もできたのである。何か確実な手応えをわたしは直感的に感じとっていたのである」
用意しておいた言葉ではだめだろう。またほかの医師がこのアイデアをまねて実践したところでうまくいくとも思えない。「思いつき」という非科学的な領域での出来事なのだ。では、その「思いつき力」を訓練するにはどうしたらいいか、というようなよくありがちな方向に発展していかないところにこの著作の特徴がある。「思いつき力」が訓練で得られるなら話は簡単ではないか。そうは問屋がおろさないところに人間の奥深さがあるし、その認識があるならば安易に自分の体験をマニュアル化はできないのである。
代わりに彼は数多くの詩を引用している。だれもが知っているようなメジャーな詩人の作品でないところがまたおもしろい。日常と地つづきのような言葉の列が途中でふっとくねり曲がって思わぬ岸辺に運ばれる。山崎るり子の「廃屋」、衣更着信の「老人」、柿沼徹の「木々」、小長谷清実「夢の中では」、相沢正一郎の「テーブルの上のひつじ雲テーブルの下のミルクティーという犬」など未知の詩ばかりだったが、こういう詩に触れ考え感じていることがある一瞬に「苦戦中」という言葉になって彼に舞い降りるのだろうと感得したのだった。
朝、ベランダに野鳥が飛んでくるように私のそばにも言葉がやって来てなにかが書けそうな気がするというめずらしい効果があったことも添えておく。