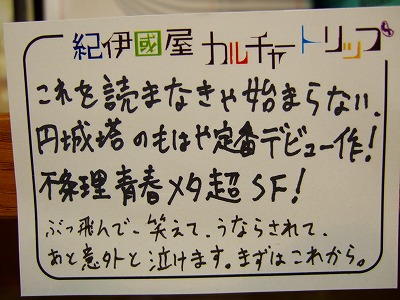『映画の身体論』塚田幸光編(ミネルヴァ書房)
「身体論が拓く可能性」
本書は全8章からなる。どの章も興味深いが、ここでは、評者が特に惹かれた第2章と第8章に焦点を当ててみたい(各章のタイトルと著者は文末に記した)。
これはまったくの一読者としての感想にすぎないが、身体表象をテーマにしたアンソロジー(複数の著者によって書かれた本)を手にとったとき、まず全体の統一感が欠けていることに戸惑いを覚えることがある。そして次に、「それぞれの章がどのように関連しているのか」「全体を通じて何を主張したいのか」といった疑問が次々に生じることがある。それは著者によって「身体」が指すものに幅があることに加え、その表象の分析手法が多様であることにもよるのだろう。
だが、本書にはそのような戸惑いや困惑を感じなかった。そこからは編者と著者間、著者相互の綿密な打ち合わせや用語、分析対象の擦り合わせの跡がうかがえる。映画用語集(小野智恵)が巻末に付されていることもその結果であろう。
編者は映画の身体論へと読者をいざなうにあたり、漫画(のちにアニメ、映画化)の『銀河鉄道999』(松本零士作)をまず紹介する。そこには、本書が映画ファンではない読者にも開かれているという意味が込められているのだろうが、それに加えて、例えば第1章で堀が触れているように、テレビや漫画といったほかのメディアとの関わり合いを通じて発生したり、変化したりする意味をもとらえようという意図があるように思う。編者の問題設定は明確だ。
「映画はいかに『身体』を描いてきたのだろうか。スクリーンが隠蔽(イン)/開示(アウト)する身体とは、文化的、社会的に構築される差異としての「身体」に他ならない。性やジェンダーや人種に接続する身体として、或いは国家的イデオロギーや政治的メタファーを逆照射する表象/身体として「身体」が包摂する領域は限りない。明滅するスクリーンの向こう側から呼びかける俳優の身体、そしてそこに同一化する観客の身体も忘れてはならないだろう。映画と身体との関係は複層的であり、その関係性は、網状のテクスト/コンテクストの中でキメラの如く変化する。当然のことながら、複数の身体をめぐる鉄郎(評者注、『銀河鉄道999』の主人公)の旅は、その一例に過ぎない」(「はしがき」ⅳ)
このように、映画のなかで見られる身体は実に多様な意味を帯び、さまざまな可能性へと接続される。各章では、その可能性が戦後まもなくの作品から比較的最近の作品までを例に饒舌に述べられる。
第2章は「ブルース・リーはいかに世界を変えたか」という見出しから始まる。そこで強調されるのは、西洋中心のヘゲモニーに反旗を翻すものとしての「≪ポストコロニアル≫ブルース・リー」と著者が呼ぶ視点である。西洋の帝国主義、資本主義に基づく<覇権的マスキュリニティ>に対し、映画におけるブルース・リーの身体は<周縁化されたマスキュリニティ>と位置付けられる。その身体による暴力が法の裁きという帰結を迎えることで、その反体制的メッセージを中和し、エンターテイメントとして作品を成立させているという著者の図式は分かりやすい。
また、そこでの身体をめぐって喚起されられた点がある。繰り返し用いられることからもわかるように、著者は「鍛え抜かれた類まれなる身体」という表現を基調としながらも、さらに微細ともいえる身体表現に注目しているのだ。それは、その暴力に憂いや苦しみが内包されているというや視点や、リーの甲高い雄叫びが主人公の<周縁化されたマスキュリニティ>を強化させているといった点だ。
しかし、著者は『燃えよドラゴン』以降の作品において、その図式が反転する様を見る。これらにおいては、これまで打倒すべき対象だった<覇権的マスキュリニティ>はリーが演じる主人公の内側にあるという。しかし、詳細に見ていくとそれは<擬態>(ミミクリー)であるなど、二項対立ではなく両義的で複雑なマスキュリニティの有り様をリーの身体に見るのである。
第8章は編者によって書かれているが、終章という位置づけのものではない。むしろ、ニューシネマにおける男性の身体、しかもシャワーやベッドのシーンという事例に絞り込んだ章だ。なぜ、女性ではなく男性の身体なのだろうか。著者は、男性身体を「ニューシネマの性と政治が交錯する『場』(トポス)」と考える。
著者は表現を抑制しながら、ポルノグラフィの文化的考察の可能性を論じることから議論を始める。興味深いのは、ポルノグラフィが内在されていた時代は、「異形」「奇形」も社会に許容されていたという点だ。
また、著者は「映画と『性』の関係は、検閲/コード抜きに考察することは不可能だろう」として、検閲とコードの歴史的過程をまとめている。シーンの分析に入る前にその歴史的、制度的、産業的な文脈を押さえておくことは、分析の手続きとして必要であることはあるとしても、それ以上に、ここではそれらが男性身体のスペクタクル(ショー/見世物)化と結びついていることを示唆していると考えられよう。
ポルノ産業では女性がスぺクタクルの対象となっているが、著者によると、ニューシネマではその視線のポリティクスは反転する。だが、その男性身体は女性の欲望/視線を集めるだけではなく、既存のジェンダーを攪乱させるものであるという。第2章もそうだったが、本章も既存の枠組みに身体表象を押し込もうとするのではなく、表象における身体と性の曖昧さ、その複雑さをとらえ、そこから次の研究へとつなげようとする視点が見られる。逆説的ではあるが、その意味では限定されたジャンルの個々のシーンを対象とした本章は、やはり終章として相応しいのだろう。
本書は分析対象を映画に限定したものであるが、その分析から考察されるものは映画に限らない。さまざまなメディアの相互の関係やその作用において、身体論、身体表象が拓く豊饒な可能性があることに気づかせてくれるものだ。
【各章のタイトルと著者】
第1章 運動家ゴダール―スポーツ、身体、メディア(堀潤之)
第2章 ≪ポストコロニアル≫ブルース・リー―カンフー映画における身体・マスキュリニティ表象をめぐって(山本秀行)
第3章 カウボーイと石鹸の香り―ハリウッド映画における男性の入浴シーンについて(川本徹)
第4章 ブラクスプロイテーション映画のアクション・ヒロイン―パム・グリアとタマラ・ドブソンの身体をめぐって(名嘉山リサ)
第6章 命短し芸は長し―市川雷蔵 銀幕に生き続ける身体(小川順子)
第7章 アメリカ戦中ミュージカル映画の系譜―進軍とアメリカーナ(松田英男) 第8章 メイル・ボディの誘惑―ニューシネマ、身体、ポルノグラフィ(塚田幸光)