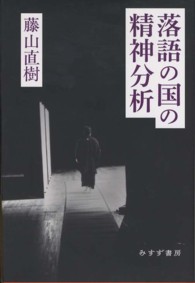『落語の国の精神分析』藤山直樹(みすず書房)
「先生、この噺を聞くと笑ってしまうのはなぜでしょう」
精神分析の先生が書く落語の登場人物論なんて読みたくないな。あの与太郎は○○病、この与太郎は□□症候群、江戸の昔からひとびとの心は病んでおり……そんなことで落語を聞く楽しみを邪魔されたくないからだ。でも本書を開くと早々に、精神分析家になるだいぶ前の落語大好き藤山直樹クンが現れて、夕方ラジオで聴いていた落語を憶えて保育園で披露したという逸話がある。五十代になってからは年に二、三度、落語を演っておられるというし、最初のこちらの思い込みは無用であった。
本書の主題はふたつ。ひとつは、落語の根多を、民衆が生み出したフォークロアとしてそこに働いた無意識を精神分析家として読み解くこと。もうひとつは、落語家という人間の生き方について、精神分析家である著者が〈ひとりでこの世を相手にしている〉ところに共通するものをみて論じること。「らくだ」や「粗忽長屋」、「文七元結」など私も好きな噺が並ぶ前者のテーマをおもしろく読んだ。
一本目は「らくだ」。死体が登場する噺は「粗忽長屋」や「黄金餅」などあるけれど最初から最後まで出ずっぱりなのは「らくだ」だと、言われてみればそうである。落語だからジツブツはもちろんないが、確かにいつも誰かのそばに馬さんの死体がある。半次や屑屋の語りによって、聞き手の意識から馬さんの死体が舞台に出たり入ったりしているわけだ。屑屋が死体と乞食坊主を取り違えてのオチで笑ってしまうのは、(間違えるなんてバカだなぁ、おいおい洒落になんないよ……)、これは〈部分的に彼らの狂気を楽しんでいる〉が、自分が〈いまだ正気であることを確認して喜んでもいる〉と言うのだ。〈だから私たちは笑っていられる〉。
薩長のお偉方の前で江戸っ子はどういうものかを教えてやろうと三遊亭圓朝が語ったと伝わる「文七元結」は、身を投げようとしている文七に通りすがりに出会った男が、自身にとってもかけがえのない五十両を渡して死ぬのを思いとどまらせる噺。この男はもちろんのこと、男のために自ら身を売っていた実の娘も、娘を担保にとはいえ博打好きのこの男に五十両貸した女将も、そんなひとっているかしらと思う半分、相手を信頼してとか自己犠牲とか誰かが見ているからではない勝手なふるまいをしていることに、そうしちゃうことってありそうと思える。それは〈かつて自分自身の体験した母性的な機能の遠い記憶がよみがえるから〉、〈自分自身の欲望をもたない、空の母親〉つまり無私なるものを恋い、憧れる思いであると言う。
※
患者として藤山先生を訪ねることはおそらくないけれど、もしそうなったら会話の中に、「落語が好きです。この噺を聞くともう笑っちゃって」というフレーズはきっと出てくるだろう。精神分析家とはそれにどのように対するのか、そもそも精神分析とはどういうものかわからないけれども、居心地の良い長椅子にこしかけて、紅茶でも飲みながら、藤山先生による精神分析を疑似体験したような読後感なのである。