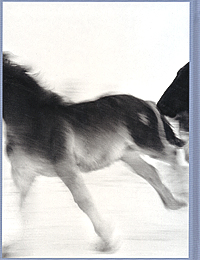小畑雄嗣写真集『二月 Wintertale』(蒼穹舎)
氷点下の世界、人と自然の接するところ
写真を写真展で見るのと、写真集で見るのとは別の体験である。これは絵画展と画集のちがいとは異なる。ホンモノと複製品という線引きが出来る絵画とちがって、写真の場合はどちらも複製品である。オリジナルプリントが出回ってから、「展覧会にかかっているのがホンモノ」で「印刷されたものはその代用品」とみなす傾向があるが、写真の本質はそこにはない。
いまから取り上げる『二月』というタイトルの写真集は、写真を写真集で見るとはどういう体験なのかを考えさせる、すぐれた例である。前のイメージがつぎのイメージとリンクして、意識下にあるものを浮上させ、思考や感情を刺激する。ページを繰っていくという本の形式が、視覚の活動を活性化するのだ。
裏表紙にタイトルがあるため逆さに開きそうになるが、馬の写真が貼り込まれたほうが表である。はじめに鹿の剥製の向こうにガスストーブが赤く燃えている写真があり、それを開くと屋外のスケートリンクの写真になる。
この写真、実はふたつの縦位置写真をつなげたものだ。右側は紅葉している秋の風景。左は冬の風景で季節がちがうのだが、違和感なく見てしまうところが不思議だ。公園の一部を凍らせただけの素朴なリンクにふたつの人影が立っている。はじめてリンクに立った少女と、彼女にスケートを教えようとしている母……とそんな想像が生まれる。
リンクのアップ、川べりの夕景、雪の中のメリーゴーランドがつづき、それをめくると初めて「二月」というタイトルが現われ、短い文章が載っている。北海道では校庭に水を撒いてリンクを作って滑るという話が記憶に残り、中標津を訪ねたのがはじまりだったこと。そこで隣町の「別海スピードスケート少年団」の名前を知ったこと……。
興味の対象を、この目で見ることからはじめるのは、写真家の習性だ。撮りながら感じ、考え、ひとつのシリーズを編み上げていく。「別海スピードスケート少年団」の活動を追ってそれだけで一冊作ることもできただろうし、別海という地域ぜんたいにテーマを広げて共同体の物語にする方法もあったかもしれない。だが、写真家はそうしなかった。冬の季節の人と自然の交わりにフォーカスし、宇宙の果てへと視線を伸ばした。
右から左へ、ページをめくる方向に何頭もの馬が走る。そしていきなり雪の結晶になる。きりっとした硬質なフォルム。ひとつとして同じ形のものはない。そのことに驚きながら凝視するうちに、視線が細かくなっていく。
馬と雪の結晶のペアがしばらくつづき、ようやくリンクに立つスケート少年たちが登場する。逆光に照らされたシルエットが劇的だ。時間は夜。周囲は暗い。リンク上を疾走する黒い影。氷上に残る無数の線のアップ。闇に響くスケート靴の歯音。これまでの写真で寒さを身に染みて感じている読者は、彼らの情熱に感銘せずにはいられない。
「別海スピードスケート少年団」は1960年代、別海に赴任した新卒の教師が水を撒いて人工のスケートリンクを作ったことからはじまった。やがてスケート団が結成され、町営リンクが出来、選手を輩出するまでになった、と途中に挟まれた説明文にある。長さ内容ともに好ましい。
橇遊びやホッケーや打上げ花火など冬の風物のカラーがつづき、ふたたびスケーターや雪の結晶のモノクロ写真にもどったところで、新たな山場を迎える。アメリカの農民で雪の結晶を撮影しつづけて生涯一冊の写真集を出したベントレー、その本に影響されて十勝岳に山小屋を建てて撮影をした雪の研究家、中谷宇吉郎博士のことが文章で紹介されるのだ。
ここに至って前半に入っていたモノクロの山小屋の写真は、中谷博士の白銀荘だったのではないかという想像が生まれる。雪の結晶写真が単なるイメージを超えて、本書を読み込むための駆動力に変る。さりげなく目にしていたものが意味を持ち、世界が広がっていく。『二月』というタイトルの意味が、結晶のように固まって腑に落ちる瞬間でもある。
奥付の後、再びカラー写真がつづいて、最後は雪道に立つ6人の若者の写真になる。手にカーネーションを持っているから卒業式の後かもしれない。なんということないカットだが、一度みたら忘れられない。みんな笑っている。撮影者にお別れを言っているようにも見える。
人だけを撮っても自然だけを撮っても足りない。人がそこでどんなふうに生きているのか、人と自然の結びつきの親密さこそを感じとりたいと思う。この写真集はその望みに思わぬ形で応えてくれている。