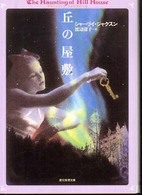『一六世紀文化革命』〈1〉〈2〉山本義隆(みすず書房)
|
|
|
それって要するに職人たちのマニエリスムなのである
17世紀の「科学革命」(トマス・クーン)を大掛かりに論じた『磁力と重力の発見』(〈1〉古代・中世/〈2〉ルネサンス/〈3〉近代の始まり)で2003年の出版界最大の成果をもたらした著者が、それには16世紀の「文化革命」が先行した筈だが、次にそこを詰めてひとつの文化史を完結させると漏らした「約束」が、こうして丸三年の歳月をかけて果たされた。
大部二巻。堂々たる読みでのある作品だが、主張は単純にして骨太い。芸術理論を枕に、外科学、解剖学と植物学、冶金術と鉱山業、算術と代数学、力学と機械学、そして天文学と航海術と地図制作と、目次を順にたどるだけで、文書偏重・文字崇拝のスコラ的思弁から出ようとせぬ中世来の旧守の諸学が、黒死病その他の流行病とか、火砲主体に変貌した戦場とか、広がる世界の未知の経験を前にお手上げになる中、大学アカデミーの外にあって蔑視されていたギルド的職人たちが新時代に即応する知を、印刷術というハードウェアの展開にのって外部に、ラテン語でなくヴァナキュラー(俗語)をもって公開し共有するというやり方で突破していった大きなうねりが、もう既にほのみえてくる。
以上、個別の学問分野での「16世紀文化革命」の展開を通覧したきた。それは外面的には学問の担い手の交代とその表現言語の変化として現れている。つまり職人や芸術家や商人たちが、俗語でもって自己表現を始め、それまでラテン語が専一的に支配していた文学文化の領域に越境したことで、知の独占の一角を崩したのである。しかしそれだけには止まらない。それは基本的には、視覚芸術における表現技法や技術者や職人の自然への働きかけの手順、そして商人による資本や商品を管理する手法、とりわけ的確な観察と精密な測定と正確な記録、総じて自然と世界に向き合う彼らの姿勢そのものが自然にかんする知識の獲得に有効であるという新しい認識であり、ひいては自然について知がいかなるものであるべきかという真理観の根本的な転換を意味していた。(p.621)
これに尽きている。こういうマクロ・スケールのまとめが山本氏は実に巧い。厖大な具体的データも必ずこういう展望が挟んでくれるので、読後、一片の散漫感もない。グラン・テーズ(大論文)の構成をよく知る、近頃の学者には珍しいほどきちんとした立論の空間は壮観だし、たわみも緩みもなく快い。
要するに、エリート貴族の子弟がラテン語でやる「韜晦(とうかい)体質」に凝り固まった大学アカデミーの「自由学芸(artes liberales)」が現実的な威力を何も持ちえなくなったとき、「機械的技芸(artes mechanicae)」を担う職人たちの「手でおこなわれる」知の営みが一世紀間、世界をつなぎ、世界を救った。文字通り世界を救ったのが医学アカデミーから締め出された理髪外科医たちで、大学の医学教授から賤業視された彼らが自らの一命を賭して悪疫禍の街区にとどまり、少しずつ対処法を模索していく間に、ガレノスべったりの「典籍医学」の方は為すすべもなく、尻まくって逃げ出す他ないという長々と続く逸話は、まさしく今日の大学ないし初中等教育が多くの場面において畳の上の水練以上のものでない状況にそっくりはね返ってくるようで、文書偏重のアカデミーに距離を置く山本氏は、はっきり現下の日本のアルテス・リベラレス(教養教育とも訳せる)の行き詰まりの構造を寓話として語っているのだ。自ら英会話できぬ英語教師、キーボード打てないメディア論教授の授業。この本で改めて“auctoritas”が権威/文庫の両義語であることを思い出させられたが、ロゴサントリックな教育現場が視覚文化的(oculocentric)な現実にブレーキにしかなっていない状況を、山本氏自身いらいらしながら描く16世紀ヨーロッパにどうしても透かし見てしまう。結局は例えば『アートフル・サイエンス』のB・M・スタフォードと同じ激しい現代批判を16世紀に仮託して綴った、と見るのが最高の読み方かと思う。
スタフォード本と、印刷書籍に複製される図像・図版への圧倒的評価でも通じる。タッコラやフランチェスコ・ディ・ジョルジョの機械製図法が見事な「グラフィック・デザイナー」たるレオナルド・ダ・ヴィンチの解剖図やアゴリコラの『デ・レ・メタリカ』の鉱山断面図に継承され、かくて「芸術性を有する科学資料というジャンル」がつくりだされるのだが、「美術史」はこれを評価できないでいる。いや、こういう文字通りの「アートフル・サイエンス」については既に荒俣宏の『想像力博物館』や「ファンタスティック12」シリーズが存分に切り込んでいると思うのだが、山本氏の文章や文献一覧にはスタフォードも荒俣もまるで出てこない。
ここまでゲリラ戦に出た相手にだから言ってもよいと思うのだが、あまりにもひと昔前の参考書ばかりなのに喫驚。そりゃ偉大な人とは思うが今さら下村寅太郎でもあるまいに、と感じた。今、『磁力と重力の発見』を書くに、Hélène Tuzet, "Le cosmos et L'imagination"(1965)もなく、Fernand Hallyn, "La structure poétique du monde : Copernic, Kepler"(1987)なくてどうする?『十六世紀文化革命』綴るに、Michel Jeanneret, "Perpetuum mobile"(1997)なく、Jessica Wolfe, "Humanism, Machinery, and Renaissance Literature"(2004)なくてどうする?結構不可欠な本ばかり。
全巻のキー・イメージは「手」である。スコラ学者どもの「頭」に対峙、ということなのだが、アルス・メカニカエの「メカネー」の語源も「手」ということである。そして全巻、技師・職人たちの「文化革命」はまず「芸術家にはじまる」という素晴らしい出だしを構えたのなら、何故「マニエリスム(mannerism)」が「マヌス(manus 手)」に由来し、そのマニエリスムがまさしく16世紀精神史において今最大のキーワードたることに、これだけ浩瀚厖大の本にしてただ一言の言及もないのか。さかんに狂言回しに登場する悲劇の陶工ベルナール・パリッシーにして、現在はまずそのマニエリスムが話題になるはずだ。この本で紹介された奇人ラメッリは、ホッケの16世紀マニエリスム美学の研究『迷宮としての世界』(1957)に、その「読書機械」という奇怪なメカが紹介されていておなじみだが、そこでのホッケの説明も不備。『迷宮としての世界』は山本著と併せて読むと異様に面白かったりする。
もと東大全共闘の、ぼくなど仰ぎ見ていたトップだった著者。アインシュタインの再来と言われ、勿体ながられたがキャンパスに残らず、潔く駿台予備校講師に。最新情報に疎くなりがちな氏を、ファンのネットワークが支えてきた。素晴らしい。今日インターネットは下手な大学百個に勝る。ネットワーキングが偉大な学を成り立たせた最右翼が山口昌男人類学、そして最左翼が山本義隆科学史/文化史、という印象である。
であるが、それにしてもそのネットに、まさしく「芸術家にはじま」ったマニエリスム・ムーヴメントのデータが何ひとつ引っかかっていないらしいのが口惜しい。マニエリスムこそは、芸術家の「頭」と職人の「手」の間で激しく交錯した16世紀きっての問題的現象だった。ジャック・ブースケの『マニエリスム美術』(1964)を覗いても、エウジニオ・バッティスティの『反ルネサンス』(1989)を見ても、山本氏がとりあげた画家や職人の仕事が片端から「マニエリスム」と呼ばれている。月刊『ユリイカ』誌「マニエリスムの現在」特集号にわざわざ人を頼んで、マンリオ・ブルーサティン「厖大なる労働」という職人マニエリスム論の傑作を訳載したのに、山本さんの目には触れていないみたい。