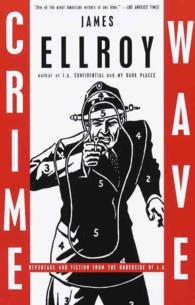『穴』小山田浩子(新潮社)
「現実への深い理解が生み出す幻想譚」
日本中にうんざりするほど均一な風景が広がっている。全国展開のスーパーやチェーン店やコンビニ、その店頭に立っている原色の幟、同一規格の建材で造られた注文住宅やビル。目立つことを意識したそれらは、色も形も似通って差がわからないけれど、ああ、知っている、と思わせるのがポイントだから、それでいいわけだ。
小山田浩子の芥川賞受賞作『穴』」は、そのような視覚情報により均一化された現実界、名前で納得した気にさせられる記号的世界の裏側を示して見せる。
夫の転勤先が彼の実家のある街に決まり、うちの借家に住めばいいと姑に言われて若夫婦はその家に引っ越す。同じ県内だがかなりので田舎で、前の職場を辞めた妻の「私」は当面何もすることがない。あるとき、実家の裏手の小屋に夫の義兄と称する男が暮らしているのを発見する。夫は一人っ子の長男で、兄がいる話は聞いたことがないが、男はその小屋にもう20年も暮らしているという。
いまの言葉だと「引きこもり」になるが、その義兄には長く隠棲していた陰気さはない。自分自身の見極めがついて弁舌さわやかで、家を出た理由も「家族と合わなかったんだなあ!」と実にふるっている。
「親父やおふくろがやろうとしていることは、ただ一つ、ぼくという子孫をどうにかして次の世代に生きて残そうとしているわけです。それが僕には気味が悪いです。悪かったんです。わかりますか? わかるわけないか。はは、わかっちゃ困る、ね、謀反を起こすのは一族に一人で充分だ。ね、僕はそれにいたたまらなくなって、逃げた」
家族や、共同体や、それが作りだす人間関係に自分を合わせられない人間は、いつの時代にも存在する。血がつながっているからといってウマが合うとは限らず、猿山の離れ猿のように群れから距離を置いて生きようとする者は必ず現れる。それが可視化されているか、見えないところに隠されているか。時代の差があるとすればそこだろう。
義兄に「私」を引き会わせたのは得体のしれない黒い獣である。「私」は数日前、用足しに近所に出たときにこれを見かけ、何だろうと追っていくと、穴に落ちてしまう。隣の奥さんの手を借りてようやく脱出するが、後日、それと同じ生き物が実家の門をすたすたと入っていくのを見て、あとをついて行き、義兄に遭遇したのだった。
近所に怪しげな家があって、素性のわからない人が住んでいて、その人が意外と子どもに人気があるというようなことは、これまでも物語や映画によく描かれてきたし、実生活でも経験している。その意味で義兄は古典的な人物と言えるし、親しみを抱きやすい。不可視の彼と「私」をつなぐのが、古井戸の穴が好きでやってくる黒い獣だというアイデアも、めずらしくはないかもしれない。むしろこの作品の新しさは、そうしたモチーフよりもそれらを組み立て、物語る手法のほうにあるように思われる。
導入から現実を浮遊した視座にすれば、非現実に移行するのはたやすい。そういう方法はこれまでもよく採られてきたが、作者が選んだのはそうではなく、ドキュメンタリーのように冷静で淡々とした文体である。外界で起きている事柄を徹底して観察し、自分の内部すらも他者のもののように眺める視点が、現実と非現実のバランスをとる役目をしている。非現実のほうに比重がいって「お話」に傾かないよう、視覚の力で現実を手元に引き寄せながら、見えない世界へとゆっくりと移行していく。
生理感覚や皮膚感覚だけではこうした離れ業はできない。物語を立脚させる現実社会と、そこに生きる人間のメカニズムへの骨太な理解がなくてはならない。幻想的な内容に深いリアリティーをもたらしているのは、いまという時代を見据えるたしかな視線なのだ。
著者は広島在住だが、地方をベースに、地方限定のネタではなく、都市にも共通するテーマが取り上げられていることも興味深い。そういう時代に、私たちが生きているということだ。