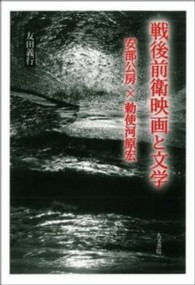『戦後前衛映画と文学 安部公房×勅使河原宏』 友田義行 (人文書院)
安部公房と勅使河原宏監督の「協働」を跡づけた本であり、きわめて刺激的である。
安部公房の世界的な名声はカンヌ映画祭で特別賞を受賞した映画版『砂の女』の成功によるところが大きいが、この作品は勅使河原監督との「協働」の第二作にあたり、安部はみずから脚本を何バージョンも執筆している(主人公をアメリカ人としたシノプスまで残っている)。
本書は第一章「協働の序章」で前衛芸術運動に邁進した若い日の安部と勅使河原の活動をたどっている。
安部と勅使河原の「協働」は1962年の『おとし穴』にはじまり、1970年の大阪万博の自動車館で上映された『一日二四〇時間』までの七作品で区切りをつけ別の道を歩むようになるが、二人の出会いは戦後復興期の前衛芸術運動の時代にさかのぼる。引きあわせたのは岡本太郎で、「世紀の会」で活動し、『世紀群』という同人誌を共に発行している(埼玉近代美術館の「勅使河原宏展」で実物を見たが、ガリ版印刷とは思えないくらい美しかった)。
この時期、勅使河原は草月ホールのディレクターとなって意欲的な企画を次々とプロデュースし、草月ホールは前衛芸術運動の拠点となっていく。こんなに刺激的で潑刺とした時代があったのかとうらやましくなった。
第二章「文学と映画の弁証法」では1958年から1960年にかけて映画人のみならず文学者も巻きこんで戦われた「映像と言語論争」を軸に、実作に乗りだそうとしていた時期の安部と勅使河原の映画論を検証している。
論争は羽仁進のモンタージュの再検討を端緒とする。モンタージュはカットを単位にしてたが、羽仁は『教室の子供たち』の演出経験からカットの単位までばらばらにしてしまうと子供たちの生き生きとした姿が失われてしまうと気づき、より長いシークェンスを単位とすべきことを提唱した。それにネオリアリズモの「カメラ万年筆」説に触発された岡田晋が呼応し、状況自体にドラマがあるのだから映画作家が勝手に編集でドラマを作りだす必要はないというモンタージュ終焉論にまで先鋭化する。そして映像は言語に代わりうるとしたために映像言語と一般言語が同等かが問われることになった。
安部は羽仁=岡田説は言語による思考と映像による思考という虚妄の二元論にたつものと批判し、映像表現は言語を媒介にしてのみ可能であり、芸術の総合化はあくまで文学を中心にすべきとした。演劇においては安部独自の方法論は演出家として既成の俳優と係わる中で「安部システム」へと結実していったが、映画においては実作に係わりはじめる前に理論が深められていたのは興味深い。
一方、勅使河原は理論には関心はなく、論争に積極的にコミットしなかったものの、モンタージュという技法を堅持しつつも、長回しで対象に内在するドラマに接近していく羽仁の姿勢を評価し、それが撮影中の偶然を重視する演出につながったという。
第三章ではいよいよ「協働」の第一作『おとし穴』を論じている。『おとし穴』は九州朝日放送で放映された『煉獄』というTVドラマがもとになっているが、TVドラマが抽象的なセットだったのに対し、『おとし穴』では40ヶ所以上をロケハンし実写で作りあげた。ロケにこだわったのはぼた山や陥没湖、炭住といった歴史性をもった実景をとりいれるだけでなく、「意識の外にはみだした偶発的なもの」(安部公房「新記録主義の提唱」)を活かすためでもあった。『おとし穴』がドキュメンタリー的手法をとりいれたといわれる所以である。
『おとし穴』は組合幹部の身代わりに殺された渡り坑夫の幽霊を主人公とするが、著者はこの選択に共産党と社会主義的プロパガンダからの離反を見ている。大炭鉱の坑夫は組合で団結できるが、零細な中小炭鉱はろくな設備もなく、最底辺の渡り坑夫に危険きわまりない作業をさせて生き血を搾り取っている。次の要約は正鵠を射ている。
中小炭鉱に生きた人々の、不条理なまでの無力と悔しさが引き立つこの映画は、言葉さえも奪われた坑夫たちの記録と表象に挑んでいる。殺された直後、生者に声が伝わらないことを知った坑夫の「本当に、せつねえこっちゃのォ」という言葉は、未来永劫続く空腹感とも重ねて身体化される、無念と憤怒の表出である。